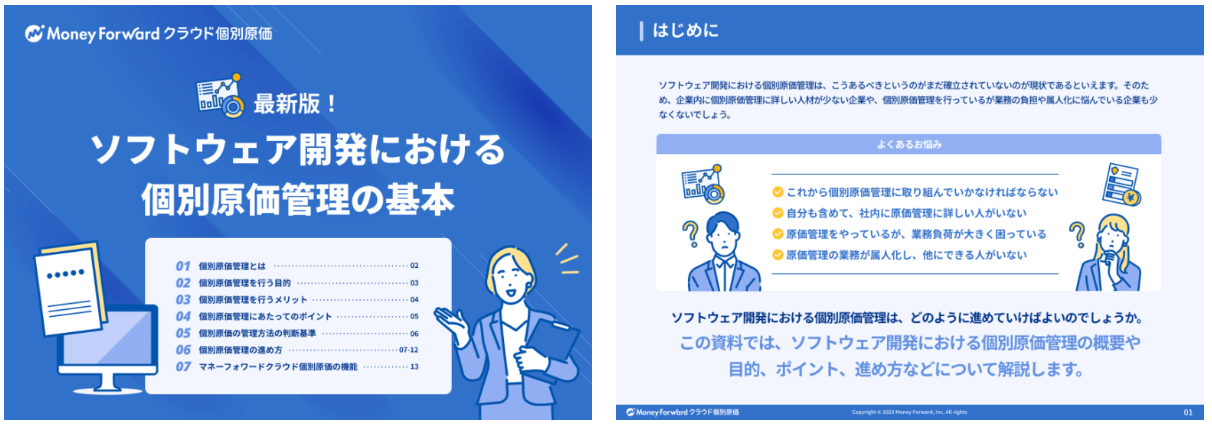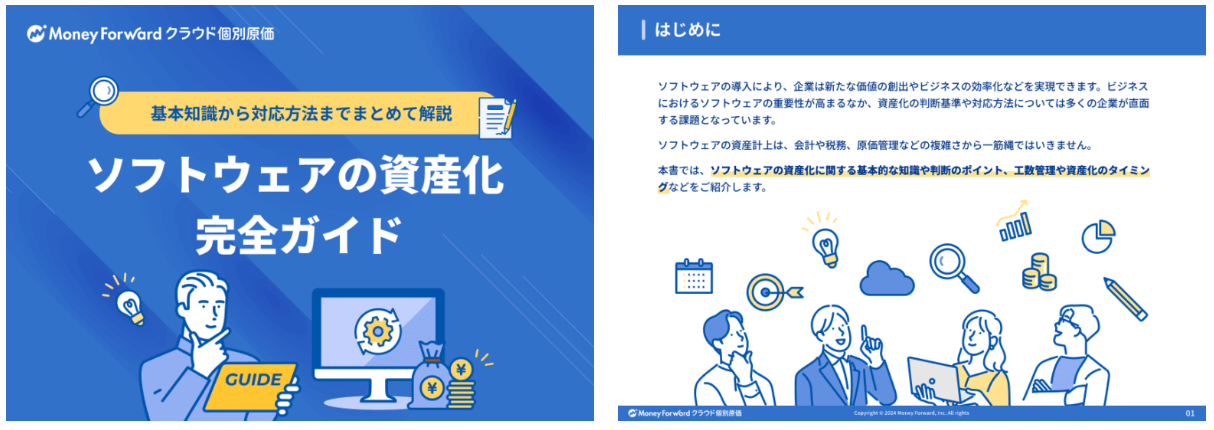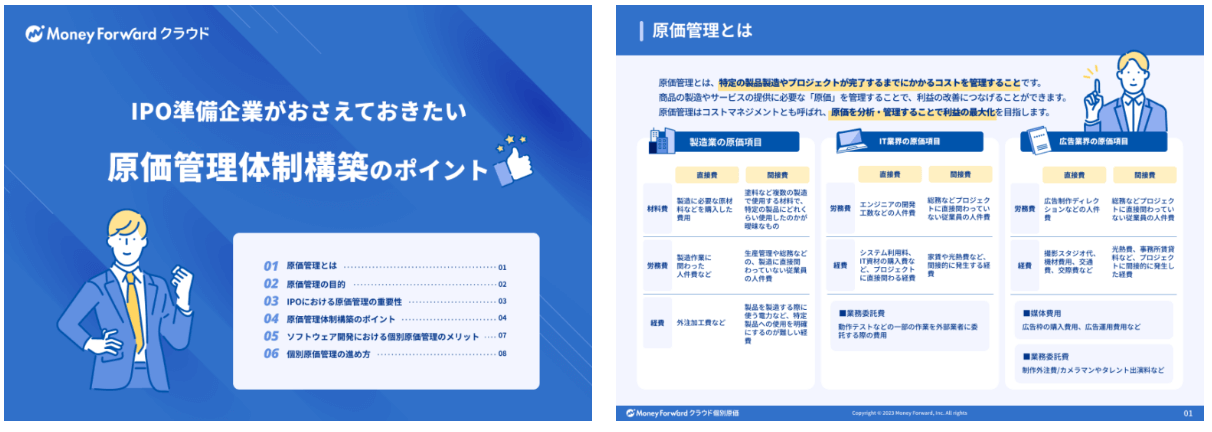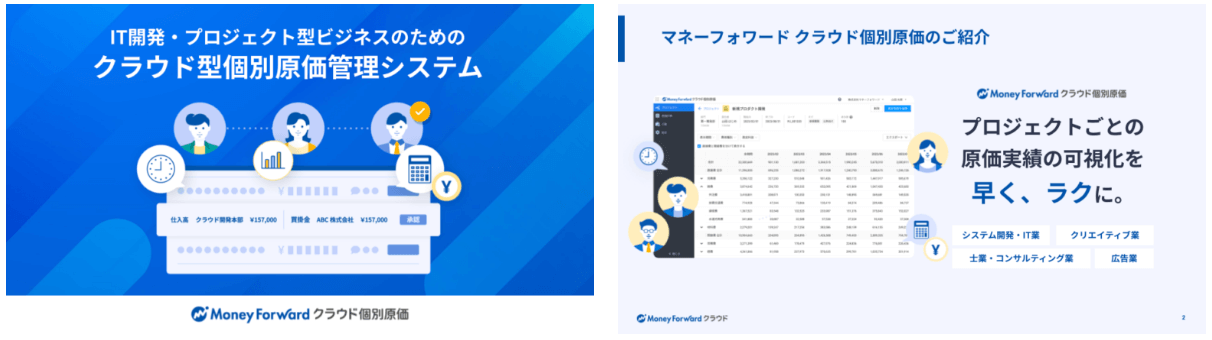- 作成日 : 2025年8月5日
工数の単位とは?人時、人日、人月や一人工など各業界の例、計算方法を解説
プロジェクトの計画や進行管理では「工数」の把握が欠かせません。人時や人日、人月といった単位が登場しますが、それぞれの違いを正確に理解しておかないと、見積もりやスケジュールに誤差が生じる恐れがあります。本記事では、工数の定義から各単位の違い、計算方法、実際の使い分けまでをわかりやすく解説します。効率的なプロジェクト運営に役立ててください。
目次
工数とは何か?
工数とは、特定の作業を完了するために必要な作業量のことです。時間と人の組み合わせによって数値化され、計画やコスト管理、進捗確認の指標として使われます。たとえば、あるタスクを3人で5日間かけて終わらせた場合、その作業量は「15人日」のように表します。
この工数という考え方を使うと、プロジェクト全体の大きさや、それをやり遂げるためにどれくらいのメンバーや期間が必要なのかを、感覚ではなく数字でしっかり捉えられます。数値に基づいた計画や見積もりができるので、プロジェクトを進める上では欠かせない計算になります。
ウェブサイト作成の工数の例
1人のデザイナーが1ページ分の画像を差し替えるのに2時間かかるとします。これは「2人時」に相当します。5ページ分の作業なら「2時間 × 5ページ = 10人時」です。これを人日に換算すると「10人時 ÷ 8時間 = 1.25人日」となります。
2人で同時に作業すれば、約0. 625日(約5時間)で完了できる計算になります。1人のデザイナーが1ページ分の画像を差し替えるのに8時間かかるとします。これは1人日です。同じ作業を5ページ分行うなら、理論上5人日が必要です。2人で並行して行えば、2.5日で完了できる計算になります。
工数の単位:人時・人日・人月の違いと計算式
工数を表すとき、時間の長さに応じて主に3つの単位「人時」「人日」「人月」が使われます。それぞれの単位は、プロジェクトやタスクの規模に合わせて使い分けられます。
人時(にんじ)
人時(にんじ)は、1人が1時間で終わらせられる作業量を「1人時」とする単位のことです。工数を考える上で一番短い時間の単位で、英語では「Man Hour」、略して「M/H」と書かれることもあります。
計算式は「作業時間(時間数)× 作業人数」で表します。
たとえば、3人で5時間かかる作業なら、その工数は 3人×5時間=15人時 と計算します。
また、カスタマーサポートが1件のメール対応に平均15分かかるとすると、1時間で4件処理できます。10件対応するには2.5人時が必要になります。
このような時間単位の管理に人時は便利です。
人日(にんにち)
人日(にんにち)は、1人が1日で終わらせられる作業量を「1人日」とする単位のことです。建設業界などでは「人工(にんく)」と呼ばれることもあります。
英語では「Man Day」、略して「M/D」と書かれる場合もあります。
計算式は「作業日数 × 作業人数」です。
ここでポイントになるのは、1人日の「1日」が具体的にどれくらいの働く時間を示すかという点です。一般的には、1人日は「1日8時間労働」を前提として計算されます。これは、休憩などを除いた実際に作業する時間として考えることが多いです。
たとえば、開発者5人が10日間作業した場合、工数は 5人×10日=50人日 となります。この50人日は、50人日×8時間/人日=400時間 の総作業量があることを意味します。
人月(にんげつ)
人月(にんげつ)は、1人が1ヶ月で終わらせられる作業量を「1人月」とする単位のことです。英語では「Man Month」、略して「M/M」と書かれることもあります。
計算式は「作業月数 × 作業人数」です。
人月を計算するときの「1ヶ月」は、カレンダーの1ヶ月(30日や31日)ではなく、営業日数を基準に考えます。一般的には、「1ヶ月あたり20営業日」を前提として計算されることが多いです。
したがって、「1人月」は「20人日」に相当すると考えられます(1人月 = 20人日 = 20日 × 8時間/日 = 160時間)。
たとえば、開発者5人が3ヶ月作業した場合、工数は 5人×3ヶ月=15人月 となります。
システム開発や大きな製造プロジェクトなど、数ヶ月から年単位にわたる中長期的なプロジェクトの工数を見積もるときによく使われます。
各業界における工数の単位例
工数の考え方は業界によって表現や単位が異なることがあります。一般的な人時・人日・人月のほかにも、それぞれの現場で使われる実務的な単位があり、それぞれの業務特性に適した形で活用されています。
建設業:一人工(いちにんく)
建設業界では「一人工(いちにんく)」という単位がよく使われます。これは「1人の作業員が1日(通常8時間)現場で働く労働量」を意味し、実質的には「1人日」とほぼ同じ考え方です。
計算式としては「(1人 × 作業時間)÷ 8時間」もしくは 、「人数 × 日数」で表します。
現場では契約や請求の単位として使われることが多く、たとえば職人が朝から夕方まで働いた場合、たとえ実際の作業時間が短くても「1人工」としてカウントし、1日分の最低保証のような意味合いを持つこともあります。
外注費や原価を計算する際の基礎となり、「左官工1人工あたり〇万円」のように、人工代(にんくだい)として単価設定を行います。
製造業:機械時
製造業では、人の労働力だけでなく、設備や機械の稼働も生産量に大きく関わります。そのため、人の作業工数(人時・人日など)に加えて、機械がどれだけ動いていたかを示す指標も重要になります。
たとえば、「機械1台が1時間稼働した時間」を「1機械時」のように捉え、設備ごとの稼働工数を管理することがあります。NC旋盤が10時間稼働すれば「10機械時」となり、その間に必要な人員の工数は別途管理されます。
また、機械が実際に正常に動いていた時間を示す「可動率」(実可動時間 ÷ 総運転時間) や、一定時間内にどれだけ生産できるかを示す「タクトタイム」 なども、生産性分析や設備投資の評価、原価計算において重要な指標となります。
人の工数計算「作業時間 × 作業者数」 と合わせて、これらの機械に関する指標も管理することで、より正確な生産計画やコスト管理が可能になります。
コールセンター業界:AHT(平均処理時間)
コールセンターでは、直接的な「工数」という単位よりも、オペレーターの業務量を測る指標として「AHT(Average Handle Time:平均処理時間)」がよく用いられます。AHTは、顧客からの問い合わせ1件あたりに対応するためにかかった時間の平均値を示します。
「ATT(Average Talk Time:平均通話時間)」と「ACW(After Call Work:平均後処理時間)」を足して計算されます。
つまり、「(通話時間の合計+後処理時間の合計)÷総対応件数」で算出されます。
たとえば、AHTが6分であれば、1時間あたり10件の問い合わせに対応できる計算になります。このAHTを管理・分析することで、オペレーターの生産性やコールセンター全体のサービスレベルを把握し、人員配置やシフト設計、業務改善に役立てています。
医療・介護業界:サービス単位
介護保険サービスや一部の医療サービスでは、「単位」という考え方が使われます。これは、提供されるサービスの種類や内容、所要時間、要介護度などに応じて国が定めた点数のようなものです。
たとえば、訪問介護で「身体介護20分未満なら163単位」「生活援助45分以上なら220単位」のように、サービスごとに細かく単位数が決められています。
実際に事業所に支払われる介護報酬(サービス費用)は、この「合計単位数」に「1単位あたりの単価」を掛けて計算されます。
1単位の単価は基本10円ですが、地域ごとの人件費水準などを考慮して調整され、10円から11.40円程度の幅があります。
この「単位」は、提供されたサービスの労力や価値を数値化したものであり、実質的な工数管理の基準としています。
イベント業界:スタッフ日数・人員日数
イベント会場や展示会などでは「スタッフが1日動員された数=1人日」として計上されます。
たとえば3日間のイベントに10人が毎日稼働すれば「30人日」となり、人件費や弁当、宿泊などの手配もこの単位で見積もられます。
繁忙期や大型イベントではこの「延べ人数」をベースに全体の人員配置やコスト設計が行われます。
工数の見積もり精度を高めるポイント
工数見積もりはプロジェクトがうまくいくかどうかを左右する大切なポイントです。見積もりの精度が低いと、予算オーバーや納期遅れといったリスクが高くなります。
見積もりの精度を高めるには、一つの方法だけに頼るのではなく、複数のやり方を組み合わせてもよいでしょう。ここでは、具体的な方法と考え方を紹介します。
工数の見積もり手法
工数見積もりには、いくつかの代表的な方法があります。プロジェクトの性質、使える情報の量や質、見積もりの段階などに応じて、適切な方法を選ぶことが精度アップにつながります。
- 類推法
過去に行った似ているプロジェクトやタスクの実績データをもとに見積もる方法です。過去のデータが正確で、今のプロジェクトと似ていれば、比較的短い時間で精度の高い見積もりができます。ただし、完全に同じ条件のプロジェクトは少ないので、違いを考えて調整が必要です。 - ボトムアップ法(WBS法)
プロジェクト全体の作業をWBS(Work Breakdown Structure)という手法でできるだけ細かいタスクに分け、一つ一つのタスクの工数を見積もって合計する方法です。作業の抜け漏れを防ぎやすく、信頼性の高い見積もりが期待できますが、タスクを洗い出して見積もるのに時間がかかりがちです。 - 三点見積もり法
各タスクについて、「楽観値(一番早く終わる場合)」「最可能値(一番現実的な場合)」「悲観値(一番遅く終わる場合)」の3つの工数を見積もり、特定の計算式(例:(楽観値 + 4 × 最可能値 + 悲観値) ÷ 6)を使って期待値を計算する方法です。不確実性を考えに入れやすく、関係者との合意形成にも役立ちます。 - 係数法(パラメトリック法)
過去のデータから、特定の要素(例:機能の数、画面の数、作る個数など)と工数の関係を示す係数を見つけ出し、それを今のプロジェクトの要素に当てはめて工数を計算する方法です。統計的な根拠に基づいて客観的な見積もりができますが、信頼できる過去データと、場合によっては専門知識が必要になることもあります。
日々の工数管理を効率的に進める手順
工数管理は、プロジェクトが始まる前の見積もり作成で終わりではありません。プロジェクトが進んでいる間、どの作業にどれだけの時間がかかったのか(実績工数)を日々記録し、最初の見積もり(予定工数)と比べて分析することが大切です。
効率的な工数管理は、一般的に以下の手順で進められます。
- 工数入力:プロジェクトに参加している各メンバーが、毎日の業務で「どのタスクに」「どれくらいの時間」を使ったのかを記録します。入力はできるだけ作業直後に行うのが、記憶違いによる不正確さを防ぐ上でおすすめです。また、入力が習慣になるような仕組みやツールを導入するとよいでしょう。
- 集計:メンバーが入力した実績工数のデータを、プロジェクトごと、タスクごと、メンバーごと、期間ごとなど、分析に必要な切り口でまとめます。手作業での集計は手間がかかり、ミスも起こりやすいため、ツールやアプリを活用します。
- 予実比較:集計された実績工数と、事前に作った見積もり工数(予定工数)を比べます。これにより、計画に対して進捗が進んでいるのか遅れているのか、特定のタスクで思った以上に工数がかかっていないか、といった違いがわかるようになります。
- 分析・改善:予実比較でわかった違いの原因を分析します。たとえば、特定のタスクで遅れが出ている場合、その原因は見積もりが甘かったのか、予期せぬ問題が起きたのか、担当者のスキルに問題があったのかなどを探ります。分析結果をもとに、スケジュールの見直し、メンバーの再配置、作業プロセスの改善、追加のサポート提供など、必要な対策を決めて行います。そして、その結果を次の工数管理サイクルに反映させていきます。
この「入力→集計→比較→分析・改善」というサイクルを継続的に回すことで、プロジェクト管理の精度が徐々にアップしていきます。
この日々の工数管理をうまく機能させるためには、ツールやプロセスを整えるだけでなく、チームメンバー全員の協力が欠かせません。メンバー一人ひとりが、工数入力の目的を理解し、責任を持って正確なデータをタイムリーに入力する必要があります。
管理者は、その目的をはっきり伝え、入力しやすい環境を整えるとともに、入力されたデータが信頼できるものかを確認しましょう。
Excel(エクセル)で工数管理をする場合
Excel(エクセル)は、導入コストをかけずに工数管理を始められます。多くの人が基本的な操作に慣れており、使い方を覚える時間が少なくて済む点も良い点です。
また、管理したい項目に合わせて列を追加したり、計算式を入れたりと、比較的自由にフォーマットをカスタマイズできます。個人や少人数のチーム、管理項目が比較的シンプルなプロジェクトであれば、Excelでも十分に対応できます。
ただし、Excelでの工数管理には、いくつか注意したい点があります。まず、実績工数の入力は基本的に手作業になるため、メンバーの入力負担が大きく、入力漏れや入力ミス(ヒューマンエラー)が起こりやすいです。特にプロジェクト数やメンバー数が多くなると、データの集計や分析にもかなりの手間がかかります。
また、データ量が増えるとファイルの動作が重くなったりする心配もあります。複雑な分析機能やレポート作成は標準では付いておらず、マクロや複雑な関数を駆使する必要があり、結果として特定の担当者にしかメンテナンスできない「属人化」の状況が生まれがちです。
大規模なプロジェクトや、高度な分析・管理が必要な場合には、有料ツールの導入も視野に入れて検討するとよいでしょう。
工数管理の無料テンプレート
マネーフォワード クラウドでは、工数管理の無料テンプレートをご用意しております。ご自由にダウンロードしていただけますので、ぜひお気軽にご利用ください。
ツール・アプリで工数管理をする場合
近年ではクラウド型のプロジェクト管理ツール(Backlog、Redmine、Asanaなど)も広く使われています。これらを活用することで、リアルタイムで工数を管理しやすくなります。
以下に、代表的なツールとその特徴を簡単に紹介します。
Backlog(バックログ):タスク管理、バグ管理、バージョン管理など、開発プロジェクト向けの機能が充実していて、ガントチャートやカンバンボードで見た目で進捗管理もできます。
Lychee Redmine(レッドマイン):オープンソースのプロジェクト管理ツール「Redmine」をベースに、ガントチャート、工数管理、リソース管理、コスト管理などの豊富な機能を追加したツールです。
Brabio!(ブラビオ):「Excelより10倍速いガントチャート作成」をうたい、初心者でも直感的に操作できるシンプルな画面が特徴です。5名まで無料で使えます。
Jooto(ジョートー):カンバン方式のタスク管理が特徴で、見た目で進捗を把握しやすいツールです。無料プランもあります。
TimeCrowd(タイムクラウド):時間計測(タイムトラッキング)に特化し、「どの業務にどれだけ時間がかかっているか」を簡単に見える化できるツールです。
TeamSpirit:勤怠管理、工数管理、経費精算などをまとめて管理できるプラットフォームです。勤怠データと工数データを連携させて、正確な原価管理をしたい会社に向いています。
CrowdLog(クラウドログ):工数入力のしやすさとレポート機能の豊富さが特徴で、プロジェクトの損益管理にも対応しています。
Asana(アサナ):タスク管理、ワークフロー管理に強く、タイムトラッキング機能やレポート機能も備えています。色々な外部ツールとの連携も豊富です。
これらのツールは、機能、料金体系(無料プランがあるか、ユーザーごとの課金か固定料金かなど)、サポート体制、連携できる外部サービスなどが異なります。
ツールを選ぶ際には、まず自社が工数管理によって何を達成したいのか(目的)、どんな機能が必要か、予算はどのくらいか、メンバーが使いこなせるか、といった点をはっきりさせることが大切です。
多くのツールで無料トライアル期間が設けられているので、実際に試してみて、自社の業務の流れや文化に合っているかを確認するのがおすすめです。
この記事をお読みの方におすすめのガイド4選
最後に、この記事をお読みの方によく活用いただいている人気の資料・ガイドを紹介します。すべて無料ですので、ぜひお気軽にご活用ください。
最新版!ソフトウェア開発における個別原価管理の基本
ソフトウェア開発における個別原価管理にお悩みではありませんか?
ソフトウェア開発における個別原価管理の基本から、その目的やメリット、具体的な進め方までを詳しく解説します。
ソフトウェアの資産化完全ガイド
ソフトウェアの資産計上は、会計や税務、原価管理などの複雑さから難易度が高く、うまく進められていない企業も多いのではないでしょうか?
ソフトウェアの資産化に関する基本的な知識や判断のポイント、工数管理や資産化のタイミングなどを解説します。
IPO準備企業におすすめ!原価管理体制構築のポイント
個別原価管理は、IPOに必要とされるあらゆる経営管理体制の構築・運用と密接に関連しており、非常に重要です。
これから原価管理をはじめる企業向けに、体制構築のポイントや進め方を解説します。
マネーフォワード クラウド個別原価 サービス資料
IT開発・プロジェクト型ビジネスのための個別原価管理システムをお探しではありませんか?
マネーフォワード クラウド個別原価は、個別原価計算はもちろん、プロジェクト申請・工数入力・資産振替・レポート作成までの一連の業務をワンストップでサポートします。
※ 掲載している情報は記事更新時点のものです。
※本サイトは、法律的またはその他のアドバイスの提供を目的としたものではありません。当社は本サイトの記載内容(テンプレートを含む)の正確性、妥当性の確保に努めておりますが、ご利用にあたっては、個別の事情を適宜専門家にご相談いただくなど、ご自身の判断でご利用ください。
関連記事
ヒューマンエラーとは?発生原因や防止策、他社事例を解説
ヒューマンエラーが発生する原因は、知識不足や経験不足、業務の慣れによる手抜き、集団欠陥、複雑な業務フローの影響などさまざまです。 ヒューマンエラーが発生すると、労働災害や社会的信用…
詳しくみるテレワークのセキュリティリスクと対策とは?よくあるリスクと運用のポイントを解説
コロナ禍による変化で、従来の会社に出社する働き方からテレワークへの移行が増えています。情報セキュリティ10大脅威2023にも掲載があるように、昨今はテレワークに関連するセキュリティ…
詳しくみるBCP対策マニュアルの作り方実践ガイド【病院・介護施設対応】
災害や感染症、サイバー攻撃などの非常事態に備える「BCP(事業継続計画)」の策定は、事業継続に必須です。しかし、実際にマニュアルを作ろうとすると「何を書けばいいのか」「厚労省のテン…
詳しくみるERPとBIツールの関係とは?これらツール連携のもたらすメリットなどを徹底解説
近年では、企業内部のデジタル化とともに、ERPの導入が進みました。そして、ERPに蓄積されるさまざまなデータを活用し、企業の成長につなげるためには、BIツールとの連携が有効です。 …
詳しくみるITAC(IT業務処理統制)とは?内部統制との関係や効果を解説
「内部統制」は、企業が適切かつ透明性の高い経営を行うために必要な仕組みやプロセスです。ITACは、この内部統制を推進するために重要な要素といえます。ITACに取り組めば、業務効率化…
詳しくみるIT-BCPとは|IT領域に特化したBCP対策の手順・ポイントを解説
自然災害やサイバー攻撃など、企業の活動を止めるリスクは年々増加しています。とくに近年では、ITシステムが業務の基盤となっている企業も多いため、機能が停止すると、直ちに売上や信頼低下…
詳しくみる