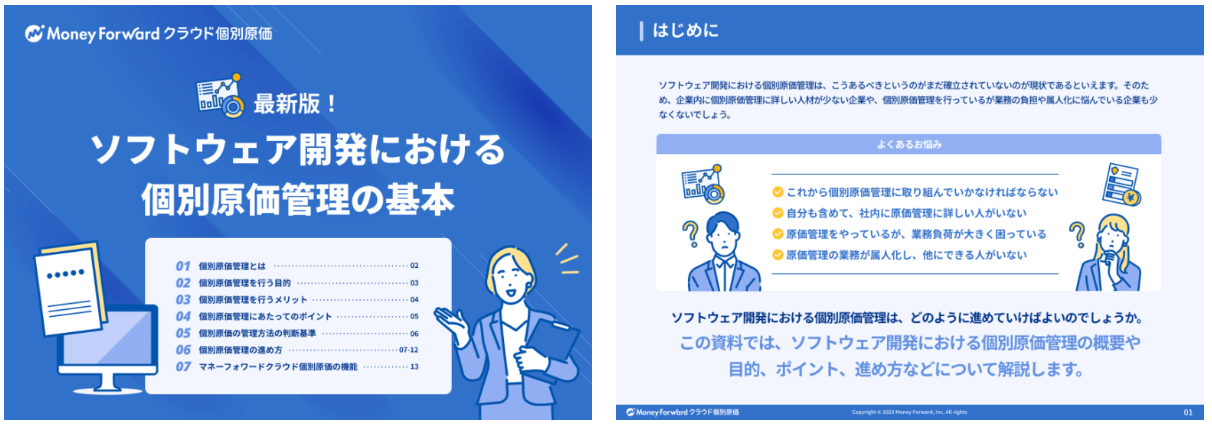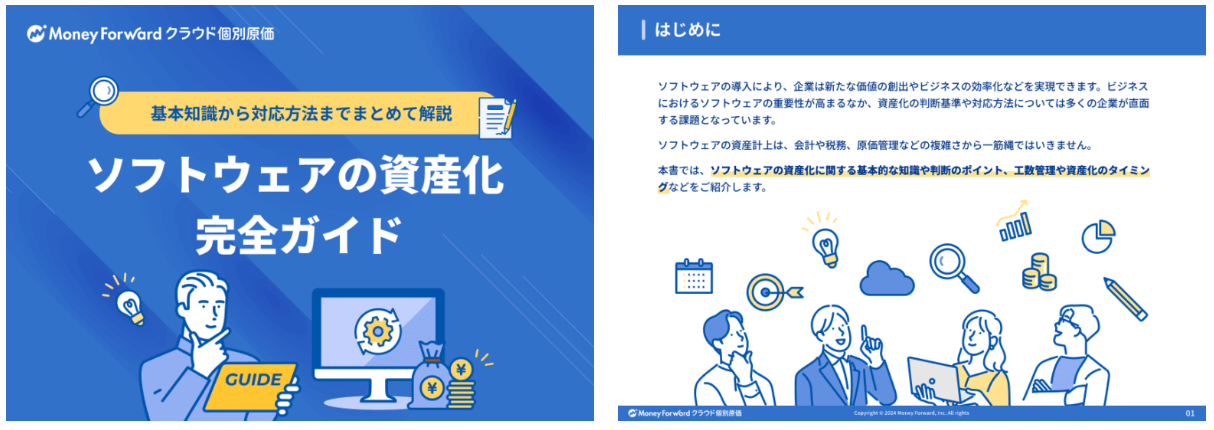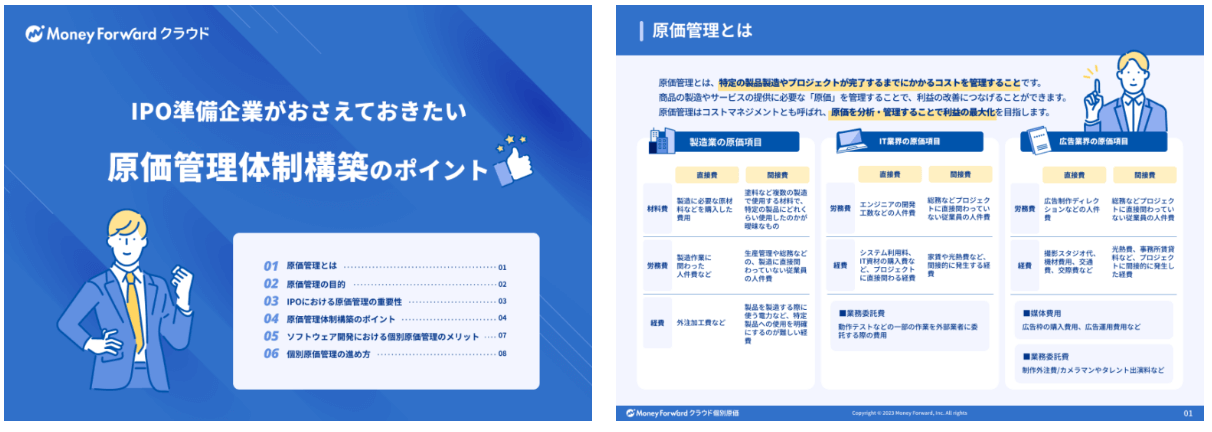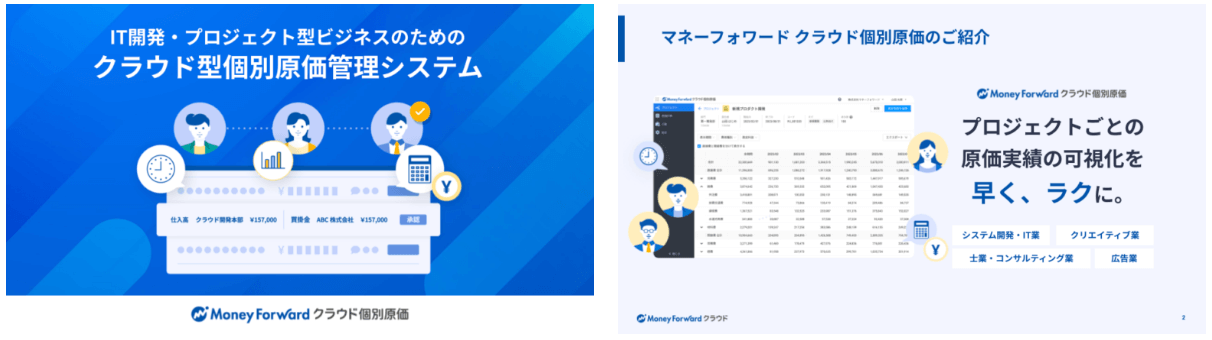- 作成日 : 2025年8月19日
デザイナーの工数管理とは?工数計算から見積書の作成、ズレを防ぐ対策を解説
デザイナーの工数管理は、プロジェクトの成功と会社の利益を左右します。デザイン業務にかかる時間を正確に把握し、管理することは、納期遅延やコスト超過を防ぎ、適正な対価を得るために欠かせません。この記事では、デザイナーの工数管理の基本から具体的な進め方、役立つツール、そしてそのデータをどう経営に活かすかまで、わかりやすく解説します。
※本記事は、「デザイナー」と検索された方を想定していますが、「webデザイナー」に該当する内容を含みます。
目次
デザイナーの工数管理とは?
デザイナーの工数管理とは、デザイン業務にかかる作業時間を正確に記録し、分析することです。プロジェクトやタスクごとにどれだけの時間や人員が費やされたかを把握し、それを計画、実行、評価に役立てます。
工数管理がなぜ必要なのか
デザイン業務の工数を管理することは、プロジェクトを計画通りに進行させ、ビジネスとして収益を上げるために役立ちます。デザイン業務はクリエイティブな性質上、時間の見積もりが難しい面があります。しかし、工数を管理しないと、見積もりと実際の作業時間に大きなズレが生じ、結果として納期遅延や採算悪化を引き起こします。工数管理を行うことで、かかる時間を「見える化」し、適切な計画とリソース配分ができるようになります。
デザイナーの工数管理でわかること
工数管理によって、具体的な作業時間や人員配分に関するデータが得られます。
例えば、特定のデザインタスク(ロゴ作成、Webサイトのトップページデザインなど)にどれくらいの時間がかかるのか、個々のデザイナーがどんな種類の作業に、どれくらいの時間を費やしているのかがわかります。
このデータがあれば、プロジェクト全体の所要時間やコストをより正確に見積もる根拠が生まれます。さらに、チームや個人の得意なタスクや、時間がかかっているボトルネックになっている作業も見えてきます。
今後のプロジェクト計画や、チーム全体の生産性向上策を考える上で重要な判断材料になります。
デザイナー業務で発生する主な工数
Webデザインやグラフィック制作など、デザイナーが関わる業務にはさまざまな工程があります。ここでは、一般的な制作フローをベースに、具体的な作業とその目安時間を紹介します。見積もり精度の向上やスケジュール管理の参考にご活用ください。
1. クライアントとの打ち合わせ・要件確認
制作に着手する前に、クライアントの目的や課題を把握し、必要な情報をヒアリングします。初回ミーティングやチャットでの要件確認、参考資料の共有、競合調査の要望整理などが含まれます。この工程はプロジェクトの方向性を左右するため、丁寧な準備と確認が求められます。
- 見積もり目安:1〜5時間
2. サイト構成案・ワイヤーフレーム作成
ページ全体の構成や情報の流れを設計する工程です。画面ごとの役割を整理し、ワイヤーフレームやサイトマップを作成します。ユーザーの導線を意識しながら、クライアントに提案できる資料として仕上げる必要があります。
- 見積もり目安:3〜10時間
3. トップページのデザイン作成
最初に着手するメインビジュアル部分のデザインです。ブランドイメージや訴求ポイントを考慮しながら、配色やフォント、写真やイラストのバランスを設計します。複数案を提案することもあり、時間がかかる工程です。
- 見積もり目安:6〜12時間
4. 下層ページのデザイン作成
サービス紹介や会社概要、採用情報など、トップページ以外のページをデザインします。基本レイアウトは共通化されることが多いものの、内容に応じた調整やビジュアルの最適化が必要です。
- 見積もり目安:1ページあたり3〜6時間
5. バナー・アイコン・画像素材の制作
ページ内に使用する各種ビジュアル素材を個別に作成します。オリジナルバナー、ボタン画像、アイコン、説明図など、細かいパーツの調整に時間がかかることも多く、見積もり時に見落とされやすい作業です。
- 見積もり目安:1〜5時間
6. デザイン修正対応
クライアントからのフィードバックを受けて行う修正作業です。文言変更からレイアウトの再調整、コンセプトの再提案に至るまで、対応内容によって工数が大きく変動します。初期段階で修正回数を取り決めておくことが望ましいです。
- 見積もり目安:1回あたり1〜3時間
7. コーディング(HTML/CSS)
静的なHTML/CSSによる実装作業です。デザイン通りの表現になるよう調整しつつ、レスポンシブデザインやSEOへの配慮も求められます。デザイナーがコーディングも担当する場合には、見積もりにしっかり含める必要があります。
- 見積もり目安:1ページあたり1〜5時間
8. CMS(WordPressなど)への実装
WordPressをはじめとするCMS環境への組み込み作業です。カスタム投稿タイプやテンプレート設計、クライアントによる更新を前提とした編集画面の最適化などが含まれます。デザインだけでなく設計的な視点も必要です。
- 見積もり目安:一式で10〜20時間
9. テスト・表示確認・納品対応
各ブラウザやデバイスでの表示テスト、リンク切れや誤字脱字のチェックを行い、最終的な納品データを整えます。軽視されがちな工程ですが、最終品質を担保する重要な作業です。
- 見積もり目安:1〜3時間
10. 進捗報告・資料作成・社内対応
作業報告書の作成、進捗管理ツールへの入力、社内MTGへの参加など、直接的な制作ではないものの、プロジェクトを円滑に進めるために発生する業務です。これらも確実に工数として記録すべき対象です。
- 見積もり目安:1案件あたり2〜4時間
デザイナーの効果的な工数計算と見積もりのステップ
デザイナーの工数計算と見積もりは、プロジェクトの進行や利益に直結します。正確な見積もりができれば、無理のないスケジュール管理と適切なコスト設定が可能になり、納期遅延や赤字のリスクを抑えられます。
効果的に見積もるためには、タスクを細分化し、過去のデータを活用し、予備の時間を含めることが基本です。この3つのステップを丁寧に行うことで、現実的なプロジェクト計画が立てられます。
1. 作業を細かく分けて計算する
見積もりの第一歩は、プロジェクト全体を細かい作業単位に分けることです。たとえばWebサイト制作なら、「企画・構成」「ワイヤーフレーム作成」「デザインカンプ作成」「素材作成」「コーディング」「テスト・修正」などの大項目に分類します。
さらに、それぞれを具体的な成果物ごとに細分化します。例えば「デザインカンプ作成」なら、「トップページデザイン」「お知らせページデザイン」といった形です。
作業を具体的に分けることで、それぞれにかかる時間が見積もりやすくなり、誰がどの作業を担当するかの整理にもつながります。
2. 過去の工数データを見積もりに活かす
過去に行った類似プロジェクトの工数データは、新しい見積もりの精度を高める材料になります。例えば、以前のLP制作で「トップページデザイン」に平均で6時間かかったと記録があれば、同様の案件の見積もりにそのデータを参考にできます。
精度の高い見積もりを行うには、日頃からタスクごとの作業時間を記録し、データとして蓄積しておくことが重要です。さらに、プロジェクトの種類や規模、関与した人数などの条件別に分類しておけば、より適切なデータとして参照しやすくなります。
3. バッファを含めて見積もる
見積もりは予測に過ぎず、実際の現場ではさまざまなイレギュラーが発生します。こうした事態に備えるためには、見積もりに「バッファ(予備時間)」を必ず含めます。バッファの量はプロジェクトの性質や関係者の特性、チームの経験値などを踏まえて決めます。
例えば「見積もり時間の5%をバッファとして加算する」といったルールを事前に設定しておけば、予期せぬ追加作業が発生しても納期や品質に影響を出さずに対応できます。バッファはトラブル対応のためだけではなく、全体の安定運用のための余白です。
デザイナーの工数計算から見積書を作成
デザイン業務の見積書は、感覚や一律の料金で作るものではありません。プロジェクトに必要な作業を洗い出し、「かかる時間=工数」を根拠に計算します。見積書の一例を紹介しながら、作成の際に気を付けたいポイントを解説します。
| No. | 作業項目 | 数量・単位 | 単価(円) | 金額(円) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 企画構成(要件定義含む) | 一式 | 30,000 | 30,000 |
| 2 | ワイヤーフレーム作成(画面設計) | 10ページ | 2,500 | 25,000 |
| 3 | トップページデザイン | 1ページ | 20,000 | 20,000 |
| 4 | 下層ページデザイン | 5ページ | 8,000 | 40,000 |
| 5 | バナー・画像素材制作(装飾画像含む) | 一式 | 30,000 | 30,000 |
| 6 | デザイン修正対応(2回まで) | 一式 | 10,000 | 10,000 |
| 7 | HTML/CSSコーディング(静的ページ) | 10ページ | 2,000 | 20,000 |
| 8 | WordPress組み込み(テーマ構築含む) | 一式 | 40,000 | 40,000 |
| 9 | テスト・検証・納品準備 | 一式 | 10,000 | 10,000 |
| 小計 | 225,000 | |||
| 進行管理費(5%) | 11,250 | |||
| 合計(税抜) | 236,250 | |||
| 消費税(10%) | 23,625 | |||
| 総合計(税込) | 259,875 |
工数計算・見積書作成のポイント
1. 「一式」の使いすぎに注意
一式表記は便利ですが、すべてを一式にするとクライアントが内容を把握しにくくなり、交渉材料にもなりません。時間が読める作業は「ページ数」や「時間」で分解し、説明可能な形にしましょう。
2. 工数の根拠を明確にする
「なぜこの金額なのか」が説明できるように、過去実績や所要時間ベースでの積算を習慣化すると、見積もりに説得力が出ます。感覚で価格をつけると後々自分が困ることもあります。
3. 進行管理費(バッファ)を忘れずに
想定外の修正・待機時間・確認作業は必ず発生します。全体の5〜10%程度のバッファをあらかじめ見積もりに含めておくと、赤字や過重労働を防げます。
4. 納品後の対応を含めるか明記する
「納品して終わり」ではなく、公開対応、軽微な更新、簡易レクチャーなどが発生する場合があります。あらかじめ含めるか、別料金とするかをはっきりさせておきましょう。
5. 単価を調整して信頼性と現実性を両立
コーディングなどは単価を抑えて見せつつ、全体の設計や制作工程で適正な利益を取る形にすることで、価格面と実務負荷のバランスが取りやすくなります。
6. 見積書は「説明のためのツール」として使う
クライアントは専門外です。項目は簡潔に、でも内容は丁寧に説明できるように準備すると信頼感が上がります。「何に、どれだけ、なぜかかるのか」を可視化できると、承認もスムーズです。
デザイナーの工数管理でよくある課題と対策
デザイナーの工数管理では、実際に運用する中で見積もりとのズレや記録漏れ、突発的な依頼への対応といった課題が生じやすくなります。こうした課題をクリアすることが、より正確な工数管理につながります。
見積もりとのズレ
見積もりと実際の作業時間にズレが生じる原因は、タスクを十分に細分化できていないことや、過去データが不足していること、さらにプロジェクト途中で仕様変更が発生することなどが挙げられます。
このズレを減らすには、まずプロジェクト開始前にタスクを細かく洗い出し、それぞれにかかる時間を具体的に見積もる練習を積みます。仕様変更が発生した場合は、追加工数を再見積もりし、クライアントと合意を取る手順を明確にしておくことで、時間の過不足を防げます。
作業時間の記録漏れ
作業時間の記録は、忙しい業務の中でつい後回しになりがちです。記録の目的が曖昧だったり、方法が複雑だったりすると、記録漏れが続きやすくなります。
この問題には、記録の目的(見積もり精度の向上、振り返り、チーム内の負荷把握など)を全員で共有し、「なぜ記録が必要か」を理解してもらうことで対処しましょう。記録方法はできるだけ簡単にし、リアルタイムで記録できるツールを活用するのが効果的です。終業前に記録の時間を確保する、チームで記録状況を共有するなど、仕組み化することで定着しやすくなります。
突発的なタスクへの対応
デザイン業務では、予定にない修正依頼や急ぎの対応が入ることがあります。こうしたタスクは軽視されやすく、工数の記録が漏れがちです。
突発的な作業も、他のタスクと同様に記録の対象です。内容と時間を必ず記録し、全体の負荷を見える化します。事前に対応フローを決めておくとスムーズです。例えば「1時間以内の対応は口頭報告、それ以上は簡易見積もりとスケジュール調整を行う」といったルールを設けることで、既存プロジェクトへの影響を最小限にしつつ、突発工数の管理も行いやすくなります。
デザイナーの作業時間を正確に記録する方法やツール
作業時間を正確に記録するためには、自分たちに合った記録方法を選び、無理なく継続できる仕組みを作ることがポイントです。どの方法を選ぶかは、チームの規模、予算、求める機能、すでに使っているツール環境によって変わります。
手書きやスプレッドシート
ノートやExcel、Googleスプレッドシートなどを使って手入力する方法です。
メリットは、ツールを新たに導入する必要がなく、すぐに始められる点です。コストもかかりません。
デメリットは、記録や集計に手間がかかること、リアルタイムでの入力が難しく、忘れやすいことです。また、チーム全体で共有するにはやや不便です。
タイムトラッキングツール(専用の時間記録ツール)
作業開始・終了をワンクリックで記録できるツールで、作業時間を自動的に記録・集計してくれます。「タイムデザイナー」などがこれに該当します。
メリットは、タスクごとの作業時間を簡単に記録でき、分析やレポート作成にも対応しやすい点です。
デメリットは、ツールの利用料がかかる場合があることと、導入や操作に慣れるまで時間がかかることです。
プロジェクト管理ツールの付随機能
Asana、Trello、Backlogなど、プロジェクト管理ツールに備わっている時間記録機能を活用する方法です。
メリットは、タスク管理と時間記録を一元化できる点で、進捗管理と並行して時間の把握がしやすくなります。
デメリットは、時間記録機能が限定的な場合もあることと、プロジェクト管理ツールそのものの習熟が必要な点です。
この記事をお読みの方におすすめのガイド4選
最後に、この記事をお読みの方によく活用いただいている人気の資料・ガイドを紹介します。すべて無料ですので、ぜひお気軽にご活用ください。
最新版!ソフトウェア開発における個別原価管理の基本
ソフトウェア開発における個別原価管理にお悩みではありませんか?
ソフトウェア開発における個別原価管理の基本から、その目的やメリット、具体的な進め方までを詳しく解説します。
ソフトウェアの資産化完全ガイド
ソフトウェアの資産計上は、会計や税務、原価管理などの複雑さから難易度が高く、うまく進められていない企業も多いのではないでしょうか?
ソフトウェアの資産化に関する基本的な知識や判断のポイント、工数管理や資産化のタイミングなどを解説します。
IPO準備企業におすすめ!原価管理体制構築のポイント
個別原価管理は、IPOに必要とされるあらゆる経営管理体制の構築・運用と密接に関連しており、非常に重要です。
これから原価管理をはじめる企業向けに、体制構築のポイントや進め方を解説します。
マネーフォワード クラウド個別原価 サービス資料
IT開発・プロジェクト型ビジネスのための個別原価管理システムをお探しではありませんか?
マネーフォワード クラウド個別原価は、個別原価計算はもちろん、プロジェクト申請・工数入力・資産振替・レポート作成までの一連の業務をワンストップでサポートします。
※ 掲載している情報は記事更新時点のものです。
※本サイトは、法律的またはその他のアドバイスの提供を目的としたものではありません。当社は本サイトの記載内容(テンプレートを含む)の正確性、妥当性の確保に努めておりますが、ご利用にあたっては、個別の事情を適宜専門家にご相談いただくなど、ご自身の判断でご利用ください。
関連記事
BCP対策とは?目的や策定の流れをわかりやすく解説
企業や施設が自然災害や感染症、サイバー攻撃などの非常時にも事業を継続させるには、事前にBCPの策定が必要です。 とくに日本は地震や台風などの自然災害が頻発するため、業種や規模に関わ…
詳しくみる業務標準化とは?メリットやデメリット、進め方について詳しく解説
昨今の働き方改革によって勤務時間の短縮や生産性向上が求められている中、業務標準化に取り組む企業が増えています。業務標準化に取り組めば、企業全体の生産性向上や業務の効率化など、多くの…
詳しくみるプロジェクト別原価計算とは?目的や重要性、実施プロセスなどを解説
プロジェクト別原価計算とは、労務費や外注費、経費などの原価をプロジェクト単位で計算する作業のことです。 主にソフトウェア開発業やコンサルタントといったプロジェクト単位で仕事を行う業…
詳しくみるBCP対策に活用できる補助金とは?支給額や申請手順を解説
近年、企業の間でBCP(事業継続計画)を策定・強化する動きが広がっています。しかし、BCPを推進するには、設備の導入や体制の構築などに多額の費用がかかるため、中小企業にとっては大き…
詳しくみるBPOとは?メリット、デメリット、アウトソーシングとの違いも踏まえて解説
業務効率化やコスト削減のためにBPOの導入を検討している方の中には、「そもそもBPOって何?」「アウトソーシングと何が違うの?」「自社に適しているのはどっち?」といった疑問や不安を…
詳しくみる物流のBCP対策とは?メリット・要素・実践ポイントをわかりやすく解説
物流の現場では、災害や事故などによって輸送・配送がストップした場合、企業活動全体に大きな影響がおよびます。近年は自然災害の頻発に加えて、感染症やサイバー攻撃などのリスクも増えており…
詳しくみる