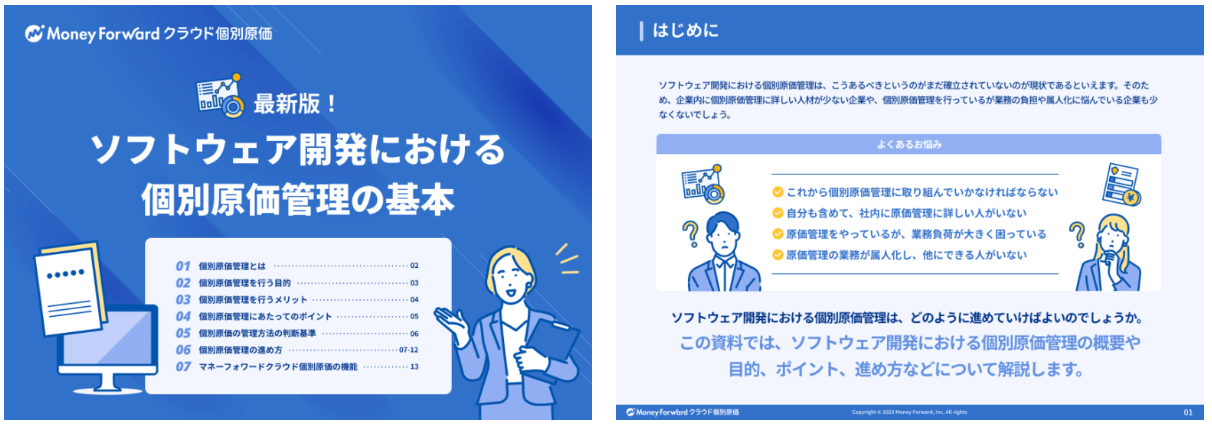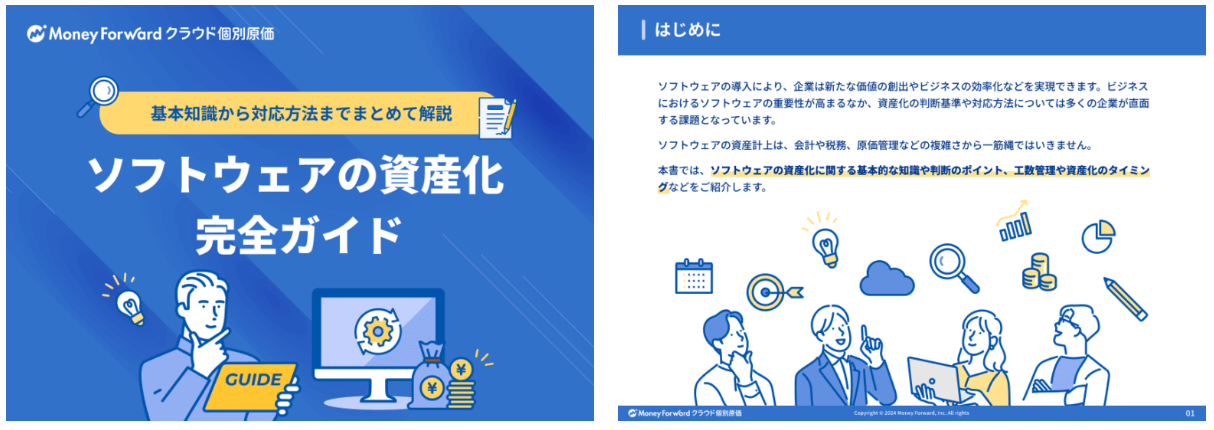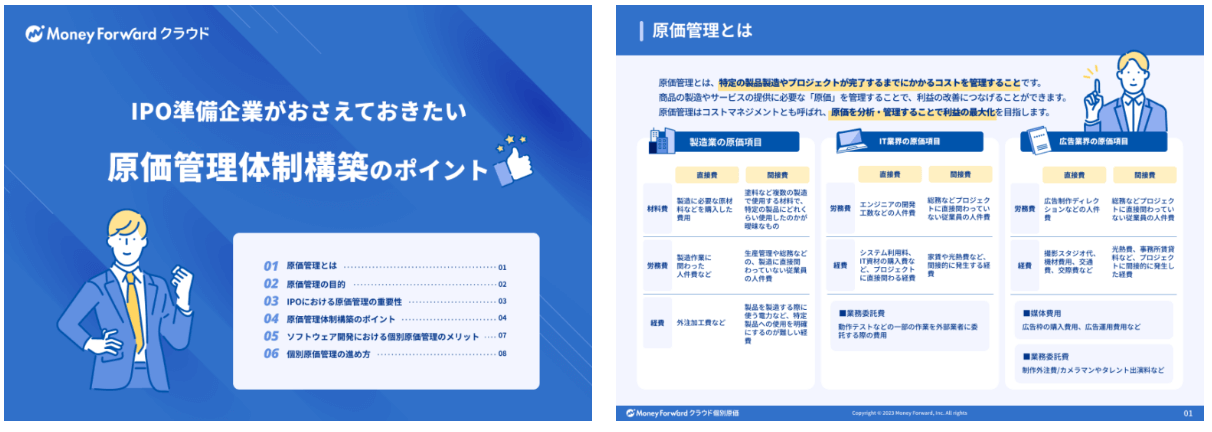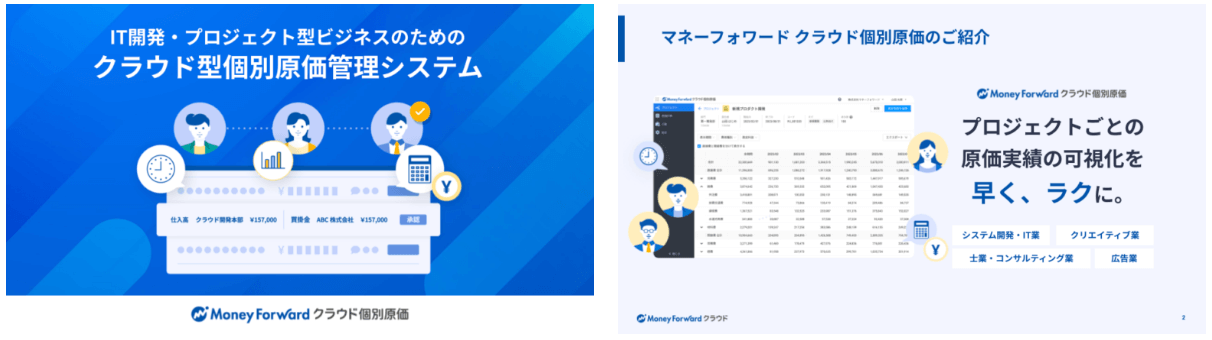- 作成日 : 2025年8月19日
開発工数の見積もり精度を高める7つの確認項目!工数の削減・効率化の方法も解説
システム開発における開発工数の管理は、プロジェクトの成功に直結します。工数の見積もりが不正確だと、納期遅延やコスト超過の原因になります。一方で、見積もりの精度を高め、効率的に管理することで、業務全体の無駄を減らし、コスト削減にもつながります。本記事では、開発工数の基本から見積もりの確認項目、削減方法までを具体例を交えてわかりやすく解説します。
開発工数とは
開発工数とは、システム開発プロジェクトを完了するために必要な作業量を示す指標であり、「人数×時間」という計算式で算出されます。この作業量には、プログラミングに限らず、要件定義から設計、テスト、リリース、保守運用までの全工程が含まれます。
工数の単位には「人日」と「人月」があり、前者は1人が1日8時間働く作業量、後者は1人が月20日間働く量を指します。例えば、5人の開発者が10日間作業する場合、工数は「5人×10日=50人日」となります。
プロジェクトを円滑に進め、予算内に収めるには、開発工数の精度が求められます。定義が明確であることで関係者間の意思疎通がスムーズになり、見積もり精度向上にもつながります。
精度の高い開発工数を見積もる方法
精度の高い開発工数の見積もりには、プロジェクトの特性に応じて手法を選ぶことが必要です。代表的な方法を紹介します。
類推法(アナロジー法):過去のプロジェクトと比較して見積もる
過去に実施した類似プロジェクトの工数実績を元に、今回の開発工数を予測する方法です。
特に、工程や作業内容、参加メンバーのレベルなどが過去の事例と類似している場合には、精度の高い見積もりが期待できます。
【具体例】
以前開発した飲食店予約システム(100画面)の工数が120人月だったとします。今回の案件が機能構成や要件等の点で類似し、200画面の場合、「120人月×2」でおよそ240人月を初期見積もりとして算出します。
- 類似システムの実績がある
- 同じ開発チームが対応する
注意点として、過去のプロジェクトとの違い(スキル、技術、要件変更)を適切に調整する必要があります。
しかし、過去の工数データを正確に把握していない場合や、見積もり担当者の経験値に左右される部分が大きくなる点もデメリットとして挙げられます 。
係数法(パラメトリック法):定量的データで工数を計算
プロジェクトの規模や仕様に基づいて、過去のデータから導き出した「係数」を使い、工数を見積もります。代表的な係数モデルとしては、ソースコードの行数から工数を見積もるCOCOMO (Constructive Cost Model) や、システムの機能を外部からの視点で定量的に評価し、工数を見積もるファンクションポイント法(FP法) などがあります。この手法のメリットは、誰が見積もっても同じ結果になりやすく、客観的な見積もりができる点です 。
【具体例】
Webアプリの開発で、1画面あたりの平均工数が「1.5人日」だった場合、新規に開発する画面が80ページであれば、「80 × 1.5 = 120人日」と算出します。
- データが豊富な企業
- 定型業務が多い開発案件
注意点として、係数の根拠が明確でないと、クライアントへの説明が難しくなることがあります。
ボトムアップ法(積み上げ法):全作業を細分化して合算
プロジェクトに必要な作業をすべて洗い出し、個々の工数を積み上げて全体を算出する手法です。
各機能を精査し工数を見積もるため、タスクの抜け漏れを防ぎやすく、精度の高い見積もりが期待できます 。作業開始後には、タスクごとに進捗状況を把握しやすくなり、遅延が発生した場合でも、どのタスクに問題があるのかを特定し、ピンポイントで対策を講じることができます 。しかし、見積もり作成に時間がかかるというデメリットがあります 。
- 小規模チーム
- 要件が明確になっているプロジェクト
注意点として、タスクの抜け漏れに注意。要件が未確定だと正確な積み上げが困難です。
3点見積もり法:不確実性を加味して工数を出す
各タスクについて、最も楽観的なケース(楽観値)、最も現実的なケース(最頻値)、最も悲観的なケース(悲観値)の3つの工数の見積もりを行い、平均を求める方法です。
計算式として、「(悲観値 + 4 × 最頻値 + 楽観値) ÷ 6」が用いられます 。
この手法のメリットは、不確実性を考慮に入れることができるため、より現実的な見積もりが可能になる点です 。
【具体例】
ある機能Aの工数について、下記のように見積もります。
- 楽観的(最低)見積もり:10人日
- 現実的(最頻)見積もり:15人日
- 悲観的(最大)見積もり:25人日
→ 「(10+4×15+25)÷6 = 15.8人日」として採用します。
- 新規性のあるプロジェクト
- 複数の担当者の意見を統合したい場合
注意点として、担当者の主観が強く出ると、見積もりの信頼性に影響します。
標準タスク法:WBSを使って定型タスクで積み上げる
WBS(Work Breakdown Structure:作業分解構造図)に基づき、標準化された工数単位で積み上げる手法です。
各作業を細分化して一覧表に起こした計画書に基づいて見積もりを算出するため、精度が高い見積もりを作成できるというメリットがあります 。しかし、各作業の工数を見積もる際に時間がかかるというデメリットがあります 。
【具体例】
過去のデータから平均的に「1機能あたり0.8人日」と定めている場合、新機能が40個あると「0.8 × 40 = 32人日」で見積もります。
- 業務の標準化が進んでいる会社
- 精度の高いWBSテンプレートがある場合
注意点として、標準工数が古いと、実態とのズレが生じやすくなります。
プライスツーウィン法:予算に収まるよう逆算して設計
クライアントの予算上限から逆算し、開発可能な機能と工数を割り出す方法です。予算超過を防げるというメリットがありますが 、予算ありきでの見積もりとなるため、開発工数に制限がかかり、必要な機能が不足したり、システムの品質が保証できないといったリスクがあります 。
【具体例】
予算が600万円、人月単価が100万円なら最大6人月(=120人日)までしか使えません。この枠内で「優先機能」に絞って開発を行います。
- 予算が厳格に定まっている案件
- MVP開発や短期プロトタイプ
注意点として、機能削減の判断が必要。成果物の品質や完成度に影響が出るリスクがあります。
見積もりの精度を高める7つの確認項目
見積もられた開発工数の妥当性を判断するには、複数の視点から見積もりの中身を確認する必要があります。以下のポイントを押さえることで、過不足のない、現実的な工数見積もりを見極めることができます。
1. エンジニアのスキルが要件に合っているか
見積もりに記載されているエンジニアが、プロジェクトに求められるスキルを持っているかを確認します。熟練したエンジニアは単価が高い傾向にありますが、効率の良い作業と高い品質の成果物が期待できます。逆に、スキルが不足していると開発が遅れたり、手戻りが発生するリスクがあります。
2. 各工程の作業範囲に過不足ないか
見積もりに含まれる作業範囲が、要件定義、設計、開発、テスト、導入、保守運用までの全工程を網羅しているかを確認します。例えば、「要件定義に10人日」「基本設計に15人日」「開発に80人日」「テストに25人日」など、各工程の内訳が明確になっていれば、工程ごとの工数配分が妥当かどうかを判断できます。
3. 工数の前提条件が記載されているか
見積もりがどのような前提で作成されているかは非常に重要です。使用する技術、開発環境、対象プラットフォーム、開発期間などの前提が曖昧な場合、開発途中での想定外のコスト増につながる可能性があります。たとえば「AWS利用前提」や「Windows環境上での開発」など、具体的な記述があるかを確認します。
4. 開発費用以外のコストが記載されているか
ライセンス費用、保守費、運用費、プロジェクト管理費、外注費用など、ソフトウェア開発に付随するコストが見積もりに含まれているかを確認します。これらが抜けていると、後から追加請求され、総予算を大きく超過するリスクがあります。
5. 工数配分に偏りがないか
プロジェクト内の各フェーズに対して、工数が過不足なく割り当てられているかを見ます。例えば、開発に多くの工数が割かれているのに、テスト工程が極端に少ないと、後からバグ修正の工数が膨らむリスクがあります。類似プロジェクトと比較して、バランスが取れているかを検討しましょう。
6. リスクを想定しているか
予期せぬ技術的課題や仕様変更などに対応するために、バッファ(予備)の工数が見積もりに含まれているかを確認します。リスクのある工程に対しては、10〜15%程度のバッファが設定されているのが一般的です。これがないと、問題発生時に開発が大幅に遅れる可能性があります。
7. 他の見積もりと比べて相場とずれていないか
複数の業者から見積もりを取得し、内容を比較することで相場を把握できます。極端に安い見積もりには、重要な工程が抜けていたり、品質が犠牲になっていたりするリスクがあります。逆に高すぎる場合は、不必要な作業や過剰な人員配置が含まれている可能性があります。
開発工数を効率化・削減するには
開発工数を減らすには、単純に作業時間を短縮するのではなく、業務プロセスそのものを見直し、仕組みで効率化することが求められます。ここでは、開発工数を効率的に削減するために実行すべき戦略を紹介します。
業務プロセスの可視化とボトルネックの改善
まず取り組むべきは、現在の業務フローを明確に把握することです。開発に関わる一連のタスクを洗い出し、それぞれにどれだけ時間がかかっているのかを定量的に記録します。これにより、無駄な承認プロセスや重複する作業など、非効率の原因を特定できます。改善例として、Excelベースで行っていた進捗管理をプロジェクト管理ツールに置き換えたことで、会議の回数が減り、報告にかかる時間を大きく削減した事例もあります。
繰り返し作業や定型業務の自動化
定型的な作業はRPA(Robotic Process Automation)やスクリプト、自動化ツールの導入によって効率化できます。例えば、開発後の単体テストや日報作成など、繰り返し発生する作業は自動化が容易です。人の手で毎回行っていた場合と比べて、1タスクあたり30分の短縮でも、週に数十回繰り返されると大きな削減効果をもたらします。自動テストの導入により、品質向上と同時にテスト工数を半減した企業も少なくありません。
アジャイル開発やDevOpsによる開発サイクルの短縮
従来のウォーターフォール型開発では、各工程の完了を待って次のフェーズへ進むため、手戻りが大きくなりがちです。アジャイル開発は、短い開発サイクル(スプリント)で設計・実装・テストを反復し、途中での仕様変更にも柔軟に対応できます。さらに、開発と運用の連携を強化するDevOpsを取り入れると、自動デプロイやCI/CD(継続的インテグレーションとデリバリー)により、手作業を減らし、リリース頻度の向上と同時に作業時間の圧縮が可能になります。
再利用可能な資産の活用と標準化の推進
業務アプリケーションの構築では、すでにあるコードやライブラリ、テンプレートの再利用が大きな効果をもたらします。同じ機能を毎回ゼロから作るのではなく、再利用可能な部品(モジュール、フレームワーク)として整備しておくことで、設計・実装・テストの時間を削減できます。また、業務フローや入力フォームなどもテンプレート化し、作業の属人性をなくすことで、生産性と品質の安定化が図れます。
ITツールの導入とアウトソーシングの活用
勤怠管理、経費精算、給与処理、日報提出などのバックオフィス業務にITシステムを導入することで、間接的に開発にかかる負担を軽減できます。例えば、クラウド型の勤怠管理システムを導入すれば、月末の集計作業を数時間から数分に短縮できます。また、専門性が低い作業やルーチン業務を外部のパートナーに委託することで、社内エンジニアの開発リソースを戦略的な領域に集中させることができます。
開発工数の管理を正しく行うことで業務効率化とコスト削減を両立できる
システム開発において、工数の管理は単なる作業量の把握ではなく、ビジネス全体の効率とコストに直結する重要な施策です。正確な見積もりと工程ごとの可視化により、不要な作業や手戻りを抑え、プロジェクト全体の流れをスムーズにします。また、自動化や開発手法の最適化を取り入れることで、人的リソースの無駄を減らし、品質を保ちながら工数を削減することが可能です。開発工数の管理を徹底することは、業務効率とコストの両面で成果を出すための現実的かつ効果的な手段です。
この記事をお読みの方におすすめのガイド4選
最後に、この記事をお読みの方によく活用いただいている人気の資料・ガイドを紹介します。すべて無料ですので、ぜひお気軽にご活用ください。
最新版!ソフトウェア開発における個別原価管理の基本
ソフトウェア開発における個別原価管理にお悩みではありませんか?
ソフトウェア開発における個別原価管理の基本から、その目的やメリット、具体的な進め方までを詳しく解説します。
ソフトウェアの資産化完全ガイド
ソフトウェアの資産計上は、会計や税務、原価管理などの複雑さから難易度が高く、うまく進められていない企業も多いのではないでしょうか?
ソフトウェアの資産化に関する基本的な知識や判断のポイント、工数管理や資産化のタイミングなどを解説します。
IPO準備企業におすすめ!原価管理体制構築のポイント
個別原価管理は、IPOに必要とされるあらゆる経営管理体制の構築・運用と密接に関連しており、非常に重要です。
これから原価管理をはじめる企業向けに、体制構築のポイントや進め方を解説します。
マネーフォワード クラウド個別原価 サービス資料
IT開発・プロジェクト型ビジネスのための個別原価管理システムをお探しではありませんか?
マネーフォワード クラウド個別原価は、個別原価計算はもちろん、プロジェクト申請・工数入力・資産振替・レポート作成までの一連の業務をワンストップでサポートします。
※ 掲載している情報は記事更新時点のものです。
※本サイトは、法律的またはその他のアドバイスの提供を目的としたものではありません。当社は本サイトの記載内容(テンプレートを含む)の正確性、妥当性の確保に努めておりますが、ご利用にあたっては、個別の事情を適宜専門家にご相談いただくなど、ご自身の判断でご利用ください。
関連記事
原価と人件費とは?原価と人件費の関係を詳しく解説
企業の粗利や業績を正確に把握するためには、「原価」や「人件費」がどれだけかかっているのかを把握する必要があります。 原価と人件費の正しい意味や計算式を理解することで、原価管理をスム…
詳しくみる介護施設のBCP対策とは?具体的な策定方法やテンプレート活用法を解説
2024年度から、介護施設に「BCP(事業継続計画)」対策が義務化され、多くの事業者が対応を迫られています。しかし、「何から始めればいいのかわからない」「テンプレートだけでは不安」…
詳しくみる経理部門をIT化する方法!IT化のメリットや具体的なステップを解説
経理部門のIT化とは、ITツールを導入してして経理業務をシステム化したり、それによって効率化することを指します。 コスト削減や正確なデータ管理・分析、ヒューマンエラーの防止が可能と…
詳しくみるIT-BCPとは|IT領域に特化したBCP対策の手順・ポイントを解説
自然災害やサイバー攻撃など、企業の活動を止めるリスクは年々増加しています。とくに近年では、ITシステムが業務の基盤となっている企業も多いため、機能が停止すると、直ちに売上や信頼低下…
詳しくみる収支管理とは?概要やメリット、進め方、効果的な管理のポイントを解説
収支管理とは、プロジェクトや部署の収入および支出を管理する活動のことです。 収支管理の主な目的はプロジェクトや部署の利益を適切に維持・管理することであり、そのために売上や予算、原価…
詳しくみる工数の見積もりとは?手法や計算方法、見積書の書き方を解説
プロジェクトの計画や進行管理では「工数」の把握が欠かせません。人時や人日、人月といった単位が登場しますが、それぞれの違いを正確に理解しておかないと、見積もりやスケジュールに誤差が生…
詳しくみる