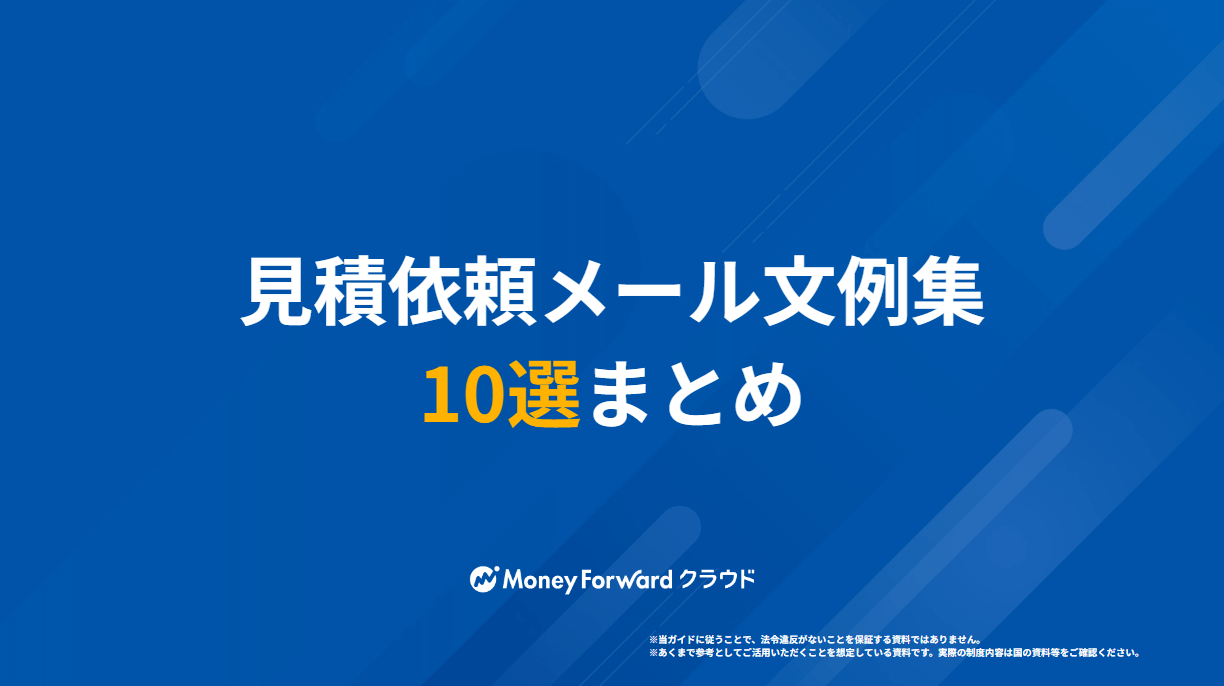- 更新日 : 2025年11月5日
見積依頼メール、返信メールの書き方は?例文や注意点を解説
最近は商品やサービスの価格、納期、取引条件などを確認するために見積もりをメールで送る方法が増えています。この記事では、見積依頼メールの基本から、具体的な書き方、例文、返信メールや見積書の送り方まで、一連の流れをわかりやすく解説します。
目次
見積依頼メールとは
見積依頼メールとは、取引先に商品やサービスの価格や内容を問い合わせるメールのことです。特に建設業界では、工事の規模や内容によって価格が大きく変わるため、事前に見積もりを取ることが重要です。見積依頼メールを送ることで、予算内に収まるかどうかを確認したり、複数の業者から見積もりを取って比較検討したりすることができます。
見積依頼メールは、以下のような場合に使用されます。
- 新規の取引先に対して: 新たにビジネスを始める際には、商品やサービス価格、納期、取引条件などを確認するために見積依頼メールを送ります。
- 既存の取引先に対して: 既存の取引先に対して新たな商品やサービスを依頼する際、または取引条件を再確認する際にも見積依頼メールを送ります。
見積依頼メールの書き方
見積依頼メールを書く際には、相手が必要な情報をすぐに理解できるように、明確でわかりやすい表現を心掛けましょう。
メールの件名はわかりやすく
件名には「見積依頼」や「〇〇プロジェクト見積り希望」「【見積依頼】〇〇工事について」など、簡潔でわかりやすいものにしましょう。件名が曖昧だと、見落とされたり後回しにされたりする可能性があります。
株式会社リンクアンドパートナーズが行った「企業のメールマーケティングに関する調査」によると、メール送信の際に重視するポイントとして、「件名の工夫」が57.0%で最も重視されるポイントであることを示しています。
参考:【企業のメールマーケティングに関する調査】メール送信の際に重視することは、「件名の工夫」が最多に。
希望の予算や取引条件は明確に
予算の上限があれば、あらかじめ伝えておくことをおすすめします。また、支払い方法や納期など、取引条件についても明確にしておきましょう。
例えば、「予算は〇〇万円以内で、納期は〇月〇日までにお願いしたいです」などと書くことで、スムーズに見積もりを作成してもらえます。
回答期限を設ける
複数の業者から見積もりを取る場合は、そのことを明示しておきましょう。「◯月◯日頃までにお見積りを頂けますと幸いです」など、今回は他社様にも相見積もりをお願いしていることを正直に伝えましょう。
隠していると、後々トラブルになる可能性があります。
相見積もりをとる場合はそのことを明示する
複数の業者から見積もりを取る場合は、そのことを明示しておきましょう。
隠していると、後々トラブルになる可能性があります。
「本件については他社にも見積もりを依頼しております」と明記することで透明性を保ちながら、業者に対して競争意識を促すことができます。これにより、より良い条件の見積もりを引き出すことが期待できます。
相手への礼節を忘れずに
見積もり依頼は、相手に仕事を依頼する立場です。
「〇〇していただけますと幸いです」「よろしくお願いいたします」など、丁寧な言葉遣いを心がけましょう。
また、メールの末尾には「このたびは貴重なご時間を割いて頂き、誠にありがとうございます。何卒よろしくお願い申し上げます。」など、相手に敬意を表す言葉を添えることが重要です。
見積依頼メールの例文・テンプレート
以下に、いくつかのケースに応じた見積依頼のメールの例文をご紹介します。
初めての取引先に送る場合
初めての取引先に見積依頼メールを送る際は、自社の簡単な説明や依頼の経緯などを添えると良いでしょう。
また、相手先の実績に言及するなど、信頼関係を築くための一言を添えるのもポイントです。
| 件名:【見積依頼】〇〇工事の見積もりについて 〇〇株式会社 突然のご連絡、失礼いたします。 弊社は、〇〇を専門とする会社です。 工事内容:〇〇 他社様にも相見積もりをお願いしておりますが、御社の実績を拝見し、ぜひお願いしたいと思っております。 どうぞよろしくお願いいたします。 株式会社〇〇 |
既存の取引先に送る場合
既存の取引先に見積依頼メールを送る場合は、これまでの取引に対する感謝の言葉を添えましょう。
また、できるだけ具体的な情報を記載することで、スムーズなやり取りにつなげることができます。
| 件名:【見積依頼】〇〇工事の見積もりについて 〇〇株式会社 いつもお世話になっております。 この度、〇〇工事の見積もりをお願いしたく、ご連絡いたしました。 工事内容:〇〇 ご多忙とは存じますが、〇月〇日までにご回答いただけますと幸いです。 いつもお世話になっており、ありがとうございます。 株式会社〇〇 |
急ぎで見積依頼したい場合
急ぎで見積もりが必要な場合は、件名と本文にその旨を明記しましょう。
ただし、あまりに無理な要求は控えるようにしてください。
| 件名:【至急・見積依頼】〇〇工事の見積もりについて 〇〇株式会社 大変急な依頼で恐縮ですが、〇〇工事の見積もりをお願いしたく、ご連絡いたしました。 工事内容:〇〇 誠に恐れ入りますが、〇月〇日までにご回答いただけますと幸いです。 株式会社〇〇 |
相見積もりをとる場合
複数の業者から相見積もりを取る場合は、メールにその旨を明記しましょう。
依頼する側にも選択肢があることを伝えることで、適正な価格設定を促すことができます。「今回は他社様にも相見積もりをお願いしている」など、正直に伝えましょう。
| 件名:【相見積依頼】〇〇工事の見積もりについて 〇〇株式会社 お世話になっております。 この度、〇〇工事の見積もりをお願いしたく、ご連絡いたしました。 以下の内容で見積もりをお願いできますでしょうか。 工事内容:〇〇 ご提示いただいたお見積りを元に、発注先を検討させていただきたいと思います。 どうぞよろしくお願いいたします。 株式会社〇〇 |
見積依頼メールは、シチュエーションによって書き方が異なります。上記の例文を参考に、自社の状況に合ったメールを作成してみてください。
見積依頼メールへの返信メール、見積書送付のポイント
見積依頼メールを受け取ったら、できるだけ早く返信しましょう。返信文は、丁寧な言葉遣いを心掛け、明確に伝えます。見積書は改ざんできない形式(PDF)で送付し、必要に応じてパスワードで保護します。
返信メールの件名の工夫
見積依頼メールへの返信の際は、依頼内容を明記した件名にしましょう。 「Re:【見積依頼】〇〇工事の見積もりについて」など、元のメールに関連づけるとよいでしょう。
見積書の送付形式の選択
PDF形式見積書はPDF形式で送付するのが一般的です。その理由は、PDFフォーマットが広く使用されているため、受取人が別途ソフトウェアをインストールする必要がなく、またPDF自体が改ざんが難しいためです。PDFファイルは、文書の整合性と信頼性を保持するために適しています。
見積書のセキュリティ強化
メールに見積書を添付して送る場合は、パスワードをかけて保護するとよいでしょう。パスワードは別途メールや電話で伝えましょう。セキュリティ対策として重要です。
見積依頼メールへの返信メールの例文・テンプレート
以下に、いくつかのケースに応じた返信メールの例文をご紹介します。
一次回答し見積もりを後送する場合
以下のテンプレートは、見積もり作成に時間が必要な場合の一次回答の例です。顧客への迅速な対応を示しつつ、詳細な見積もりを後ほど送付する旨を明記します。
| 件名:Re:【見積依頼】〇〇工事の見積もりについて 株式会社△△ お世話になっております。 〇〇工事のお見積りのご依頼を受領いたしました。 ご依頼いただきまして、ありがとうございます。 今後ともどうぞよろしくお願いいたします。 株式会社〇〇 |
返信と一緒に見積もりを送付する場合
見積依頼の内容を確認し、すぐに見積書を作成できる場合は、返信メールに見積書を添付しましょう。ただし、セキュリティ対策として、見積書にパスワードをかけ、そのパスワードは別途メールで送信するようにしてください。
| 件名:Re:【見積依頼】〇〇工事の見積もりについて 株式会社△△ お世話になっております。 〇〇工事の御見積りを作成いたしましたので、添付いたします。 見積金額:〇〇円(税込) ご不明な点やご要望などございましたら、お気軽にお問い合わせください。 株式会社〇〇 |
お断りする場合
何らかの理由で見積もりを提出できない場合は、丁寧にお断りするメールを送りましょう。
この際、代替案や他社の紹介などができると、よりよいでしょう。
| 件名:Re:【見積依頼】〇〇工事の見積もりについて 株式会社△△ お世話になっております。 〇〇工事のお見積りのご依頼をいただき、ありがとうございます。 お見積りのご提出ができず申し訳ございません。 また機会がございましたら、ぜひよろしくお願いいたします。 株式会社〇〇 |
見積依頼メールへの返信は、相手の立場に立って、丁寧かつ迅速に対応することを心がけましょう。例文を参考に、状況に合った返信メールを作成してみてください。
見積書の無料テンプレート(エクセル)
「マネーフォワード クラウド請求書」では、見積書のテンプレート(ひな形)をエクセル形式にて無料で提供しています。以下のリンクからダウンロードが可能です。
※ 掲載している情報は記事更新時点のものです。
バックオフィス業務の知識をさらに深めるなら
※本サイトは、法律的またはその他のアドバイスの提供を目的としたものではありません。当社は本サイトの記載内容(テンプレートを含む)の正確性、妥当性の確保に努めておりますが、ご利用にあたっては、個別の事情を適宜専門家にご相談いただくなど、ご自身の判断でご利用ください。
関連記事
受領書とは?書き方や注意点を解説【テンプレつき】
受領書とは、物品やサービスなどを受け取ったことを証明する書類です。 この記事では、受領書の概要から、ビジネス上はどのようなケースで受領書が必要になるか、適切に作成するための必要事項などを、テンプレートをもとに解説します。 受領書とは 受領書…
詳しくみる工事発注書とは?書き方や印紙、注意点を解説(無料テンプレート付き)
工事発注書とは、発注者が請負者に対して工事の内容、条件、金額などを明確に示す正式な文書です。本記事では、工事発注書の書き方や注意点、印紙の要否などについて解説します。さらに、実務で役立つテンプレートも提供しているので、すぐに活用いただけます…
詳しくみるピンハネとは?中間搾取の法的な定義や違法なケース、相談先まで解説
ピンハネとは、不当に高いマージンを取得することを指します。ビジネスにおいては、違法な「中間搾取」にあたるケースも存在します。 この記事ではピンハネの意味から法的な定義、建設業界における違法な中間搾取の例や対策などを解説していきます。違法な中…
詳しくみる【一人親方向け】人工代の請求書はどう作る?テンプレをもとに書き方を解説
この記事を読むことで、一人親方が人工代の請求書を正確かつ効率的に作成する方法を理解できます。具体的な記載項目や各項目の書き方、インボイス制度に基づく適格請求書の要件も詳しく解説しています。 また、請求書作成時に注意すべき点や効率化のためのツ…
詳しくみる一人親方がインボイス制度に対応する、対応しない場合の対策を解説
一人親方のインボイス制度への対応は、「課税事業者になるかどうか」を自分で判断することから始まります。登録して課税事業者になるべきか、それとも免税事業者のまま続けるか。制度の内容や取引先の方針、自身の事業規模によって、選ぶべき対応は変わります…
詳しくみる図面の拾い出しにおすすめ積算ソフト9選!無料・有料を紹介
図面の拾い出しとは、設計図から必要な材料や工事の内容を正確に拾い出し、コストを算出する作業のことを指します。特に建築業においては日常的に行われる業務です。しかし、この作業を手作業で行うと、時間がかかりミスも発生しやすくなります。ここで、積算…
詳しくみる