- 作成日 : 2025年9月9日
DCF法(ディスカウントキャッシュフロー方式)とは?計算式と計算方法をわかりやすく解説
DCF法とは企業価値評価の代表的な手法のひとつです。
しかし、実際にDCF法を用いるメリット・デメリットや、計算方法について詳しく知らない方も多いのではないでしょうか?
そこで、本記事では経営者や経理担当者向けにDCF法のメリットデメリットや、計算方法について解説します。
目次
DCF法(ディスカウントキャッシュフロー方式)とは?
DCF法とは、企業が将来にわたって生み出すと見込まれるキャッシュフローを現在の価値に割り引いて合計し、その結果を企業の価値とみなす評価方法です。
上場企業の場合、市場価格も企業の価値を反映するものですが、株価は株式市場の相場変動の影響を受けてしまいます。株式市場の相場に依存せず、事業の実態に基づいて価値を算定できる点がDCF法の大きな特徴です。
投資判断やM&Aの場面でも広く利用されており、理論的に最も整合性のある方法として知られています。
実際には、予測されたキャッシュフローを「割引率」という基準で調整し、現在の価値を求めます。
こうした仕組みによって未来の収益性を数値化でき、事業価値を客観的に把握することが可能です。
この記事をお読みの方におすすめのガイド4選
続いてこちらのセクションでは、この記事をお読みの方によく活用いただいている人気の資料・ガイドを簡単に紹介します。すべて無料ですので、ぜひお気軽にご活用ください。
※記事の内容は、この後のセクションでも続きますのでぜひ併せてご覧ください。
請求業務50倍でも1名で対応!売上増加を支える経理効率化の秘訣
債権管理・請求業務効率化が必要と言われも日常業務に追われていて、なかなか改善に向けて動けないというご担当の方もいらっしゃるのではないでしょうか。
本ガイドでは、請求業務の効率化が必要なのか・効率化することで本業に集中することで得られるメリットを詳しくご紹介しています。
経理担当者向け!Chat GPTの活用アイデア・プロンプトまとめ12選
債権管理担当者や経理担当者がChat GPTをどのように活用できるか、主なアイデアを12選まとめた人気のガイドです。
プロンプトと出力内容も掲載しており、コピペで簡単に試すことも可能です。お手元における保存版としてでだけでなく、従業員への印刷・配布用としてもぜひご活用ください。
経理担当者向け!Excel関数集 まとめブック
経理担当者の方をはじめ、ビジネスパーソンが知っておきたい便利なExcel関数集を初級~上級までギュッと網羅。
新人社員の研修用などにもお使いいただけます。Google スプレッドシートならではの関数もご紹介しています。
会計士監修!簿記の教科書
簿記のキホンについて最低限知っておきたい情報をギュッとまとめた保存版のガイドです。
仕訳例や勘定科目がついており、はじめての方でもイメージをつけながら読むことができるようになっています。
DCF法のメリット・デメリット
DCF法は、将来の収益を踏まえて企業価値を計算する理論的な方法で、具体的な金額を求められるメリットがあります。
一方で、予測の精度に大きく依存するため、不確実性が高い場合は評価結果が変動しやすいというデメリットもあります。
メリット
DCF法の最大のメリットは、将来のキャッシュフローを基準にするため、現時点での収益だけでなく将来性も考慮した企業価値を明確に算定できる点です。
さらに、事業戦略や投資計画を数値化して評価に反映できるため、将来の成長力を織り込んだ判断が可能となります。
実際にM&Aや新規投資の場面では、DCF法を用いることで交渉の根拠となる具体的な金額を提示でき、企業価値を公平に示す手段として役立ちます。
上記のような特徴により、投資家や経営者にとって意思決定を支える重要な評価方法といえるでしょう。
デメリット
メリットがある一方でDCF法にはデメリットもあります。
DCF法のデメリットは、将来のキャッシュフローを予測する必要があるため、経済環境や市場動向の変化によって見積もりが大きく変化してしまう点です。
さらに、割引率や永久成長率といった前提条件を少し変更するだけで、最終的な企業価値が大きくぶれる可能性があります。
新規事業や不安定な市場に属する企業では、予測が難しく評価の信頼性が下がる恐れもあります。
上記のデメリットを理解したうえで活用しなければ、誤った判断につながるので注意しましょう。
DCF法を計算するうえで重要な要素を解説
DCF法を正しく活用するためには、いくつかの前提条件を理解することが欠かせません。
とくに重要なのが、事業から得られるフリーキャッシュフロー、資本コストを反映した割引率、予測期間終了後の価値を表すターミナルバリュー、そして長期的な成長を想定する永久成長率の四つです。
上記の概念を押さえることで、DCF法を実務で応用しやすくなります。
それぞれ解説していきますので、ぜひ参考にしてください。
FCF(フリーキャッシュフロー)
フリーキャッシュフローとは、営業活動によって手元に残ったお金から、今後の投資に必要な金額を差し引いた後の、企業が自由に使える資金を意味します。
税引後の営業利益をベースに、減価償却費を足し戻し、売掛金や買掛金の相殺を考慮した上で、工場への設備投資額などを除いたものがフリーキャッシュフローです。
投資家にとっては、配当や株式の買い戻しの原資となるため、企業の実際の稼ぐ力を測る重要な指標です。
会計上の利益だけでは企業の価値を正しく測れないため、実際に手元に残る資金であるフリーキャッシュフローを基準にすることが、DCF法の信頼性を高める根拠となります。
割引率
DCF法では、将来のキャッシュフローを現在の価値に直すために割引率を用います。
この割引率には、一般的に加重平均資本コスト(WACC)が使われます。
WACCとは、企業が資金調達をするにあたり、借入による場合(利息などのコストが発生)と増資による場合(配当などのコストが発生)それぞれの資金コストを加重平均したものです。
割引率が高ければ企業の価値は小さく評価され、逆に低ければ企業の価値は大きくなります。
たとえば、安定した大企業はリスクが低いため割引率も低めに設定され、成長段階にあるベンチャー企業はリスクが高いため割引率が高めに設定される傾向があります。
割引率の適切な設定が、DCF法の結果の正確性を左右する重要なポイントです。
ターミナルバリュー(TV)
ターミナルバリューとは、事業計画で予測できる期間を超えた後も企業が継続して価値を生み出すと仮定して、その将来の価値を一括で計算したものです。
たとえば、予測可能な5年間のキャッシュフローをDCFで評価した後、6年目以降はターミナルバリューとしてまとめて評価します。
実際の計算では、最終年度のフリーキャッシュフローを割引率と永久成長率を用いた数式で割り戻して求めます。
上記の値を加えることで、企業全体の価値がより現実に近づくのです。
ターミナルバリューは企業の長期的な収益力を反映するため、DCF法における欠かせない要素になります。
永久成長率
永久成長率とは、予測期間終了後も企業のキャッシュフローが一定の割合で増加すると仮定して設定する成長率のことです。
通常は、経済全体の成長率や業界の安定的な伸び率を参考に決定します。
たとえば、日本国内の長期的な名目GDP成長率が2%程度と予測される場合、永久成長率もそれに近い数値で設定することが多いです。
数値を高く見積もれば企業価値は膨らみますが、過度に楽観的な設定は現実離れした評価を導いてしまいます。
逆に過小に見積もれば企業価値が過小評価される恐れがあります。
成長率を適切に設定することが、DCF法を実務で活用する際の信頼性を高める大切なポイントです。
DCF法の計算式と計算方法をわかりやすく解説
DCF法は、企業価値を算定するためにいくつかの手順を踏んで計算する方法です。
まず、営業活動や投資活動から算出されるフリーキャッシュフローを求め、その後に資本コストを反映した割引率を計算します。
さらに、予測期間を超える将来の価値を示すターミナルバリューを設定し、最後に各期の現在価値を合算することで企業価値を算出します。
上記の手順を正しく理解すれば、実務の現場でも活用できる評価方法として有効です。
それぞれ解説していきますので、ぜひ参考にしてください。
①FCF(フリーキャッシュフロー)の計算
フリーキャッシュフローとは、営業活動によって得られる現金収入から投資活動に必要な支出を差し引いた後に残る資金です。
計算式は「営業活動に基づくキャッシュフロー-投資によるキャッシュアウト」で表されます。
たとえば、ある会社が営業活動で毎年1,000万円の利益を生んでいるとします。利益に対する税率が30%で、経費計上された減価償却費が100万円、また設備投資に300万円を投じていた場合、フリーキャッシュフローは1,000万円×(1-30%)+100万円-300万円=500万円となります。
この数字は、債権者や株主へ分配できる現金の源泉を意味するため、DCF法において最も重要な要素のひとつです。
利益の額ではなく、実際に使える資金を基準にしている点がDCF法の信頼性を高めています。
企業の将来価値を測るうえで、FCFを的確に把握しましょう。
②割引率の算定
DCF法では、将来のキャッシュフローを現在の価値に直すために割引率を使います。
この割引率として一般的に用いられるのが加重平均資本コスト(WACC)です。
WACCの計算式は以下のとおりです。
ここで、負債コストとは支払利息を有利子負債で割った値であり、株主資本コストは株主が期待する収益率を指します。
たとえば、低金利で借入をしている企業は負債コストが低くなり、結果的にWACCも下がり、株主が高いリターンを求める場合は株主資本コストが高くなり、WACCも上昇します。
割引率の適切な設定は、企業価値を大きく左右するため重要なポイントとなります。
③TV(ターミナルバリュー)の計算
ターミナルバリューは、予測期間を超える将来のキャッシュフローを一括で評価する仕組みです。
DCF法では、将来すべてのキャッシュフローを無限に予測することは不可能なため、一定の年数を区切ってその先の価値をまとめて計算します。
具体的には以下の式で求めます。
たとえば、最終年度のフリーキャッシュフローが1億円、割引率が8%、永久成長率が2%とした場合、ターミナルバリューは、以下の計算式になります。
この金額を加えることで、企業全体の価値が現実に即した水準になります。
ターミナルバリューは、DCF法において長期的な企業価値を表す要となる計算要素です。
④企業価値の算出
最後に、各期ごとに計算したフリーキャッシュフローを割引率で現在価値になおし、合計することで企業価値を算出します。
さらに、ターミナルバリューを同様に割り引いて加えることで、最終的なDCFによる企業価値が導かれます。
つまり、企業が将来生み出すと期待される資金をすべて現在価値に換算し、その合計をもって評価するのです。
上記の計算によって、将来性を含めた企業の実力を数値で示すことができます。
DCF法でエクセルを使い計算する方法
DCF法を実務で利用する際には、表計算ソフトであるエクセルを用いる方法が一般的です。
1年目から5年目までは、各年度のフリーキャッシュフローを割引率で割り戻して計算します。
そして6年目以降については、ターミナルバリューを算出して同様に割り引くことで、企業全体の価値を求める流れになります。
つまり、計算は「1〜5年目」と「6年目以降」で方法が分かれるのです。
それぞれ解説していきますので、ぜひ参考にしてください。
1〜5年目
エクセルで1年目から5年目までのDCFを計算するには、各年度のフリーキャッシュフローを割引率で割り戻す式を使います。
具体的には以下の計算式です。
たとえば、1年目のフリーキャッシュフローが1,000万円で割引率を8%とすると「=1000/(1+0.08)^1」となり、現在価値は約926万円となります。
同様に2年目以降も、年数を2や3と変えて計算していきます。
5年間の各年度で得られる現在価値を求め、その合計を出すことで、予測期間の価値を把握可能です。
上記の方法を使うことで、エクセル上で簡単に将来の収益を現在の金額に置き換えられます。
6年目以降
6年目以降の計算では、ターミナルバリューを用います。
ターミナルバリューは以下の手順で入力すれば算出可能です。
上記の値を現在価値になおすために、5年間分の割引をかけるので以下を入力します。
たとえば、5年目のフリーキャッシュフローが1億円、割引率が8%、永久成長率が2%の場合、ターミナルバリューは17億円です。
17億円を「(1+0.08)^5」で割ることで、現在の価値として約11億5,000万円が算出されます。
こうして計算された金額を1〜5年目までの現在価値に加えると、企業全体の価値を導くことが可能です。
エクセルを使えば、自動計算で修正やシナリオ比較も容易になるため、実務での活用に適しています。
まとめ
DCF法は、将来のキャッシュフローを現在価値に割り引き、合計して企業価値を評価する手法です。
株価水準に依存せず、事業の実態に基づいた理論的に整合性のある評価が可能で、M&Aや投資判断にも広く用いられます。
メリットは、将来性を含めた客観的な価値を算定できる点であり、交渉材料としても有効ですが、一方で、キャッシュフロー予測や割引率設定に依存するため、不確実性が高いと結果が大きく変動するデメリットがあります。
エクセルを使えば計算やシナリオ比較も容易で、実務でも活用していきましょう。
【期間限定】会計ソフト移行で最大70万円ポイント還元!
オンプレミス型・インストール型をご利用の企業様へ。 移行作業をプロに任せる「導入支援サービス(サクセスプラン)」の費用相当額が、最大70万円分ポイント還元されるお得なキャンペーンを実施中です。
最後までこの記事をお読みの方に人気のガイド4選
最後に、ここまでこの記事をお読みの方によく活用いただいている人気の資料を紹介します。こちらもすべて無料ですので、ぜひお気軽にご活用ください。
インボイス制度 徹底解説(2024/10最新版)
インボイス制度は施行後もさまざまな実務論点が浮上し、国税庁によるQ&Aの追加・改訂が続いています。これを受けて、「結局どうすればいいのか、わからなくなってしまった」という疑問の声も多く聞かれるようになりました。
そこで、インボイス制度を改めて整理し、実務上の落とし穴や対応のヒントまで網羅的に解説した最新資料を作成しました。問題なく制度対応できているかの確認や、新人社員向けの教育用など、様々な用途にご活用いただける充実の資料です。
電子帳簿保存法 徹底解説(2025年10月 最新版)
電子帳簿保存法は、1998年の制定以降、これまでに何度も改正を重ねてきました。特に直近数年は大きな改正が続いた上に、現在も国税庁による一問一答の追加・改定が続いており、常に最新情報の把握が必要です。
70P以上にわたるボリュームであることから、ダウンロードいただいた方から大好評をいただいている1冊です。
マネーフォワード クラウド請求書Plus サービス資料
マネーフォワード クラウド請求書Plusは、営業事務・経理担当者の請求業務をラクにするクラウド型請求書発行システムです。
作成した請求書はワンクリックで申請・承認・送付できます。一括操作も完備し、工数を削減できます。
マネーフォワード クラウド債権管理 サービス資料
マネーフォワード クラウド債権管理は、入金消込・債権残高管理から滞留督促管理まで、 広くカバーする特定業務特化型のクラウドサービスです。
他社の販売管理システムと連携して、消込部分のみでのご利用ももちろん可能です。
※ 掲載している情報は記事更新時点のものです。
会計の知識をさらに深めるなら
※本サイトは、法律的またはその他のアドバイスの提供を目的としたものではありません。当社は本サイトの記載内容(テンプレートを含む)の正確性、妥当性の確保に努めておりますが、ご利用にあたっては、個別の事情を適宜専門家にご相談いただくなど、ご自身の判断でご利用ください。
関連記事
中小企業等経営強化法とは?メリットや経営力向上計画の申請方法を解説
「中小企業等経営強化法とは何だろう」「制度を活用したいので、申請方法が知りたい」 このように悩む方も多いのではないでしょうか。 中小企業等経営強化法は、うまく活用すれば税制優遇や低…
詳しくみるブラックリストとは?与信審査への影響や載った場合の資金調達方法も紹介
ブラックリストとは、クレジットカードの支払いや債務の返済が滞った時に信用情報機関に残る記録です。情報が残っている間は、金融期間からの借り入れや新たなカードの申込は難しくなります。ブ…
詳しくみる約束手形の仕組みとは?小切手との違いやメリット、仕訳方法
会社を経営していると「約束手形」「不渡手形」「裏書手形」「為替手形」「受取手形」「支払手形」など、『手形』というキーワードが付く取引を目にすることが多いのではないでしょうか。今回は…
詳しくみる支払督促申立書とは?流れや書き方、費用を徹底解説
支払督促申立書は、裁判所を介して債務者に支払の督促を行うための文書です。 本記事では、支払督促の基本的な仕組みや流れ、必要な書類の書き方と申立て方法、発生する費用についてまとめまし…
詳しくみる売上管理とは?エクセルや会計ソフトで管理するポイント
売上を管理する方法については、エクセルで売上管理表を作成したり、会計ソフトの機能を利用したりする方法があります。 取引のしかたや会社の規模にもよりますが、売上管理においてポイントと…
詳しくみるファームバンキングとは?インターネットバンキングとの違いや代替サービスを解説
ファームバンキングは、企業のパソコンと銀行を専用回線で接続し、振込や入出金確認などの取引を完結させる仕組みです。インターネットバンキングとは異なり、業務ソフトとの連携や安定した通信…
詳しくみる会計の注目テーマ
- 勘定科目 消耗品費
- 国際会計基準(IFRS)
- 会計帳簿
- キャッシュフロー計算書
- 予実管理
- 損益計算書
- 減価償却
- 総勘定元帳
- 資金繰り表
- 連結決算
- 支払調書
- 経理
- 会計ソフト
- 貸借対照表
- 外注費
- 法人の節税
- 手形
- 損金
- 決算書
- 勘定科目 福利厚生
- 法人税申告書
- 財務諸表
- 勘定科目 修繕費
- 一括償却資産
- 勘定科目 地代家賃
- 原価計算
- 税理士
- 簡易課税
- 税務調査
- 売掛金
- 電子帳簿保存法
- 勘定科目
- 勘定科目 固定資産
- 勘定科目 交際費
- 勘定科目 税務
- 勘定科目 流動資産
- 勘定科目 業種別
- 勘定科目 収益
- 勘定科目 車両費
- 簿記
- 勘定科目 水道光熱費
- 資産除去債務
- 圧縮記帳
- 利益
- 前受金
- 固定資産
- 勘定科目 営業外収益
- 月次決算
- 勘定科目 広告宣伝費
- 益金
- 資産
- 勘定科目 人件費
- 予算管理
- 小口現金
- 資金繰り
- 会計システム
- 決算
- 未払金
- 労働分配率
- 飲食店
- 売上台帳
- 勘定科目 前払い
- 収支報告書
- 勘定科目 荷造運賃
- 勘定科目 支払手数料
- 消費税
- 借地権
- 中小企業
- 勘定科目 被服費
- 仕訳
- 会計の基本
- 勘定科目 仕入れ
- 経費精算
- 交通費
- 勘定科目 旅費交通費
- 電子取引
- 勘定科目 通信費
- 法人税
- 請求管理
- 勘定科目 諸会費
- 入金
- 消込
- 債権管理
- スキャナ保存
- 電子記録債権
- 入出金管理
- 与信管理
- 請求代行
- 財務会計
- オペレーティングリース
- 新リース会計
- 購買申請
- ファクタリング
- 償却資産
- リース取引


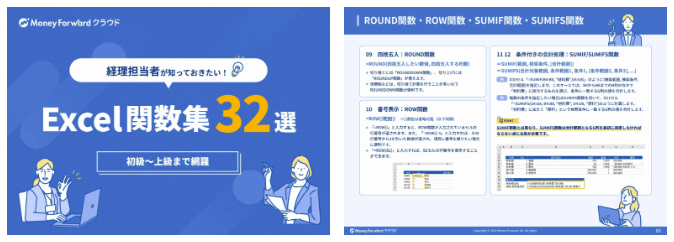



.png)

