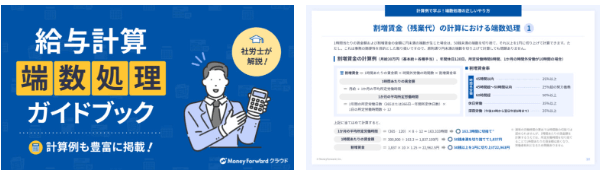- 更新日 : 2025年11月4日
フレックスタイムの給与計算とは?残業・不足時の注意点
フレックスタイム制の給与計算は、日々の労働時間ではなく、「清算期間全体の総労働時間」で過不足を判断するのが基本です。そのため、時間外手当(残業代)や不足分の控除は、すべてこの清算期間単位での計算結果によって決まります。
しかし、月々の集計時に残業代をどう計算し、時間不足をどう処理すべきかなど、担当者が判断に迷う場面があります。この記事では、フレックスタイム制の給与計算における基本的なルールから、間違いやすいポイントまでをわかりやすく解説します。
目次
そもそもフレックスタイム制とは?
フレックスタイム制とは、あらかじめ定められた総労働時間の範囲内で、従業員が日々の始業時刻と終業時刻を自主的に決定できる制度です。
働き方の多様化に対応できるため多くの企業で導入されていますが、その計算ロジックは独特です。制度を正しく理解するために、まずは基本的な用語と仕組みを確認しましょう。
この記事をお読みの方におすすめのガイド4選
続いてこちらのセクションでは、この記事をお読みの方によく活用いただいている人気の資料・ガイドを簡単に紹介します。すべて無料ですので、ぜひお気軽にご活用ください。
※記事の内容は、この後のセクションでも続きますのでぜひ併せてご覧ください。
給与計算の「確認作業」を効率化する5つのポイント
給与計算の確認作業をゼロにすることはできませんが、いくつかの工夫により効率化は可能です。
この資料では、給与計算の確認でよくあるお悩みと効率化のポイント、マネーフォワード クラウド給与を導入した場合の活用例をまとめました。
給与規程(ワード)
こちらは、給与規程のひな形(テンプレート)です。 ファイルはWord形式ですので、貴社の実情に合わせて編集いただけます。
規程の新規作成や見直しの際のたたき台として、ぜひご活用ください。
給与計算 端数処理ガイドブック
給与計算において端数処理へのルール理解が曖昧だと、計算結果のミスに気づけないことがあります。
本資料では、端数処理の基本ルールをわかりやすくまとめ、実務で参照できるよう具体的な計算例も掲載しています。
給与計算がよくわかるガイド
人事労務を初めて担当される方にも、給与計算や労務管理についてわかりやすく紹介している、必携のガイドです。
複雑なバックオフィス業務に悩まれている方に、ぜひご覧いただきたい入門編の資料となっています。
フレックスタイム制の給与計算で重要な3つの時間
フレックスタイム制の給与計算は、「総労働時間」「法定労働時間」「実労働時間」という3つの時間を正しく把握し、比較することから始まります。
これらの時間を混同すると計算ミスに直結するため、それぞれの定義を正確に理解しておくことが不可欠です。
1. 総労働時間(所定労働時間)
会社と従業員の間で、契約上働くことが定められた時間です。これは労使協定で必ず定めなければならず、以下の計算式で算出するのが一般的です。
例えば、1週間の所定労働時間を40時間、清算期間が31日の月の場合、「31日 ÷ 7日 × 40時間 = 177.1時間」がその月の総労働時間となります。この時間は、後述する法定労働時間の総枠内でなければなりません。
2. 法定労働時間
労働基準法で定められた労働時間の上限で、原則として「1日8時間・週40時間」です。フレックスタイム制では、清算期間全体での法定労働時間の総枠を計算し、これを超えた分が割増賃金の対象となる「法定外残業」となります。
上記の例(31日の月)では、法定労働時間の総枠も177.1時間となります。
3. 実労働時間
従業員が清算期間内に実際に働いた合計時間です。タイムカードや勤怠管理システムなど、客観的な方法で正確に記録・把握する必要があります。
【ケース別】フレックスタイムの給与計算方法
実際に時間が超過した場合や不足した場合など、フレックスタイムの具体的なケースごとの給与計算方法を見ていきましょう。
時間が超過した場合(残業代の計算)
清算期間内の実労働時間が法定労働時間の総枠を超えた分が、割増賃金の対象となる時間外労働です。日々の労働時間が8時間を超えても、ただちに時間外労働とはなりません。
- 実労働時間と2つの基準時間を比較する
- 実労働時間が総労働時間を超え、法定労働時間の枠内である時間
→ 法定内残業(割増なし、通常の賃金1.0倍を支払う) - 実労働時間が法定労働時間の総枠を超えた時間
→ 法定外残業(割増あり、1.25倍以上の賃金支払いが必要)
- 実労働時間が総労働時間を超え、法定労働時間の枠内である時間
- 割増率を乗じて残業代を計算する
法定外残業となった時間数に対し、以下の割増率を適用します。休日労働や深夜労働は、フレックスタイムの枠とは別で計算・支給が必要です。
| 種類 | 条件 | 割増率 |
|---|---|---|
| 法定外残業 | 法定労働時間の超過分 | 25%以上 |
| 月60時間を超える時間外労働 | 50%以上 | |
| 休日労働 | 法定休日の労働 | 35%以上 |
| 深夜労働 | 22時~翌朝5時の労働 | 25%以上 |
36協定との関係
時間外労働の上限を定める36協定の計算対象となるのは、割増賃金が発生する「法定外残業」の時間です。フレックスタイム制であっても、36協定の締結と届出は必須であり、上限時間を超えた労働は法律違反となります。
労働時間が不足した場合(控除・繰越の計算)
実労働時間が総労働時間に満たなかった場合、「不足分を当月の給与から控除する」または「不足分を翌月に繰り越す」のいずれかで対応します。
不足分を給与から控除する場合
不足した時間分の賃金を、その月の給与から差し引く方法です。これは「ノーワーク・ノーペイの原則(働いていない分は支払わない)」に基づく基本的な処理方法になります。繰り越しの定めがなければ、この方法が適用されます。この際、不足時間に対して遅刻や早退と同じようにマイナスの勤怠控除として給与計算を行います。
- 計算例: 時給2,000円の従業員が5時間不足した場合
→ 2,000円 × 5時間 = 10,000円を控除
不足分を翌月に繰り越す場合
清算期間における総労働時間に実労働時間が満たない場合には、翌清算期間に不足分を繰り越すことができます。不足時間を翌清算期間に上乗せして働くことで相殺する方法です。このような方法を取ることで、不足時間によって給与が控除されることを防げます。
逆に清算期間における実労働時間が総労働時間を上回っている場合、超過分を翌清算期間に繰り越すという扱いは認められません。このような場合には、その清算期間内で超過分を清算することが必要です。
- 運用例: 9月に5時間不足し、10月の総労働時間が160時間の場合
→ 10月の目標労働時間は 160時間 + 5時間 = 165時間 となる
有給休暇を取得した場合の扱い
年次有給休暇を取得した日は、実際に働いていなくても、所定労働時間分を勤務したものとして扱い、賃金計算に反映します。
例えば、標準となる1日の労働時間を8時間と定めている場合、有給休暇を1日取得すれば、実労働時間に8時間がプラスされます。そのため、有給休暇を使ったことで実労働時間が不足し、給料が減るということはありません。
フレックスタイム制の給与計算を導入するポイント
フレックスタイム制を適法かつ円滑に運用するためには、「就業規則への規定」と「労使協定の締結」が不可欠です。
特に労使協定では、以下の項目を必ず定めなければなりません。また、清算期間が1ヶ月を超える場合には、当該協定を労働基準監督署へ届け出ることも必要です。
- 対象となる労働者の範囲
- 清算期間(3ヶ月以内の範囲)
- 清算期間における総労働時間(所定労働時間)
- 標準となる1日の労働時間(有給休暇取得時の計算に用いる)
- コアタイム・フレキシブルタイム(任意)
- 労使協定の有効期間(清算期間が1ヶ月を超える場合)
これらのルールを定めずに制度を運用すると、未払残業代の請求など、深刻な労務トラブルに発展するリスクがあります。
就業規則への規定
まず、フレックスタイム制を導入する旨を就業規則に明記する必要があります。常時10人以上の労働者を使用する事業場では就業規則の作成と届出が義務付けられており、ここに始業・終業時刻に関する規定があるためです。
具体的には、「始業及び終業の時刻は、労働者の自主的な決定に委ねる」といった趣旨の一文を追記し、フレックスタイム制が適用される根拠を明確にします。これにより、制度が個別の合意ではなく、会社全体の正式なルールとして位置づけられます。
労使協定の締結
次に、事業場の労働者の過半数で組織する労働組合、または労働者の過半数を代表する者との間で、書面による協定(労使協定)を締結します。これはフレックスタイム制の具体的な運用ルールを定める、最も重要な手続きです。特に以下の項目は、法律で定められた必須事項です。
- 対象となる労働者の範囲
制度を適用する従業員の範囲を具体的に定めます。「全従業員」とすることも、「営業部」「開発部のみ」と部署単位で限定することも可能です。 - 清算期間と起算日
労働時間を計算する期間(3ヶ月以内の範囲)とその開始日(例:毎月1日)を定めます。期間が長いほど柔軟な働き方が可能になりますが、給与計算が複雑になる側面もあります。 - 清算期間における総労働時間(所定労働時間)
従業員が清算期間中に働くべき契約上の時間(目標時間)です。この時間を基準に、労働時間の過不足を判断します。法定労働時間の総枠を超えない範囲で設定する必要があります。 - 標準となる1日の労働時間
有給休暇を取得した際に、何時間労働したものとみなすかの基準です。これを定めておかないと、有給休暇取得日の賃金計算が曖昧になり、トラブルの原因となります。 - コアタイム・フレキシブルタイム(任意)
任意ですが、円滑な業務連携のため設定する企業が多い項目です。必ず勤務すべき「コアタイム」と、その時間内であればいつでも勤務できる「フレキシブルタイム」を具体的に定めます。 - 労使協定の有効期間(清算期間が1ヶ月を超える場合)
フレックスタイムの清算期間が1ヶ月を超える場合には、当該労使協定の有効期間を定めなくてはなりません。ただし、労働協約による場合は除きます。
フレックスタイムの給与計算でよくある勘違いとトラブル防止策
柔軟性が高い一方で、誤解されやすいのがフレックスタイム制です。担当者も従業員も正しい知識を持つことが、トラブル防止の鍵となります。
フレックスタイム制は残業代が出ない制度?
フレックスタイム制でも、法律で定められた労働時間を超えて働いた分については、割増賃金(残業代)の支払い義務が明確にあります。
「1日の労働時間が8時間を超えても、すぐには残業にならない」という特徴から誤解されがちですが、それはあくまで計算の単位が「日」から「清算期間」に変わるだけです。清算期間全体で集計した実労働時間が、法定労働時間の総枠を超えた場合は、その超過分に対して必ず残業代を支払わなければならず、支払いを怠ると労働基準法違反となります。
コアタイムがなければ、最低労働時間もない?
法律で定められた「1日に最低〇時間働かなければならない」といった最低労働時間の規定はありません。しかし、それと「働くべき目標時間がない」はイコールではありません。
フレックスタイム制では、必ず契約上の「総労働時間」が定められています。これは従業員が清算期間内に働くべき目標の時間であり、実労働時間がこれに満たなければ、給与から不足分が控除されるなどして給料が減る可能性があります。そのため、事実上、達成すべき労働時間は存在します。
従業員が自由に働けるので、厳密な勤怠管理は不要?
いいえ、それは間違いであり、法的なリスクも伴います。会社(使用者)には、従業員の労働時間を客観的な方法で正確に把握する義務があります。
これは、正しい給与計算(特に残業代の算出)を行うための大前提であると同時に、従業員の健康を守るため(長時間労働の防止)にも不可欠です。ICカードやPCのログ、勤怠管理システムなど客観的な記録に基づかない自己申告だけの管理は、実際の労働時間を証明できず、サービス残業や労務トラブルの温床となるため、絶対に行わないでください。
フレックスタイムの給与計算を効率化するツール
フレックスタイム制の複雑な給与計算を手作業で行うのは、計算ミスや担当者の負担増大につながります。勤怠管理と連動したツールの活用がおすすめです。
| ツール | メリット | デメリット |
|---|---|---|
| 勤怠管理システム |
| 導入・運用にコストがかかる |
| Excel・スプレッドシート |
|
|
企業の規模や管理体制に合わせて、最適なツールを選択することが重要です。
フレックスタイムの給与計算は「清算期間」の総労働時間が基準
フレックスタイム制の給与計算は、日々の労働時間ではなく「清算期間」全体の総労働時間を基準に行います。
清算期間内の実労働時間が法定労働時間の総枠を超えた場合は、その超過分に対して割増賃金(残業代)の支払いが必要です。逆に、総労働時間に満たなかった場合は、不足分を給与から控除するか、翌月に繰り越して精算します。この複雑な計算を正確に行い、公平な制度運用を実現するためにも、事前のルール整備と勤怠管理システムを整えておくことが大切です。
※ 掲載している情報は記事更新時点のものです。
人事労務の知識をさらに深めるなら
※本サイトは、法律的またはその他のアドバイスの提供を目的としたものではありません。当社は本サイトの記載内容(テンプレートを含む)の正確性、妥当性の確保に努めておりますが、ご利用にあたっては、個別の事情を適宜専門家にご相談いただくなど、ご自身の判断でご利用ください。
関連記事
三重県の給与計算代行の料金相場・便利なガイド3選!代表的な社労士事務所も
三重県で事業を運営する企業にとって、給与計算は日々の業務の中でも重要かつ煩雑な作業の一つです。正確な給与計算を行うためには専門的な知識と時間が必要であり、多くの企業が外部の給与計算…
詳しくみるボーナス(賞与)の前に退職したらもらえない?退職を伝えるタイミングと3つの注意点
基本的にボーナスの支給は、支給日に企業や職場に在籍していることが条件です。そのため、支給日前に退職したらもらえない場合がほとんどです。 実際に、大きな業績を上げて職場に貢献したにも…
詳しくみる扶養手当の条件は?支給対象となる必須要件や家族構成ごとの基準を解説
多くの企業で導入されている「扶養手当(家族手当)」ですが、その支給条件は法律で一律に決まっているわけではなく、会社の「就業規則(賃金規程)」によって定められています。 しかし実務上…
詳しくみる住民税を特別徴収しなくていい会社とは?普通徴収に切り替える方法も紹介
住民税の特別徴収は会社の義務ですが、一部例外があり普通徴収に切り替えられるケースもあります。 「特別徴収の対象外となるのは、どのような会社?」「普通徴収に切り替える方法は?」などと…
詳しくみる源泉所得税の納付書について書き方を解説!提出方法や期限も紹介
源泉所得税は、給与や報酬の支払者が、支払額の中から源泉徴収して国に納付する所得税のことです。通常、この源泉所得税の納付は、納付書を使用して手続きを行いますが、所得の種類ごとに使用す…
詳しくみる賞与支給通知書とは?通知義務や方法を解説!例文も紹介【無料テンプレ付き】
賞与支給通知書は、従業員に賞与額や支給条件を明確に伝えるための重要な書類です。 また、法令遵守や労務トラブルの回避においても重要な役割を持っています。 そこで本記事では、賞与支給通…
詳しくみる
-e1762740828456.png)