- 更新日 : 2026年2月24日
5時間勤務・5.5時間勤務で休憩は必要?労働基準法の定義や計算方法を解説!
労務管理において、休憩時間の付与は労働者の健康維持と生産性向上に直結する重要なテーマです。しかし、法律上のルールについては意外と知られていません。
5時間勤務のような比較的短い勤務時間の場合、休憩時間の付与は必要なのでしょうか。本記事では、労働基準法に基づく休憩時間の付与ルールや注意点を詳しく解説します。
目次
5時間勤務・5.5時間勤務で休憩は必要?
一般的に、勤務が昼食時間を挟む場合は「労働時間の長さに関係なく、お昼休みは付与される」と考えるのではないでしょうか。ただし、労働時間が一定時間以下である場合には、法律上、休憩時間を与える義務はありません。
労働基準法では、休憩時間が必要となるのは労働時間が6時間を超える場合です。
5時間勤務・5.5時間勤務は原則休憩なしで運用できますが、その日の業務状況によっては想定外に勤務が延びて6時間を超える可能性もあります。急な残業で労働時間が6時間を超えそうな場合、途中で適切に休憩を取らせて労働時間を調整することが求められます。従業員に「忙しいから休憩なしで働いてほしい」と頼むようなことは避けなければなりません。
たとえ本人が同意しても6時間超労働に休憩なしは違法であり、賃金を余分に支払う代替策も認められません。現場でトラブルを防ぐためにも、法定の休憩条件に抵触しそうな場合は事前にシフトを見直すか休憩を挟むなどの対応が必要です。
この記事をお読みの方におすすめのガイド4選
続いてこちらのセクションでは、この記事をお読みの方によく活用いただいている人気の資料・ガイドを簡単に紹介します。すべて無料ですので、ぜひお気軽にご活用ください。
※記事の内容は、この後のセクションでも続きますのでぜひ併せてご覧ください。
労働時間管理の基本ルール【社労士解説】
多様な働き方を選択できる「働き方改革」が世の中に広まりつつありますが、その実現には適切な労働時間管理が欠かせません。
労働時間に関する用語の定義や休憩・休日のルールなど、労働時間管理の基本ルールを社労士が解説します。
シフト変更申請書(エクセル)
シフト変更の申請にご利用いただける、エクセル形式の申請書です。ダウンロード後、お手元で直接入力や編集を行うことが可能です。
シフト管理や変更手続きの際にご活用ください。
休日・休暇の基本ルール
休日・休暇の管理は労務管理の中でも重要な業務です。本資料では、法令に準拠した基本のルールをはじめ、よくあるトラブルと対処法について紹介します。
休日・休暇管理に関する就業規則のチェックリスト付き。
時間外労働の管理 労基法違反から守る10のルール
年5日の有給休暇の取得が義務化され、企業には正確な休暇管理が求められています。
本資料では、有給休暇に関する基本ルールをはじめ、よくあるトラブルへの対処方法を社労士がわかりやすく解説しています。
労働基準法における休憩時間の定義は?
労働基準法では休憩時間についての定義が明記されていませんが、労働者が労働から離れることを保障された時間と解釈されています。労働基準法では、休憩時間の付与についてのルールが定められています。
労働時間が6時間超で45分、8時間超で60分の休憩が必要
労働基準法第34条第1項では、休憩時間の長さについて以下のように定められています。
- 労働時間が6時間を超え8時間以下の場合:少なくとも45分
- 労働時間が8時間を超える場合:少なくとも1時間
つまり、労働時間が6時間以下の場合、休憩時間の付与義務はありません。一方、6時間を超える場合には上記の付与基準に従って、企業はこれを下回らない範囲で休憩時間を設定する必要があります。
例えば、所定労働時間がちょうど8時間の場合には休憩は1時間ではなく、45分の付与でよいということです。しかし、所定労働時間を8時間とする企業では一般的に1時間の休憩時間を付与しています。これは労働基準法で定める基準を上回っているということになります。
パート・アルバイトなどの雇用契約に関係なく付与される
労働基準法は正社員だけでなく、パートタイムやアルバイト、契約社員などすべての労働者に対して適用される法律です。したがって、休憩時間の付与について定める法第34条第1項も、労働時間が6時間を超える場合には雇用形態にかかわらず適用され、使用者には休憩時間の付与が義務付けられています。
労働基準法における休憩時間の3原則とは?
労働基準法では休憩時間の長さに加え、休憩時間の与え方について「途中付与の原則」「自由利用の原則」「一斉付与の原則」を定めています。
途中付与の原則
使用者は、休憩時間を労働時間の途中に与えなければなりません(法第34条第1項)。「途中付与の原則」は、休憩時間を労働時間の合間に設けることを義務付けています。休憩時間が労働の開始直後や終了直前に与えられても、効果的な休息にならないためです。労働者が適切に疲労を回復し、再び効率良く働けるようにすることが目的であるため、就業開始前や終業後に休憩時間を設定することは認められません。
休憩時間の具体的な付与タイミングについて、法律上は明確な規定はありませんが、労働時間の途中に適切に配置することが求められます。なお、休憩時間の趣旨に反しなければ分割して付与することもできます。
自由利用の原則
使用者は、休憩時間を自由に利用させなければなりません(法第34条第3項)。「自由利用の原則」は、休憩時間中に労働者を労働から完全に解放し、その時間をどのように過ごすかを労働者の自由に委ねることを定めるものです。休憩時間中は、労働者が自由に食事をしたり、携帯電話を使用したり、外出したり、昼寝をしたりすることができます。
ただし、事業場内で休憩する場合は、就業規則等に記載された事業場のルールに従う必要があります。例えば、休憩時間中の外出を許可制にするなど、事業場の規律を保持するために必要な制限を加えることは、休憩の目的を損なわない限り差し支えないとされています。しかしながら、使用者が休憩時間中に業務を指示することは、認められません。
一斉付与の原則
使用者は、休憩時間を労働者に一斉に与えなければなりません(法第34条第2項)。「一斉付与の原則」には、同一の職場で同じ時間帯に休憩付与を義務付けることによって、各人の休憩取得を促すという目的があります。
ただし、公衆に不便が生じるなど一斉付与が馴染まない業種や、業務の円滑な運営に支障が生じるような場合には、例外が認められています(法第40条、法第34条第2項ただし書)。
下記の業種が該当します(労働基準法施行規則第31条)。
- 運輸交通業
- 商業
- 金融保険業
- 映画・演劇業
- 通信業
- 保健衛生業
- 接客娯楽業
- 官公署の事業
上記の業種に該当しない場合でも、労使協定を締結することで、一斉付与の対象としないことが可能です。
勤務時間別の休憩時間の計算方法は?
ここでは勤務時間の3つのパターンについて、休憩時間の付与のタイミングと計算方法を考えてみましょう。いずれも、就業規則上は「所定労働時間8時間00分・休憩時間45分」と定めています。
- 始業 9:00
- 休憩時間 12:00~12:45
- 終業 17:45
労働時間がちょうど8時間であるため、休憩時間は最低限の45分でも適法です。
- 始業 9:00
- 休憩時間 12:00~12:45
- 残業開始 17:45
- 休憩時間 18:45~19:00
- 終業 20:00
このケースではパターン1と同様に、就業規則では「所定労働時間8時間」であるのに対し、最低限の45分しか付与していません。しかし、突発的に時間外労働が生じたため、労働時間は8時間を超えており、少なくとも1時間の休憩を付与しなければなりません。したがって、時間外労働を開始後、途中で追加の15分の休憩を追加しています。
- 始業 9:00休憩時間 12:00~12:45
- 休憩時間(追加)12:45~13:00
- 残業開始 18:00
- 終業 20:00
突発的ではなく、事前に時間外労働することが予定されている場合は、通常の45分の休憩に15分を追加することで労働時間が8時間を超えても最低限の1時間の休憩を確保することができます。なお、パターン2、パターン3とも、追加する休憩は労働時間の間でなければなりません。労働者からの申出があったとしても、終業を早めて休憩付与に換えることは労働基準法違反となります。
休憩時間を付与する際の注意点は?
労働基準法で定められている休憩時間について解説してきました。改めて、付与する際の3つの注意点を確認しておきましょう。
休憩時間の最低基準を遵守する
以下の最低基準を遵守しなければなりません。
- 労働時間が6時間以内:休憩時間の付与義務なし
- 労働時間が6時間超8時間以内:最低45分の休憩
- 労働時間が8時間超:最低1時間の休憩
これらはあくまで最低基準であり、労働時間や業務の性質に応じて、より長い休憩時間を設定することもできます。また、労働時間が6時間ちょうどの場合は休憩を付与する義務がありませんが、従業員の健康維持のために休憩を設けることが推奨されます。
休憩時間の3原則を遵守する
労働基準法第34条に基づき、「途中付与の原則」「一斉付与の原則」「自由利用の原則」の3つを遵守しましょう。特に、自由利用の原則については、労働基準法第34条第3項で「使用者は、第一項の休憩時間を自由に利用させなければならない」と明確に規定されています。休憩中に業務を指示したり、電話番などで待機を強いたりすることは法律違反となる可能性があるため、注意が必要です。
雇用形態による差別を避ける
休憩時間の付与は正社員、パートタイム、アルバイト、契約社員、派遣社員などの雇用形態にかかわらず適用されます。労働基準法では雇用形態による区別を設けていないため、同じ労働時間であれば、同じ休憩時間を付与する必要があります。例えば、正社員には1時間の休憩を与え、同じ労働時間のパートタイム従業員には45分の休憩しか与えないといった取り扱いは、労働基準法違反となる可能性があります。雇用形態にかかわらず、労働時間に応じて公平に休憩時間を付与することが重要です。
休憩時間に違反した場合の罰則は?
休憩時間の付与について労働基準法に違反した場合、どのような罰則があるのでしょうか。労働基準法第119条第1号では、第34条(休憩時間)の規定に違反した場合の罰則が定められています。具体的には「六箇月以下の懲役又は30万円以下の罰金に処する」と規定されています。
この罰則は休憩時間を与えなかった場合や、法定の休憩時間を下回る休憩しか与えなかった場合に適用されます。また、休憩時間の3原則(途中付与、一斉付与、自由利用)に違反した場合も同様の罰則の対象となります。
罰則の対象となるのは、通常は事業主や事業場の責任者です。ただし、法人の場合は法人自体も罰金刑の対象となる可能性があります(労働基準法第121条)。
適切な休憩時間で従業員の健康と生産性を守ろう!
休憩時間の適切な付与は、従業員の健康と生産性を守るだけでなく、労働基準法違反のリスクを回避するためにも重要です。5時間勤務の場合、法律上は休憩時間の付与義務はありませんが、業務の性質や従業員の要望に応じて柔軟に対応するとよいでしょう。
休憩時間の3原則を遵守し、従業員の雇用形態にかかわらず公平に付与することで、よりよい職場環境の実現につながります。
※ 掲載している情報は記事更新時点のものです。
人事労務の知識をさらに深めるなら
※本サイトは、法律的またはその他のアドバイスの提供を目的としたものではありません。当社は本サイトの記載内容(テンプレートを含む)の正確性、妥当性の確保に努めておりますが、ご利用にあたっては、個別の事情を適宜専門家にご相談いただくなど、ご自身の判断でご利用ください。
関連記事
- # 勤怠管理
2026年最新 – 勤怠管理システムおすすめ比較!機能・料金・クラウド対応など
勤怠管理システムを導入すると、タイムカード(打刻)機能により従業員の労働時間を正確に把握することができます。シフト管理機能など、その他にも多くの機能が備わっているため、勤怠管理業務…
詳しくみる - # 勤怠管理
裁量労働制とは?2024年の法改正の内容は?対応方法についても紹介!
裁量労働制とは、実際に働いた時間ではなく、あらかじめ労使で取り決めた時間を労働したものとみなして賃金を支払う制度です。裁量労働制には一定のルールがあり、適用可能な職種も限られていま…
詳しくみる - # 勤怠管理
就業規則への36協定の記載例|テンプレートをもとに記入のポイントを解説
企業の労務管理において、従業員に時間外労働(残業)や休日労働を命じる場合、36協定の締結・届出と、就業規則への明示が必要です。 しかし「就業規則にどのように規定すればよいのかわから…
詳しくみる - # 勤怠管理
遅早時間(遅刻早退控除)とは?計算方法や運用時の注意点、トラブルの防止法を解説
従業員の給与を正しく計算するためには、適切な勤怠管理が欠かせません。従業員全員が常に定められた時間通りに勤務できれば計算は簡単ですが、実際にはさまざまな理由で本来の勤務時間と実際の…
詳しくみる - # 勤怠管理
勤務間インターバル制度とは?努力義務としてやるべきこと
働き方改革の一環として、労働時間等設定改善法が改正され、2019年4月1日から勤務間インターバル制度の実施が事業主の努力義務とされています。しかし、努力義務にとどまっていることもあ…
詳しくみる - # 勤怠管理
深夜労働の割増率は?時間帯や残業・休日との重複計算を解説
深夜帯に働く方にとって、深夜労働の割増賃金(深夜手当)は正当な権利であり、生活を支える重要な収入源です。深夜労働の基本的な割増率は25%以上ですが、時間外労働(残業)や休日労働と重…
詳しくみる
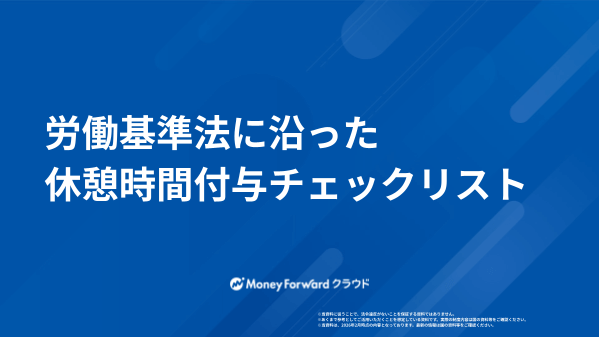

-e1763454988832.jpg)

