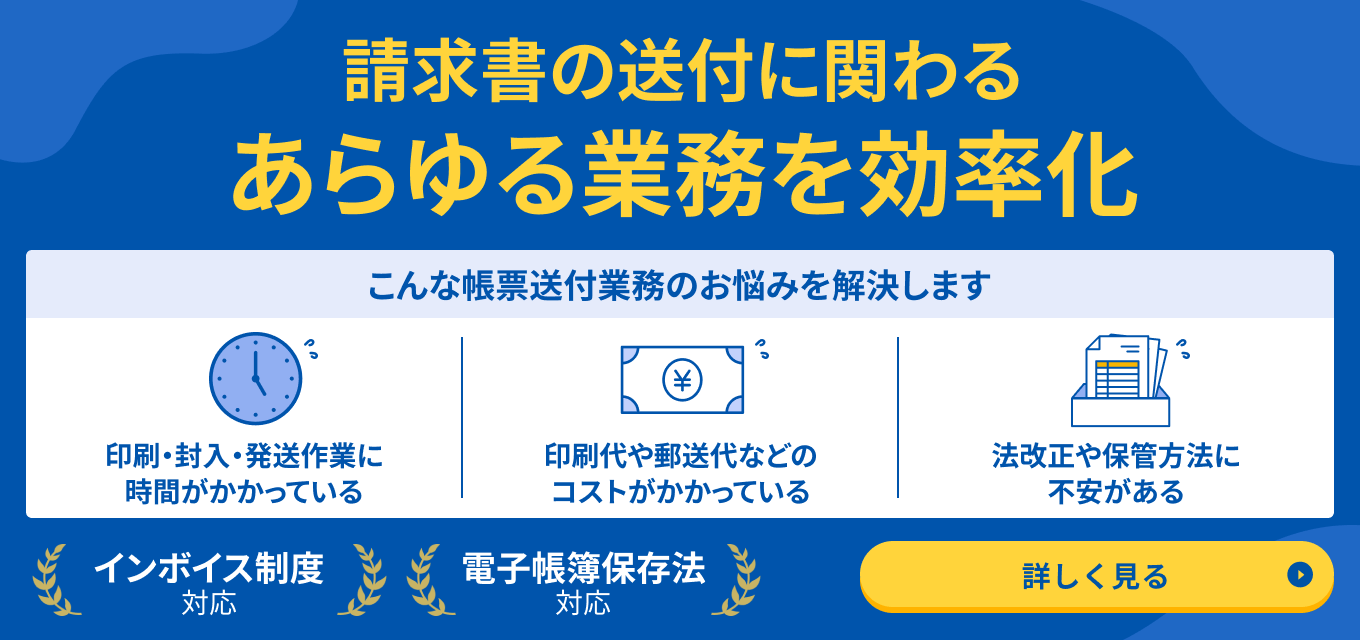経理業務のBPO(ビジネス・プロセス・アウトソーシング)の導入を検討・推進している企業は増えていますが、今回はその中でも、最近BPOするケースが増えている、請求書に関する業務についてお話いたします。
目次
受領した請求書をBPO(ビジネス・プロセス・アウトソーシング)する
請求書に関するBPOといいましたが、請求書の方でも受領した請求書の話です。つまり、支払いをすることになる請求書です。
企業によっては、毎月受領する請求書の件数が数百件にのぼるケースもありますし、より規模の大きい企業の場合は、数千件という途方もない数を受領しているケースもあります。
受領した請求書は、発注した部署で上長含めて内容を確認して、その後経理部門に送られ、必要事項を確認して支払いに回ることになります。
さらに、経理部門では請求書をもとに伝票の起票を行ったり、発注部門が計上した伝票を承認して、帳簿に反映させる作業を行うことになります。
これらの業務のうち一部をBPOすることで企業の業務負担を減らしているのですが、どのような内容をアウトソーシングしているのでしょうか。
BPOするためのセットアップ
受領した請求書ですが、以前は紙で受け取った請求書をBPOベンダーに送付しているケースが多かったです。
その場合は、受領する請求書の件数が多いと送付する資料も膨大になりますし、資料の紛失リスクも残ることになります。そのような手間とリスクを勘案して、受領した請求書のBPOを進めてこなかった企業も一定数あったと思われます。
ただ、最近は情報共有のためのクラウド型の会計システムやストレージサービスも充実してきており、それらを活用してBPOを推進するケースが増えてきています。具体的には、受領した請求書をクラウド環境にアップして、情報をBPOベンダーと共有したうえで、一部の作業をBPOベンダーにしてもらうのです。
もちろん紙を送付することでも受領した請求書のBPOを進めることは可能ですが、使い勝手の良いクラウド型の会計システム等があるのであれば、それらを活用してBPOを進めることでより生産性を高められる可能性があるのです。
どこまで何をしてもらうのか
それでは、受領した請求書のBPOに関して、発注する企業側としては何をしてもらえるのか、あるいは何をしてもらうと効率的なのでしょうか。
実務上は、主に以下のような業務をBPOしているケースが多いです。
| No | 委託業務 | BPOする内容 |
|---|---|---|
| ① | データ入力 | 請求書に記載されている各種情報(日付、金額、取引先、内容等)を 入力してもらう |
| ② | 内容確認 | 企業側でデータの一次入力をしているケースでは、 入力内容の確認をしてもらう |
| ③ | 計上伝票起票 | 請求書に基づいて計上の伝票を起票してもらう 【仕訳例】(借方)仕入や経費 ×××(貸方)買掛金や未払金 ××× |
| ④ | 支払データ作成 | インターネットバンキングで支払うためのデータを作成してもらう |
| ⑤ | 支払伝票起票 | 取引先に支払った実績の伝票を起票して会計に反映してもらう 【仕訳例】(借方)買掛金や未払金 ×××(貸方)預金 ××× |
インボイス制度が導入されるとチェック項目は増える見込み

①のデータ入力に関して、最近はAI-OCRの機能が充実しているシステムもリリースされていて、それらのシステムを活用することで人間の手入力の工数は大幅に削減することが可能となっています。
②の内容確認がBPOをするメインの内容となっています。請求書の記載事項は、日付、金額、取引先のほかに、振込口座や消費税、源泉税といったように多岐にわたっています。仮にAI-OCR等で読み込みをしたとしても個別に内容を確認すべき事項が多いのが事実です。
たとえば、振込口座に関しては先方の都合で口座変更がなされているケースもあり、このような場合にはマスタを変更しなければ④で行う支払データが正しく生成されないことになります。
また、消費税に関しては8%や10%の区分は自動的に判別できても、会計帳簿を作成する段階では、8%のうち経過措置としての8%なのか軽減税率としての8%なのかを区別しなければなりません。
さらに、消費税の申告において個別対応方式を採用している企業の場合には、税率の区分以外に課税売上との対応関係も判別する必要があります。
2023年10月以降にインボイス制度が導入されると、適格請求書発行事業者か否かの判定等、追加での確認事項も想定されますので複雑さは増しそうです。
④の支払データに関しては、BPOベンダーにデータを作成してもらったうえで、企業側で送信手続きをとります。内部牽制をはかるためにもデータの作成まではBPOベンダーに行ってもらい、最後の送信は企業側で行うことで不正の抑止にもつながります。
BPOしても社内決裁は重要業務
今回は受領した請求書のBPOについてお話をしてきましたが、企業側には重要な業務が残ります。それは、受領した請求書自体が支払ってよいものかどうかの決裁です。
BPOをすると届いた請求書の中身を確認することなく、BPOベンダーに渡してしまうということにもなりかねません。本当に発注した内容のものが請求されているのか、請求額が正しいのかといったことは、発注した企業の担当者等でないと判断ができません。
コスト意識をもって業務にあたるという点からも、BPOをした後も、決裁についてはおざなりにならないようにしましょう。
※掲載している情報は記事更新時点のものです。
※本サイトは、法律的またはその他のアドバイスの提供を目的としたものではありません。当社は本サイトの記載内容(テンプレートを含む)の正確性、妥当性の確保に努めておりますが、ご利用にあたっては、個別の事情を適宜専門家にご相談いただくなど、ご自身の判断でご利用ください。