
令和4年(2022年)の電子帳簿保存法の改正が公表されて以来、
- ・電子取引情報は電子で保存しなければいけなくなった。これは大変だ!
・法人だけでなく個人事業主も対象になるらしい。
・いやそれは2年間延長されたようだよ?
・その延長期間もまた延長されるのでは?
・どうも延長の延長ではなく、要件がすこし緩和されたようだ。
といった声があちこちで聞かれます。どちらかというと細かい改正が相次いでいるため、経理職の方でも詳細まで正確に把握されている方は少ないかもしれません。
ここでは、電子保存義務の内容とその対象を説明します。さらに、令和4年以降の宥恕(緩和)規定の状況を説明し、令和6年(2024年)から実際にどのような規制になりそうなのかを見ていきたいと思います。
目次
電子保存義務とは?
電子帳簿保存法が令和4年(2022年)1月1日に改正・施行され、いわゆる「電子保存義務」が制定されました。
これまでは、PDFなどの電子データで請求書や領収書を受け取っても、それを印刷して紙面で保存しておけば大丈夫でした。しかしそれが認められなくなり、電子データで受け取ったものは原則として電子データのまま保存しなければならないことになりました。
もっとも、電子帳簿保存法においては、電子取引に関しては電子データで保存するのが原則であって、「印刷して紙面で保存」することは例外的に認めていた状態でした。その例外を取り外して元来の法の趣旨に沿った形になったのですが、社会への周知が十分であったとは言えませんでした。
結果として、2021年の年末に宥恕措置が公表され、電子保存義務の適用は実質的に2年間延長されることになりました。
なお、電子帳簿保存法で規定されているいわゆる「スキャナ保存」や「会計帳簿等の電子保存」は上記の電子保存義務とは別のものになります。これらは引き続き任意適用のままで、義務付けられたわけではありません。
電子保存義務の対象者は?
電子帳簿保存法の対象者は幅広く、法人税と所得税の保存義務者が対象になっています。したがって、株式会社等の法人のほか、個人事業主も対象になります。
事業規模の大小は関係なく、一人で事業を営んでいるような文字通りの個人事業主も対象になりますので、電子保存義務化の影響はかなり大きいといえるでしょう。
なお、法人の場合、その決算期に関わりなく1月1日から適用開始となりますので留意が必要です。期の途中からでも対応が必要になります。
電子取引とは?
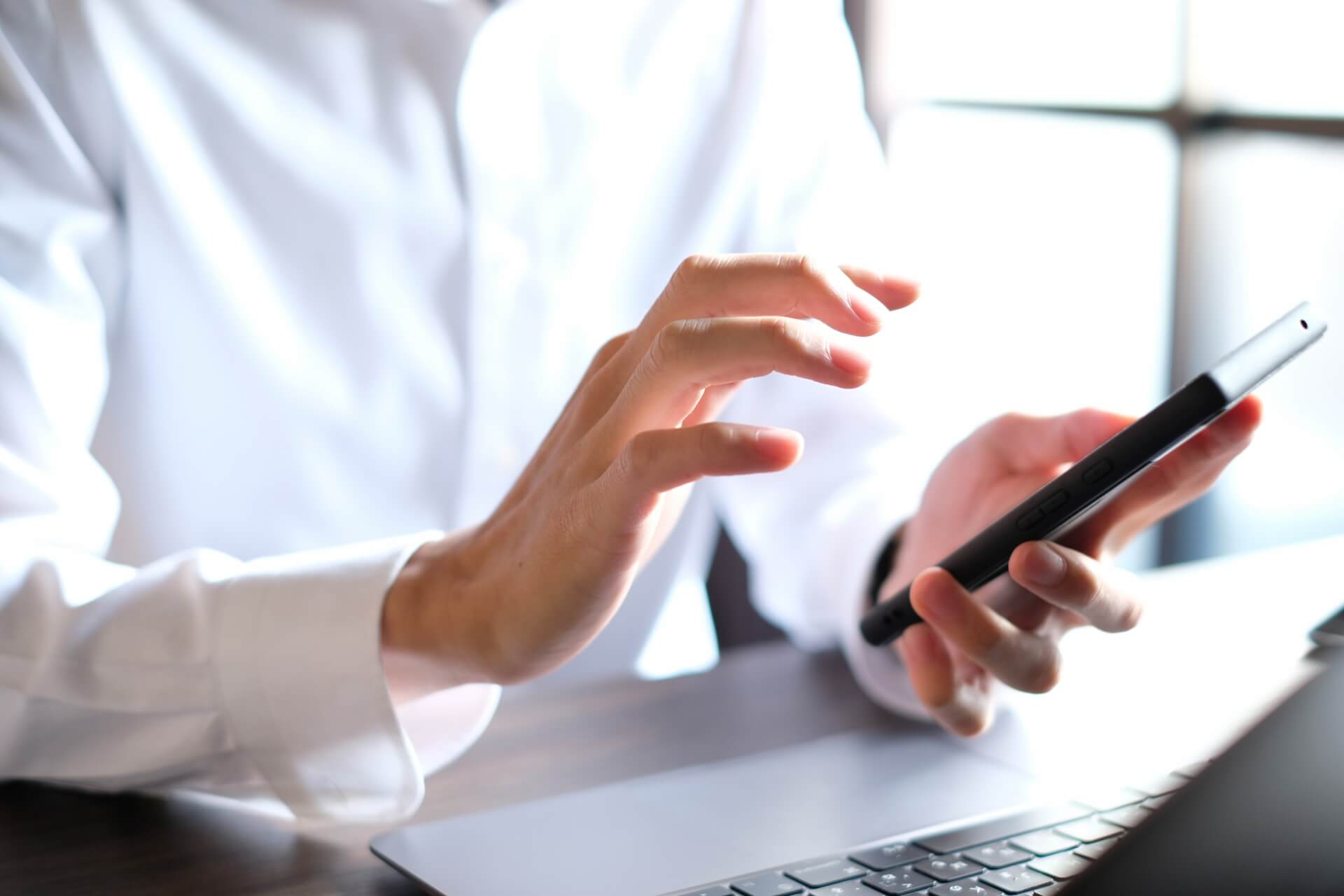
電子保存義務の対象になる電子取引とは、どのようなものが含まれるのでしょうか。国税庁が公表しているQ&Aでは、次のように説明されています。
電子取引とは、取引情報の授受を電磁的方式により行う取引をいいます。
ここで「取引情報」とは、取引に関して受領し、又は交付する注文書、契約書、送り状、領収書、見積書その他これらに準ずる書類に通常記載される事項をいいます。
具体的には、いわゆるEDI取引、インターネット等による取引、電子メールにより取引情報を授受する取引(添付ファイルによる場合を含みます。)、インターネット上にサイトを設け、当該サイトを通じて取引情報を授受する取引等をいいます。
一般的な例でいえば、取引先と電子メールで見積書や請求書のPDFファイルをやり取りした場合や、Amazonや楽天といったインターネット通販サイトで商品を購入した場合にそのサイト上に掲載される注文情報や領収書などが該当することになります。
会社の場合は、たとえば従業員が会社の経費を立て替えたときに、その従業員が支払先から領収書を電子データで受領した場合も、会社としての電子取引に該当します。
電子保存義務の宥恕期間および緩和措置の内容
電子保存義務については、令和3年(2021年)以降、実質的な2年間の延長措置(宥恕期間)や保存方法などの要件の緩和措置が公表されています。
ここでは、その内容を見ていきます。
(1) 令和3年度(2021年)税制改正
①電子保存義務化
令和4年(2022年)1月1日より、電子取引情報の保存に関する例外的な容認規定(印刷して紙面保存可)が削除され、電子保存が義務付けられることになりました。
原則として、「検索要件などを満たした方法により電子データで保存しなければならない」ことと定められました。
②保存方法の要件の緩和
一方で、保存要件の緩和が行われました。たとえば、売上高1,000万円以下の事業者が、税務調査時にダウンロードの求めに応じる場合は、検索要件を不要とする、といった内容です。
(2) 令和4年度(2022年)税制改正
①令和5年(2023年)12月31日までの宥恕措置
上記の改正が施行間際になったものの、要件を満たすためのシステム改訂や社内体制整備が間に合っていないという経済界からの要望に配慮し、電子取引情報を紙面に印刷して保存することを2年間(令和5年12月31日まで)に限り容認することとされました。
具体的には、納税地等の所轄税務署長がやむを得ない事情があると認め、かつ、その保存義務者が税務調査等の際にその電子データの出力書面(整然とした形式及び明瞭な状態で出力されたものに限る。)の提示又は提出の求めに応じることができるようにしている場合には、その保存要件にかかわらず、その電子データの保存ができることとされました。
②令和6年(2024年1月1日以降の保存方法の要件)
この時点では、令和6年以降の保存方法の要件についてはとくに変更はありません。
(3) 令和5年度(2023年)税制改正(予定)
①令和5年(2023年)12月31日までの宥恕措置
こちらの内容は変わっていません。
②令和6年(2024年)1月1日以降の保存方法の要件
今回の税制改正では、こちらの保存方法の要件が緩和されました。
イ 税務調査時にダウンロードの求めに応じる場合は検索要件を不要とする措置の対象者が拡大されました。
- ・売上高5,000万円以下の事業者(令和3年税制改正時は売上高1,000万円以下)
・税務調査等の際に、その電子データの出力書面を(一定の要件のもとに整理されたものに限る)提出することができるようにしている事業者
ロ また、保存要件に従って保存できなかったことについて①税務署長が「相当な理由」があると認め、②検査時にデータダウンロードおよび出力に対応できることを条件に、保存要件を満たさない状態で電子保存することを認めています。
令和5年度の税制改正法案は国会で審議されており、3月中には可決成立し、4月1日に施行される見込みとなっています。確定後にはあらためて本シリーズの中で詳細をお伝えさせていただく予定です。
まとめ
ここでは、電子保存義務に関する電帳法の規制内容やその影響を見てきました。令和6年1月からの規制内容は概ね見えてきていますので、それまでに対応方法を検討し対応しておく必要があるといえるでしょう。
※掲載している情報は記事更新時点のものです。
※本サイトは、法律的またはその他のアドバイスの提供を目的としたものではありません。当社は本サイトの記載内容(テンプレートを含む)の正確性、妥当性の確保に努めておりますが、ご利用にあたっては、個別の事情を適宜専門家にご相談いただくなど、ご自身の判断でご利用ください。