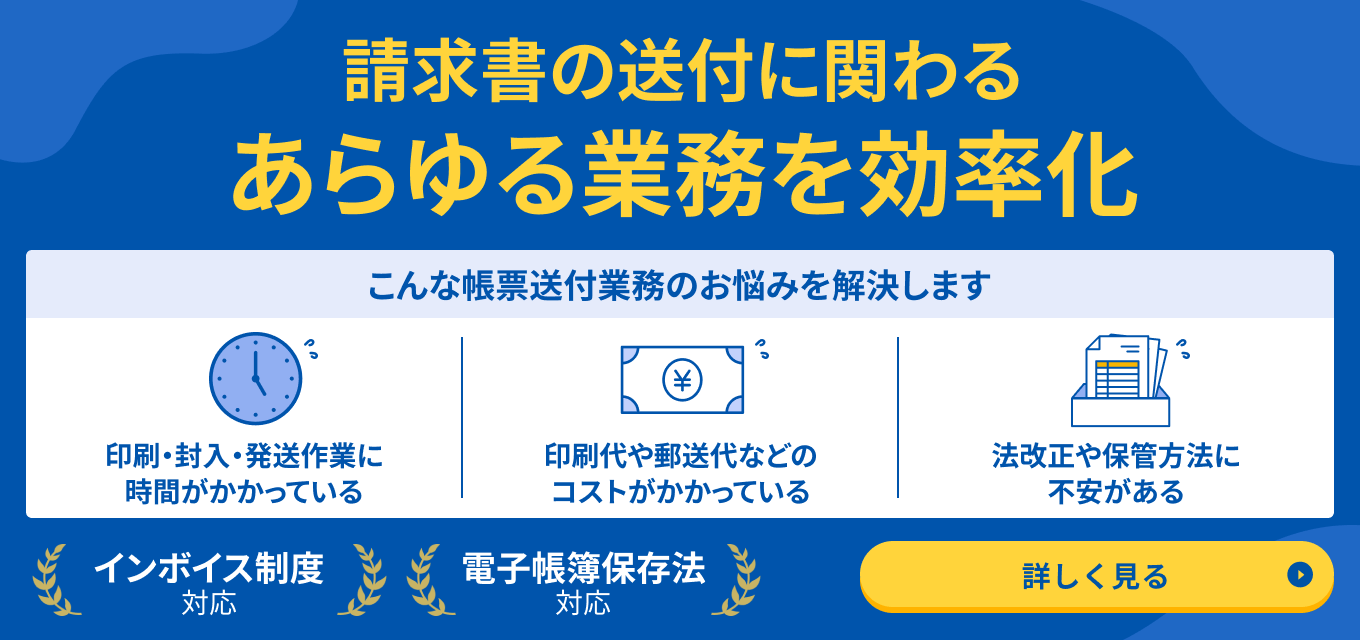前回のBPO(ビジネス・プロセス・アウトソーシング)ベンダーを選定する時の留意点パート1準備編では、業務のスタイルをどうするか、業務フローの変更を可能にするかどうか、取引ボリューム等を事前に把握しておくといったことについてお話しました。
今回は、パート2の業務範囲編として、どのような業務をBPOしていくことが多いのか、他社での取組みなどをお伝えしたいと思います。
コア業務は会社に残すという視点
BPO(ビジネス・プロセス・アウトソーシング)をするきっかけの一つに、経理部門のメンバーがより付加価値の高い業務に集中できるようにさせたいということがあります。
経営陣は経理部門に対して、数字作りよりも作られた数字をもとにして、将来の意思決定に有益な提案等をしてもらうことを期待しています。
このような期待をされている部門ですので、経理業務のうち会社に残して極めていくべきコア業務と、単純作業、繰り返し作業、付加価値が決して高くない作業といったノンコア業務に区分して、ノンコア業務をBPOしていく観点を持つことが重要になってきます。
現に、ノンコア業務に区分されるものを抽出してBPOをしている会社が多くあります。
ノンコア業務を抽出する
ノンコア業務として抽出される業務としては、次のような業務が多いです。
- 入力業務:単純入力業務でかつては依頼が多かった業務の一つです。ただ、最近はクラウドシステムの提供ベンダーが、人間が入力しないで済むように銀行取引のAPI連携機能、スキャンデータをデータ化するAI-OCR機能等を充実させているので、この手の入力業務はそもそも減る傾向にあります。
- 経費精算業務:従業員の経費精算業務は単純かつ繰り返しが多い業務なので、会社にとってはノンコア業務という区分です。最近はクラウドシステムの提供ベンダーの経費精算システムがかなり普及してきて、証憑等の共有もクラウド上でできるので、BPOベンダーが経費精算システムにアクセスして内容のチェックを行うといった業務のスタイルが増えてきています。
- 判断を要しない業務:上記以外にも支払業務、決算業務等のうち、判断を要しない業務、例えば支払いデータの作成や作成された支払いデータの内容チェック等はBPOをしているケースがあります。
成長のためには必要なコストはかけるという視点

もうひとつのパターンとしては、企業の成長速度が速くてバックオフィスの業務が追い付かずにBPOを推し進めているパターンがあります。
新しいビジネスを定期的に起こしていて、その都度会社を設立しているケースや、企業買収を盛んに行っている会社などがこれに該当します。
新しい会社ごとに経理業務は必要な機能として人材を配置しなければならないのですが、バックオフィスの人材供給が追い付かずに、BPOを進める流れです。
このようなケースの場合は、コストよりも業務範囲を広くお願いできるかどうかという点に重きを置いていることが多いです。
成長して本業で儲けることができるので、かかるコストはかけてでもビジネスを推し進めたいというのが本音だからでしょう。
幅広く依頼をする場合は、業務範囲を明確に
コストが少々かかっても人を採用するよりもBPOをするという選択肢をとる会社の場合は、委託する業務範囲がより広くなる傾向が強いです。
もちろん判断業務までは依頼しないにしても、決算業務などはかなりの部分を依頼するというケースもあります。
決算業務は作業が多い上、期限がタイトなことが多いので、ある程度の部分をBPOすることでタイトな日程の中でも経理部門のメンバーが時間的に余裕を持てるようにするために、幅広く業務を委託するのです。
このような場合に、気を付ける点は、委託する業務範囲を発注時に明確にしておくべきということです。
例えば、決算業務を委託するとなった場合でも、どこまでをBPOするのかを契約等で明確にしておく必要があります。
【決算業務の業務区分(例)】
| 業務内容 | 会社が引き続き実施する事項 | BPOベンダーに委託する事項 |
|---|---|---|
| BS,PL,内訳書作成 | - | ○ |
| BS,PL内訳書の内容確認 | ○ | - |
| 税効果計算 | - | ○ |
| 税効果回収可能性判断 | ○ | - |
決算書の作成や確認といった事項のほか、税効果計算であれば計算をするのが誰で、回収可能性を判断するのが誰なのかといったことを決めておく必要があります。
いざ決算を締める段階になって、作業分担が明確でないために作業漏れが生じるといったことになってしまっては本末転倒なので、業務開始前にその点はきちんと決めておくのです。
システムの選定も事前に決定
そして、業務範囲を決めるのに合わせて、どのようなシステムを使って業務を行うのかということは業務スタート前に決めておくべき事項の一つです。委託する会社と情報を共有するために同じシステムを使うのかどうかということもこの段階で決めておく必要があります。
最近の傾向として、スタートの段階で共有を図るためにクラウド型のシステムに切り替えるケースも増えてきています。コストメリットを享受できるのと、BPOベンダーとの情報共有が平易にできるというのが主な切り替えの理由と考えられます。
今回は、経理のBPOを実際に進めている会社がどのような視点で委託業務を決めているのか、具体的にどのような業務があるのか、決める際の留意点についてお話をしました。今後、経理業務のBPOを進めようと考えている方の役に立てれば幸いです。
※掲載している情報は記事更新時点のものです。
※本サイトは、法律的またはその他のアドバイスの提供を目的としたものではありません。当社は本サイトの記載内容(テンプレートを含む)の正確性、妥当性の確保に努めておりますが、ご利用にあたっては、個別の事情を適宜専門家にご相談いただくなど、ご自身の判断でご利用ください。