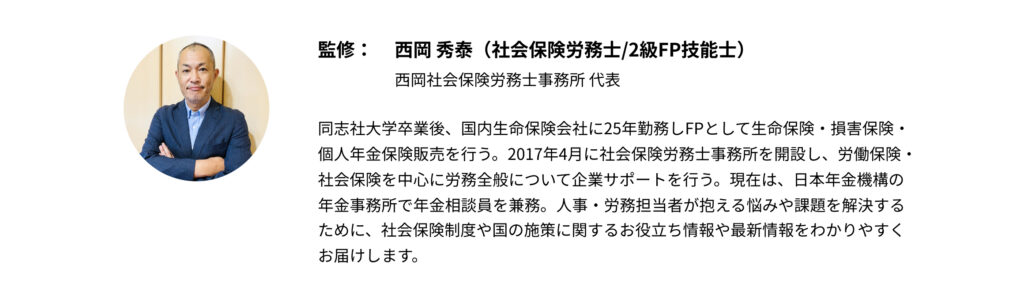台風時の自宅待機命令、どう判断する?
作成日:2025年2月20日
台風接近時に従業員の安全を守るために自宅待機命令を出すケースもありますが、判断に迷う企業も多いでしょう。ここでは、自宅待機命令を出すときの判断基準や法律上の取扱い、実際の企業の対応例について解説します。
自宅待機命令を出す際の具体的な判断基準
(1)気象情報の確認方法
自宅待機が必要かどうかを判断するため、最新の台風情報を把握しましょう。気象情報の主な確認方法は以下のとおりです。
また、鉄道会社の計画運休にも注意しなくてはなりません。運休などにより、通勤が困難になるケースも考えられるためです。近年の自然災害の激甚化や頻発化を踏まえ、鉄道などの計画運休が一般化しています。
- 気象庁ホームページ
- 国土交通省防災情報提供センターの携帯電話用サイト
- 民間気象会社の情報提供サービス
- 都道府県や市町村の情報提供サービス など
(2)従業員の安全確保の優先順位
企業には従業員の生命と安全を守る義務があります。台風の通過が確実で、大きなリスクが想定される場合、仕事よりも従業員の安全確保を優先しなければなりません。
具体的には、台風の進路や強度、影響範囲を考慮し、通勤時の危険性や職場での安全性について検討します。必要に応じて、事前に自宅待機命令を出すことで、従業員の安全を確保することが重要です。また、従業員への迅速な情報提供や、緊急時の連絡体制を整備することで、安心して対応できる環境を整えることが求められます。
(3)業務の重要度と緊急度
従業員の安全確保が原則ですが、医療や介護の従事者などは人命にかかわる業務のため出社が必要なケースも考えられます。自治体の防災担当者や消防署の職員なども同様です。
一般企業においても、従業員の出社や早退、自宅待機を判断する部署では出社せざるを得ないケースもあります。業務の重要度と緊急度によって、個別に判断することが重要です。各職場や部署の状況に応じて、柔軟な対応を心掛け、従業員の安全と業務の継続を両立させるための適切な判断を行いましょう。
自宅待機命令についての法的な視点
企業には、従業員の生命や安全を守る法律上の義務があります。自宅待機命令に関する企業の義務や休業・給与の取扱いなどを、法的な視点で解説します。

労働基準法に基づく自宅待機命令の適法性
労働基準法では、会社都合による休業に対する休業手当の支払いが義務づけられています。会社都合とは企業に責任のある休業のことで、台風の場合は対象外です。つまり、「ノーワーク・ノーペイの原則」に従って無給でも法律上の問題はありません。ただし、従業員の責任ではないため、有給や特別休暇を付与するなどの対応が望ましいでしょう。

休業日が無給になったときの労働者の権利
自宅待機命令による休業が無給の場合、労働者は有給休暇を取得できます。また、自宅待機命令が出て休業したにもかかわらず、台風が逸れて勤務ができる状態であった場合、会社都合による休業として休業手当を請求できる可能性もあります。

安全確保と業務継続のバランス
労働契約法では、企業に従業員への安全配慮義務を課しています。しかし出社しなければ、会社が大きな損失を被るケースなども考えられます。従業員の安全確保を優先しつつ、業務の継続に必要な最低限の人員に限定して出社指示を行うなど、安全確保と業務継続のバランスが重要です。

自宅待機命令に関する法的リスクと対策
自宅待機命令を出したが、実際には安全に勤務できた場合、休業手当を請求される可能性があります。自宅待機時の勤怠や給与の取扱いを就業規則に定め、規則に従って対応しましょう。一方、出社を命じてケガをした場合、安全配慮義務違反を問われるリスクがあります。出社する人数を必要最低限にする、在宅で緊急対応できる体制をつくるなど、リスクの低減に努めましょう。
判断基準の例
自宅待機命令を出すかどうかの判断基準は、企業によって異なります。夜中に台風が接近して早朝から台風による危険が想定される場合、以下のような企業対応が考えられます。
業務内容や雇用形態などによって企業の対応は異なりますが、事前に判断基準や対応方法を決めておくことが重要です。
□ 従業員の安全を最優先して、原則全従業員に自宅待機命令を出す
□ 台風による危険性や業務の緊急性などを従業員に判断させ、出社するか自宅待機するかを決めさせる
□ 業務の継続に必要な一定の役職者や特定部署の従業員のみを出勤させる など
判断基準の明文化と社内周知の方法
自宅待機命令を出すときの判断基準に法律上の定めはなく、従業員の生命と安全を守ることを前提に企業が決めます。想定されるリスクに応じた対応方法や判断のタイミング、判断材料、判断する部署などを決定します。
いつ発生するかわからない自然災害に対し、事前に判断基準を決めておき、災害対策マニュアルなどで明文化しておきましょう。自宅待機時の勤怠の取扱いや給与の有無などは、就業規則へ記載します。マニュアルや就業規則を従業員がいつでも見られるようにして周知するとともに、災害発生時には電子メールを活用するなど、迅速で正確な連絡方法を決めておきましょう。