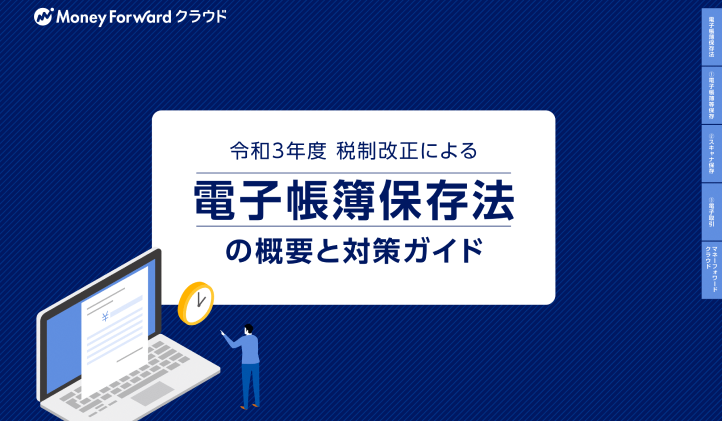中小企業の経費精算システムの選び方・比較すべき項目
更新日:2025年6月25日
中小企業における経費精算業務のよくある課題
申請から支払いまでのサイクルが長い

中小企業では、限られた要員で効率的に業務を進めることが求められます。経費精算は業務のために従業員が立て替えた費用の払い戻しが中心になりますが、その経費の内容が適切であるかどうかを確認する必要があります。
これら確認処理に時間をかけたくないものの、実際には紙での運用や経費システムであってもデスクトップPCだけでの運用であることが多く、申請から支払までのサイクルが長いことが課題として挙げられるでしょう。
経費データの一元管理ができない
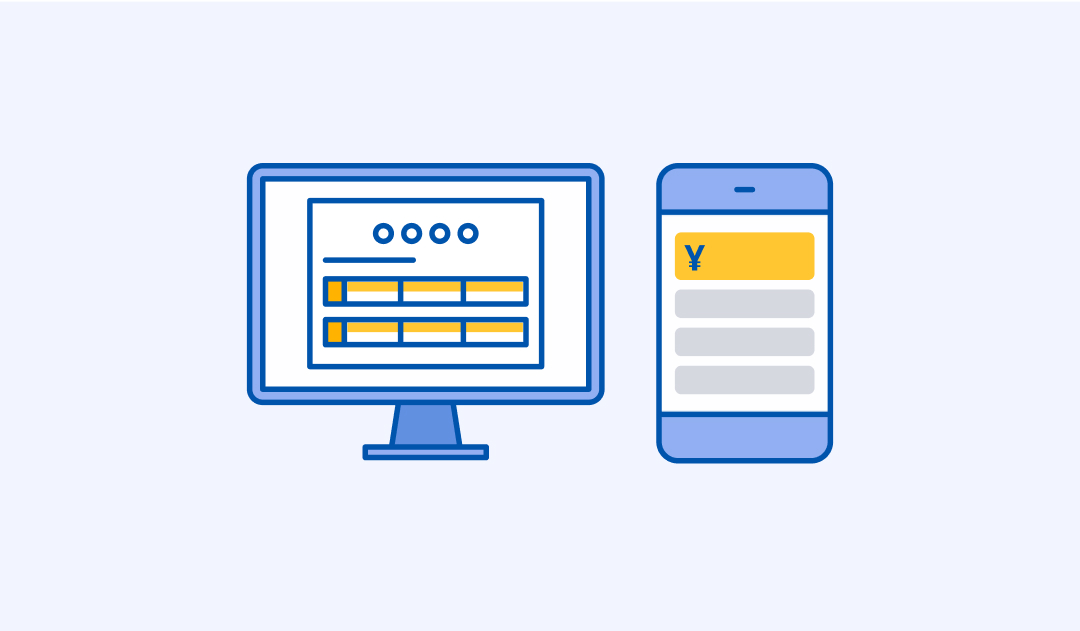
一般に中小企業においては、経営計画に基づいた購買の頻度に比べると経費精算のほうがはるかに多いと言えます。実際、経費精算の対象となる経費科目は多岐にわたり、よく利用される旅費交通費や接待交際費から、場合によっては車両費や修繕費、水道光熱費など多くの科目があります。
これらのデータを一元管理できていないと、必要な情報をすぐに見つけることができず、業務の効率が上がりません。
現場からの抵抗の声がある

経費精算システムは、社内のほとんどの人が利用するシステムです。中小企業の場合、IT教育に十分な時間をかけることができないため、ITリテラシーが高くない従業員の存在も考えられます。その場合、新たに導入されたシステムに対する操作への抵抗感が大きく、操作教育に時間と労力がかかることもあるのです。
紙の運用であれば後で補記するなどの柔軟性があったことから、システムは柔軟性に欠けると感じる人もいるでしょう。
経費精算システムの料金形態や費用感が不明

中小企業においては、新たな出費を考える場合、費用対効果は特に重要視されるポイントです。会計システムは導入したものの、経費精算システムの必要性を感じつつも、料金形態などがよく分からず先に進まないこともあります。
オンプレミス型システムとは異なり、初期費用がかからないクラウド型システムを導入する場合、自社でどの程度の費用がかかり、効果はどのような形で現れるのかが不明であると現状維持になることもあるでしょう。
中小企業向けの経費精算システムの料金形態・費用目安
経費精算システムのコストは一般的に、ユーザ数に応じて利用月額が決まるものが多いと言えます。中小企業といっても規模・業種等により従業員数に差があり、精算する経費の発生頻度は企業によりまちまちです。ここでは目安として、50名以下の利用者を中小企業と考えてみます。
利用料金の単価は、導入するシステムにより異なりますが200~500円(1ユーザの月額)程度になります。月あたり、単価×ユーザ数がコストとなります。
一般的にユーザとは、いつでもそのシステムが使えるように登録されているユーザのことであり、基本的には従業員のほとんどが対象となるでしょう。価格帯に幅があるのは利用できる機能の数が多いほど料金が高くなるためであり、自社に必要な機能が明確であると絞り込みやすいと言えます。
システムによっては会計システムに付帯して経費精算機能がついてくることもあり、単独導入できないものもあるため、仕様をよく確認しましょう。また、単独で導入の場合、利用する会計システムとの連携が可能なことを確かめることが大切です。
その他の課金方法には、利用する機能数によって料金が変動するものや、経費精算件数に応じて料金が変動するものなどがあります。
なお、中小企業において経費精算システムを選択する前に次の点に着目しましょう。
- 使いやすいこと
- 必要な機能を備えていること
- サポートが充実していること
コストだけを決め手にしないことも大切です。
中小企業が経費精算ソフトを導入する時にあると便利な機能
給与と連携する機能

経費精算には多くのパターンが想定され、精算方法が複雑なものもあります。一方、従業員としては、できるだけ早く精算してもらいたいところでしょう。
中小企業において効率化という点から見れば、従業員への給与のタイミングに合わせて経費精算を済ますことで振り込み処理1回分が合理化できます。経費精算システムに会計システムだけでなく、給与システムとも連携できる機能があれば大変便利だと言えます。
カスタマイズできるワークフロー機能

経費精算では内容や金額によって、承認ルートが異なることがあります。中小企業においては役職兼務などもよくあるため、固定的なワークフローでは対応できないこともあるでしょう。
そこで、経費申請においてワークフローを自由にカスタマイズできるソフトだと便利です。さらに承認過程において、申請者への問い合わせができるようにチャット機能などがついていれば、それぞれの申請ごとに素早く内容を確認できます。
アクティブなユーザのみの課金機能

中小企業で経費精算システムを利用する可能性のある人は全ての役員と従業員ですが、実際に経費精算システムを利用する人は限られてきます。働き方によっては1年に1度ぐらいしか利用しない人もいるでしょう。
そこで、アクティブユーザ、つまり、経費精算システムを使った人数分だけの課金機能であれば無駄がありません。休日の多い月などには経費を節約できるため、実際の利用者にのみ課金する機能は要チェックです。
中小企業が経費精算システムを比較する際のポイント
いつでもアクセスできるクラウド型であること
クラウド型の経費申請システムは、いつでもデータにアクセスができます。利用時間の制約がないクラウド型システムであることは、新システム導入の基本的な要件となり得るでしょう。
基本的にクラウドシステムのユーザーは、パソコンを閉じてもサーバーは立ち上がっているため、サーバーの管理についての詳細を知る必要はありません。人材不足となりがちな中小企業においてはサーバー管理者も不要で、発生するのはランニングコストだけです。
どこからでもアクセスできる機能があること
システムによっては、デスクトップPCのみに対応で十分なものもありますが、中小企業の経費精算システムではデスクトップPC以外からのアクセスを考えるべきでしょう。自分のアカウントを入れると、どこからでも申請や承認が可能であることで効率化がグッとアップします。
また、IOSにもアンドロイドにも対応したスマホアプリによって、パソコン同等の操作ができると外出中でもリモートワークでも経費申請が滞ることがなくなります。
現場からの抵抗をなくすサポートがあること
中小企業においては、紙の運用を残しつつ経費精算システムを導入することも考えられます。現場での事務手続きを急激に変更するのではなく、並行期間を設けてシステムを受け入れる基礎を築くようなイメージです。
そのため、利用ガイドやメールなど、サポート体制が確立したシステムを利用することをおすすめします。経費精算システムにおいて、最も上流にいるのは経費を支払う申請者ですので、申請者が実際に使えるようになるためのサポートは欠かせません。
電子帳簿保存法に対応していること
中小企業においても、今後の書類保管を考える上で電子帳簿保存法への対応は必須です。令和6年からは電子取引における電子データの保存が義務付けられましたが、今後はスキャナ保存も合わせたデータの保管について考えておくほうがよいでしょう。
経費申請システムを導入する際には、電子帳簿保存法に対応しているものを選択しておくのが安心です。導入の目安として、「電帳法スキャナ保存ソフト法的要件認証制度」における認証製品一覧の中から選ぶとよいでしょう。
中小企業に参考となる経費精算業務の改善事例

株式会社オカフーズ様の事例
乗り換え後は経費精算の仕訳データが自動作成されて会計に連携できるようになったので、毎月のデータ移行作業がなくなりました。驚いたのは社員たちの反応でした。
「マネーフォワード クラウド経費」の社内説明会を開き、アプリで領収書が読み取れることや、交通系ICカードのデータが取り込めるデモを見せたところ、「おー!」「すごい便利」と驚きの声があがりました。
株式会社文響社様の事例
以前は経費精算に、外部のシステムではなく自社でGoogle Appsを使って申請を行う方法をとっていました。紙の領収証を添付して申請をする必要があり、紙は紛失しやすいというデメリットがありますから、現場からは管理が面倒という声が上がっていました。経理側としても、提出された紙の領収証を会社で1件ずつチェックする必要がありました。
株式会社ワーク・ライフバランス様の事例
課題は経費の件数が多いことでした。外出がとにかく多く、交通費はもちろん、打ち合わせの合間にカフェに入って作業します。その際にカフェ代やランチ代の補助等で経費申請します。国内出張も多く、オフィスに出社できるのは月に5日程度、という事がよくあるので月の経費精算の数は非常に多いです。
株式会社ソルテラス様の事例
導入以前は、経費のレシートが多すぎて「社長、これって何に使いましたか?」「それは誰かの私物だったんじゃない?」というやりとりが頻出し、チェックが大変でした。
記帳ミスがあったり、手作業でレシートを見ながら入力したりと、最低でも1日2時間は経理業務に使っていました。
中小企業に役立つ経費精算業務の効率化に関する参考資料
中小企業がバックオフィス業務のDXを進めるべき理由
中小企業白書(2021)によると、コロナ禍以降、テレワークやテレビ会議といったツールを導入する企業が増加し、国内における中小企業のデジタル化への意識変化がみられました。事業方針におけるデジタル化の優先順位に関するアンケート結果では、感染症流行前に「優先度は高い」と答えた企業が15.9%だったのに対し、2021年時点では20.9%と5.0%アップという結果です。「優先順位はやや高い」と答えた企業も含めると、40.3%から62.5%に増加しました。
出典:中小企業庁「第2節 中小企業におけるデジタル化とデータ利活用」
また、日本では少子高齢化に伴って、生産年齢人口(15~64歳)が減少傾向にあります。2021年時点では7,450万人いた生産年齢人口は、2050年には29.2%減の5,275万人にまで落ち込むと予想されています。各企業でデジタル化推進による生産性向上が急務となっているものの、中小企業においては予算やリソースの制約によってデジタル化が進まないことが課題の1つです。
(出典:厚生労働省「デジタル化推進の手引き<基礎編>」/https://www.mhlw.go.jp/content/001093499.pdf)
生産性向上に向けたデジタル化を推進していくにあたって、経費精算システムを導入する中小企業が増えています。経費精算システムを導入すれば、経費申請にかかる時間の短縮や経理業務の効率化が可能です。ほかにも、経費精算システムの導入は、経費申請における不備・不正の防止や、電子帳簿保存法にも対応できるといったメリットがあります。