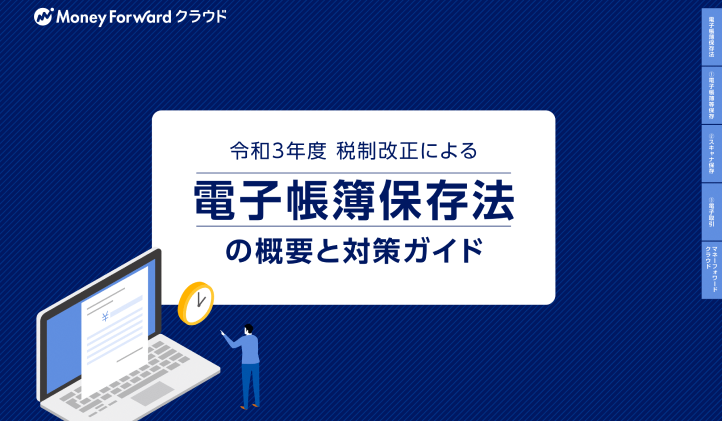大企業の経費精算システムの選び方・比較すべき項目
更新日:2025年6月25日
大企業における経費精算業務のよくある課題
承認プロセスの長期化

大企業における経費精算の承認プロセスは、事業規模の拡大や複雑な組織構造によって長期化しがちです。多段階での承認手続きをルール化する企業が多く、全国各地に拠点を展開している場合には、本社や各拠点間でのやりとりが必要なケースもあるため、承認作業が遅延する原因となりかねません。
このような状況に陥ることで経費申請の差し戻しも頻発し、従業員のモチベーション低下や業務効率の悪化を引き起こす可能性が高まります。
規則の一貫性と透明性の確保
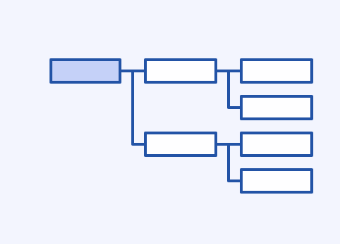
大企業における経費精算のルールについては、部署や地域によって異なる場合があり、経費の適用範囲や精算基準の混乱を招くことがあります。
一貫性のない運用方法では、従業員が経費精算を行う際の不確実性を高め、申請ミスの増加や不公平感の増大につながる事例も多いです。
また経費精算ルールの一貫性や透明性が損なわれることで、承認プロセスが形骸化し、組織全体のコスト管理が機能不全に陥ってしまうリスクも高まるでしょう。
紙ベースからの脱却

大企業においては歴史ある会社が多く、長い年月をかけて社内インフラが構築されているケースがほとんどです。
そのような企業では、基幹システムや業務プロセスが確立されている一方で、新システムの導入やフローの再構築にはまとまったコストや労力が伴うため、社内改革が思うように進まない事例も多いです。
特に紙媒体での業務体制からの脱却に課題を抱える大企業は多く、経費精算業務でも非効率な業務体制に陥りやすくなります。
経費データの分析と活用

経費精算業務によって生成される経費データに関しては、さまざまな角度から分析を行うことで、経営戦略の策定や業務改善の基盤となり得る貴重な情報です。しかしたくさんの従業員を抱える大企業では、膨大な量の経費データが生成される一方で、これらを効果的に管理・分析し、予算計画やコスト削減案の策定に活用することは容易ではありません。
特に経費データを一元管理できていない場合には、データの有効活用が困難になります。
大企業向けの経費精算システムの料金形態・費用目安
大企業が経費精算システムを導入する場合には、料金形態や導入コストの観点から比較検討を行うケースが大半です。経費精算システムでは、一般的に「オンプレミス型」と「クラウド型」の2つに分けられ、料金体系も異なります。
「オンプレミス型」の場合には、初期費用が高額になるケースが多く、大企業では数百万円単位となる場合も珍しくありません。ランニングコストとしては、月々の利用料は発生しないものの、自社で管理を行う場合には、システムに精通した人材の確保が必要となります。
「クラウド型」の場合、初期費用は比較的抑えやすく、数十万円程度のものや、中には無料のサービスも存在します。ランニングコストとしては、ユーザー数に応じて料金が変動する「従量課金制」が採用されているケースが多く、一般的には1ユーザーあたり数百円での利用が可能です。
大企業が経費精算システムを導入した場合の費用目安としては、「オンプレミス型」の場合、カスタマイズ料金も含めた初期費用として、数百万円に達する事例も多いです。
「クラウド型」の場合、初期費用は抑えやすいものの、従業員数の増加に比例して毎月のランニングコストが増えやすく、ユーザー数が500名であれば、ひと月あたり20〜50万円程度が目安となるでしょう。また、追加機能の選択によってはオプション料金が発生することもあるため、自社の運用方法を踏まえたうえで、導入コストを比較検討してください。
大企業が経費精算ソフトを導入する時にあると便利な機能
基幹システムとの連携

会計や給与計算ソフトなど、大企業ではすでにさまざまな基幹システムを運用しているケースがほとんどです。
新たな経費精算システムを導入する場合には、他の基幹システムとの連携機能のあるサービスを選択することで、シームレスなシステム間連携を実現できます。
たとえば会計システムとの連携機能があれば、仕訳入力業務の自動化に加え、経費データをリアルタイムで反映できるため、財務状況をスムーズに把握することが可能です。
モバイルアプリの活用

多数の従業員を抱える大企業では、従業員による外出や出張の機会も増えがちです。
特に営業社員については残業時間中に経費申請を行うなど、非効率な労働環境に陥るケースも少なくありません。
モバイルアプリで使用できる経費精算システムを利用することで、外出中のスキマ時間を活用して経費申請できるため、業務の効率化が期待できます。さらに承認者も外出先から手続きできるため、スムーズな承認プロセスを実現できるでしょう。
クレカや法人カードの明細取得

大企業では、経費精算業務の負担を抑えるために、クレジットカードや法人カードを活用し、従業員による経費の立て替えを削減する会社が多いです。
従業員が使用するクレジットカードや法人カードの利用明細を経費精算ソフトに連携できれば、経費データの精度向上や自動化につながり、迅速な経営判断に役立つでしょう。
またカードの利用状況をリアルタイムで把握できるため、不正利用防止やコンプライアンスの強化にも効果的です。
大企業が経費精算システムを選ぶ際のポイント
承認フローの柔軟な設定
大企業が経費精算システムを導入する場合には、経費精算業務の長期化を解消し、業務効率化を追求する必要があります。そのためには、柔軟な承認フローの設定が可能なシステムを導入することが効果的です。
たとえば高額な経費申請の場合には多段階での承認フローを設定し、少額の申請の場合には上長のみのチェックとするなど、申請内容に応じて精算プロセスを柔軟に設計できれば、内部統制と業務効率化の理想的なバランスを追求できます。
また申請内容に応じた承認フローを設定することで、従業員のコスト意識の醸成にも役立つでしょう。
経費精算ルールの統一適用
大企業が経費精算システムを導入する際は、社内の精算ルールを明確化し、それらをシステム上で反映することが大切です。
一貫性のあるルールに基づき、組織全体で同じシステムを利用することで、申請時の混乱を回避でき、経費申請の正確性も高まります。また経理担当者や承認者も、明確なルールに照らし合わせて確認作業を行えるため、業務負担の軽減にもつながるでしょう。
精算ルールを統一した場合には、経費精算システム内で「出張申請」などの汎用的なワークフローを設定することで、使用頻度の高い経費申請をさらに効率化できます。
ペーパーレス化への移行
大企業における経費精算のペーパーレス化は、業務効率を追求するうえで必要不可欠です。特に従業員数が多い企業では、紙での経費精算が経理部門の大きな負担となるため、経費精算システムの導入時には、ペーパーレス化を実現できる機能を備えたサービスを選定しましょう。
具体的には、領収書のスキャン機能やクレカ・ICカードとの連携機能により、入力の自動化や経費のデータ化を実現でき、従業員と経理担当者の負担を軽減できます。
さらにペーパーレス化により、拠点間でも経費データを共有できるため、円滑な業務遂行を実現できます。
経費の分析機能
経費精算システムを導入する場合には、経費精算プロセスを効率化するだけでなく、組織内部に蓄積された経費データを分析し、企業としての内部統制の強化やさまざまな経営判断に活用することが重要です。
各従業員や部門、費目、経費利用額の推移など、さまざまな角度から経費データを分析することで、経費の傾向を的確に把握し、プロジェクトの見直しやコスト削減の機会を探ることが可能です。
またシステムを通じてリアルタイムでの経費追跡や分析を実施することで、予算管理の精度向上にもつながり、経営基盤の構築にも貢献するでしょう。
大企業の企業様に参考となる経費精算業務の改善事例
株式会社グロービス様の事例
当社では10年程前から、経費精算と債務支払にクラウドシステムを利用していましたが、10年前から変わらぬ機能やUIに対しての不満が上がっている状況でした。業務改善のため、年1回従業員アンケートを実施しているのですが、システムに関しては「古くて使いづらい」「領収書の原本を送る作業が面倒」など、改善を希望する多く声が上がっていたのです。
ミス・パリ・グループ様の事例
マネーフォワード クラウド経費を導入してからは、経路を入力するだけで定期代を控除した交通費が自動計算されるため、申請者・経理双方の負担が軽くなりました。また、これを機に運用を見直し、毎週現金手渡しから月2回の振込へ変えよりスリムになったと思います。
生活協同組合コープさっぽろ様の事例
導入を決めた当初は、紙での経費申請をなくすことに反対意見もありました。そこで、まずはシステム部と広報部で先行利用して社内での成功事例を作り、実効性の検証をしたうえで段階的に導入を進めていきました。
導入時のマネーフォワード社の支援はとても手厚かったです。正直、支援がなかったら安定したリリースはできなかったかもしれません。
詳しくはこちら
大企業の企業様に役立つ経費精算業務の効率化に関する参考資料
大企業がバックオフィス業務のDXを進めるべき理由
現在、日本では「少子高齢化に伴う生産年齢人口の減少」や「育児・介護との両立といった勤労者のニーズの多様化」といった状況に直面しています。こうした課題の解決に向けて、「働き方改革」を推進するための法律の見直し・整備が進められています。
1947年に制定された「労働基準法」には、残業時間の上限がありません。そのため、これまでは法定労働時間を超える過度な残業に対しては、行政指導のみの対応でした。労働基準法の改正後は、法律によって残業時間の上限を制定し、原則として月45時間・年360時間を超える残業ができなくなっています。
出典:厚生労働省「働き方改革~ 一億総活躍社会の実現に向けて ~」
大企業においては、既存の経費精算システムを使って手動入力しているところや、古い経費精算システムを何十年にわたって使用しているところも少なくありません。経費精算の業務のみに焦点を当てても、大きな負担となっている可能性が考えられます。
最新の経費精算システムを導入すれば、こうした非効率化している体制を整えて、無駄な業務を減らすことが可能です。つまり、残業時間の削減が期待でき、業務効率化はもちろん社員一人ひとりの働き方改革にもつながります。最近では、クラウド型の経費精算システムも主流となっており、テレワークやリモートワークといった多様な働き方にも対応可能です。