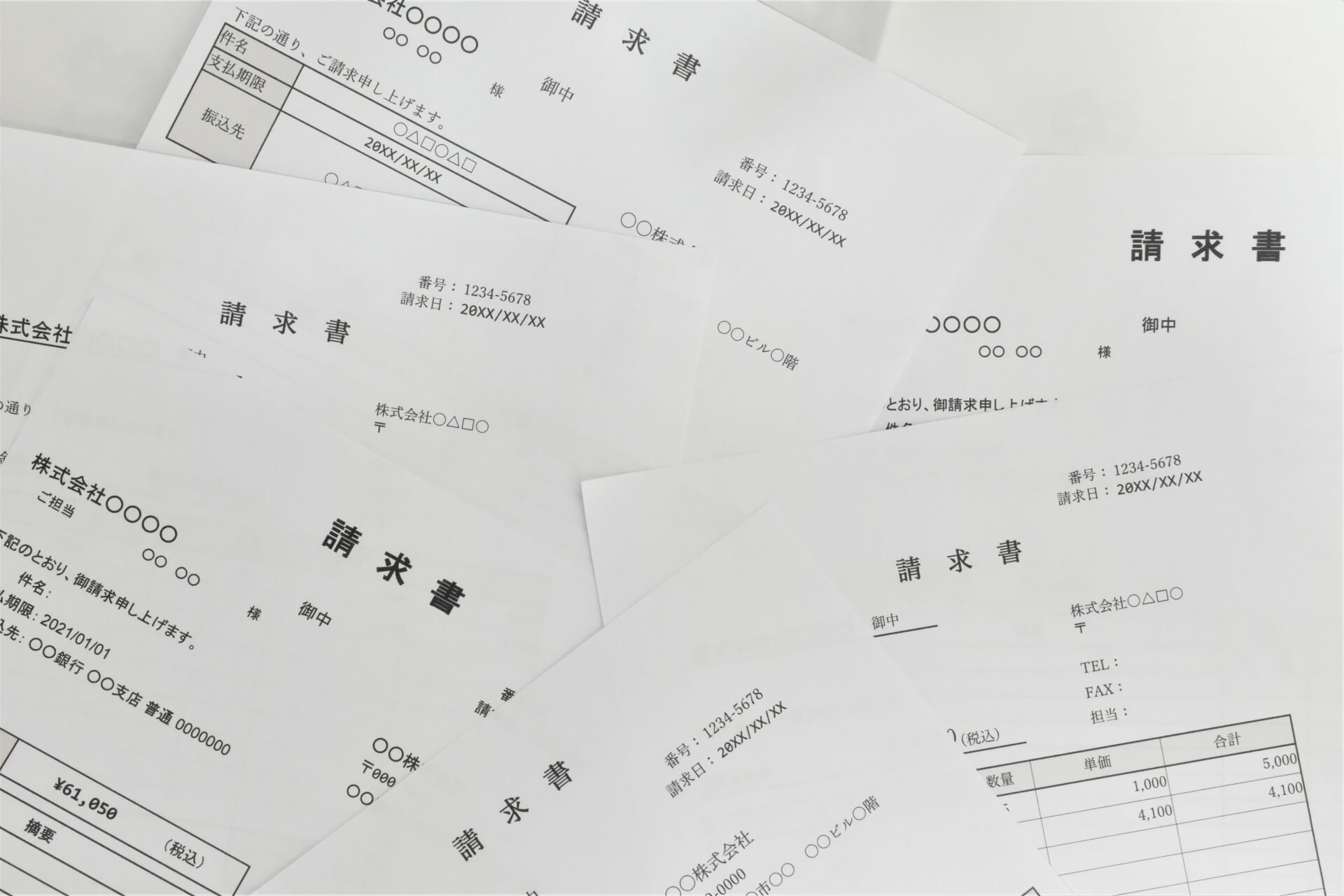
私は、数年前までとある企業で経理を担当していました。
経理というと、コツコツ入力していく穏やかな業務のイメージがあるかもしれません。しかし実際は、会社のお金を扱うだけにミスの許されない、大きなプレッシャーを伴う業務です。
気を付けてはいてもミスが起こってしまうことはあります。今回は、請求書紛失により支払い漏れとなってしまった事件を紹介します。
新入社員も真っ青!引き出しの奥で丸まった請求書…
私がいた部署では、取引先からの請求書は、営業部の担当社員宛に送られてくることになっていました。請求書を受け取った営業社員が内容を確認し、営業部長に承認をもらってから経理に回すという流れでした。
新入社員は、こうした請求書処理の流れも先輩社員からレクチャーされます。その事件は、当時の新入社員だったS君が、先輩から業務を引き継いでひとり立ちしてから3か月目、だいぶ慣れてきて誰もが安心していた頃に起こりました。
ある日、取引先の経理部から「先月分の入金が確認できていない」という連絡が入りました。慌てて担当のS君に確認を取りましたが、S君は「請求書は来ていなかったと思う」とのこと。
しかし、「届いていないようです」と連絡しようとしたその時、S君が「やっぱり受け取っていた気がする!」と言い出したのです。S君も私も真っ青になって、デスク周辺を探しました。
ところが、普段から外回りや会議で忙しくしているS君のデスクは、ものすごい書類の山。大事な物も不要な物も一緒になってひたすら積まれているような状況でした。
整理整頓も指導しなければ…と思いながら数人がかりで捜索すること数十分、引き出しの奥から無惨に丸まった請求書が発見されたのです。請求書は封筒に入ったまましわくちゃになっていて、開封された形跡もありませんでした。
S君はそれを見てハッと思い出したようで、「後でやらなきゃと思っていたら、そのまま忘れてしまいました…」とうなだれました。
顧客への対応やプレゼン準備などで毎日忙しくしていたS君は、請求書を受け取っていたことすらも忘れてしまったようです。さらに、慣れてきた頃だからと安心していた先輩社員が確認を怠ってしまったことも一つの原因でしょう。
この時はすぐに支払いを行い事なきを得ましたが、本当にヒヤッとした出来事でした。
電子化への移行が急務
この件を受けて再発防止策を考えましたが、「デスクを整理する」「きちんと確認する」など精神論に偏ってしまいがちだったので、もっと根本的な解決策が必要だと感じました。
そもそも、請求書が紙で来るということに問題があるのではないでしょうか。紙の状態だからこそ紛失のリスクが発生するので、最初から最後まで電子データで処理できれば解決できるはずです。
電子帳簿保存改正やペーパーレス化促進の流れもあり、まだアナログな経理を行っている企業には、電子化への移行が求められているといえるでしょう。
しかし、急にすべての取引先に請求書のデータ化をお願いするのも現実的ではありません。さらに、請求書データがメールで届いたとしても、誰がダウンロードしてどう処理を進めているかまでは経理で把握できないため、支払い漏れなどの事故を完全に防げるわけではないという問題が残ります。
BPOやクラウドサービスで本質的な解決を

そこで効果的なのが、BPOやクラウドサービスの導入です。たとえば次のようなサービスを活用すれば、ミスを防げるだけでなく業務効率を上げることもできるでしょう。
紙の請求書の受領代行
紙の請求書を受け取り、電子化までを代行してくれるサービスがあれば、紙の請求書を取り扱う必要がなくなります。そのため、紛失するリスクがなくなり、支払い漏れなどの事態に発展することも防げるでしょう。
営業担当者を経由せずに経理担当者が直接確認できるので、正確かつ迅速に処理を進められるというメリットもあります。
メールで受領した請求書データの自動保存
メールで受領した請求書に関しては、メールに添付されたPDFをダウンロードして自動保存してくれるサービスがあれば効果的です。
メールはチームの複数人宛に送信されることも多いため、誰が請求書の処理をしているのかわかりづらかったり、重複して処理してしまったりするケースもあり、効率的ではありません。
請求書データの自動保存サービスを活用すれば、処理漏れや重複処理も防げるため、業務の効率化につながるでしょう。
まとめ
S君の請求書紛失事件があってからというもの、しばらくの間は誰もが気を引き締めていましたが、しばらく経つとまたデスクに書類が山積みにされる光景が戻ってきて、確認も疎かになってきてしまいました…。
やはり、個人の努力に頼るだけでなく、根本的な解決が必要だと強く感じたことを覚えています。
問題を根本から解決できる画期的なシステムが次々と登場しているので、時代の流れに伴ってシステム導入の決断をしていくことが大切だと考えます。
定着するまでは少し大変かもしれませんが、長期的に見れば、会社全体にとって有益な選択であることは間違いないでしょう。
※掲載している情報は記事更新時点のものです。
※本サイトは、法律的またはその他のアドバイスの提供を目的としたものではありません。当社は本サイトの記載内容(テンプレートを含む)の正確性、妥当性の確保に努めておりますが、ご利用にあたっては、個別の事情を適宜専門家にご相談いただくなど、ご自身の判断でご利用ください。