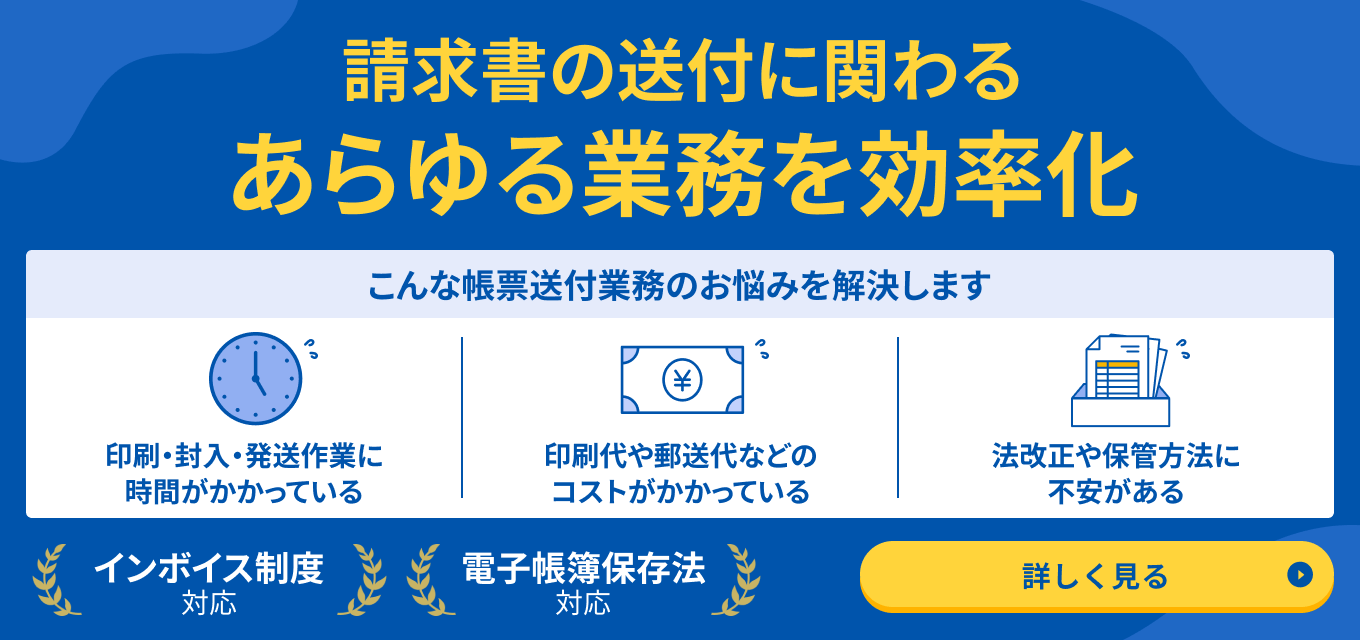経理業務のBPO(ビジネス・プロセス・アウトソーシング)を検討している会社が最近増えてきています。今回はサービスを提供してもらうBPOベンダーを選定するにあたって、留意しておくべき点についてまとめてみました。
ということで、今回はパート1の準備編として、まずは経理のBPOを検討し始めた段階で準備すべき点について見ていきましょう。
次回のパート2では、業務範囲編ということで、BPOをして社外に出す業務と社内に残す業務の選別について見ていきます。
そもそも何のための経理のBPOなのか
BPOするときに重要なのは、何を目的として経理業務をアウトソーシングするのかということです。
考えるきっかけとして多く聞くことは、
「経理部員が退職することになり、業務を継続させるために必要」
「上層部からコストダウンをするように言われた」
「事業の拡大ペースが速くて、間接部門の業務が回っていない」
「もっと付加価値の高い業務を経理部門で行ってほしい、といわれる」
「親会社からの要求水準が高いが、子会社での業務レベルが追い付かない」
といったことです。
これらのことがきっかけとなりBPOの検討を始める会社が多いように思いますが、BPOの目的が何かをきちんと決めておくことがまずはスタート時点としては重要です。
「退職等に左右されず業務を安定させる」
「コスト削減をはかる」
「ルーティーン業務を外部に出して時間を生み出す」
「一定程度品質の高いサービスをうけて経理レベルを維持・向上させる」
といったことが目的になるケースが多いようです。
大切なのはここで決めた目的に沿ってBPOベンダーを探すという視点です。
コスト削減が第一命題であれば、海外のオフショア等に拠点があるベンダーの方が、目的を達成できる可能性が高くなるでしょうし、品質に重きを置くのであれば、一定のスキルを持ったベンダーやチェック体制がしっかりしている組織のほうが、品質レベルが高いことが想定されます。
業務遂行のスタイルはオンサイトかオフサイトか
次に、業務遂行のスタイルをどのようにしたいのかということで選ぶベンダーも異なってきます。
会社に来てもらって机を準備して作業をしてもらう、いわゆるオンサイトが一つのスタイルです。
オンサイトの良さは、そばにいるので指示を気軽に出せることかと思いますが、最近のように在宅勤務が多くなってくるとBPOベンダーだけオンサイトで作業をしてもらうと遂行しにくい面も出てきます。
もうひとつのスタイルはオフサイトで業務を遂行する方法で、基本的にBPOベンダーは現地に赴かずにBPOベンダーの拠点から遠隔で作業を進めるスタイルです。
クラウド型の経理システムを入れている場合は、遠隔での作業もスムーズに行うことができますので、オフサイトで進めるにあたってはクラウド型のシステムを導入する検討も重要な肝となります。
実際、クラウド型の経費精算ソフトを導入することで、経費精算業務をBPOしている会社も増えてきています。
また、最近では、BPOベンダーが在宅勤務で業務を進めているケースも増えてきています。
ただ、扱う情報が経理情報ということで機密性が高いこと、上場企業の情報を扱う場合はインサイダー情報に該当するということもあり、執務する場所でのセキュリティ体制を確認することも重要です。
例えば、自宅等で印刷が可能な状態で業務を進めているとなると機密情報が漏洩するリスクは高くなります。そのような体制となっていないかどうかについて確認することも重要です。
業務フローの変更への許容度はどうか

業務遂行のスタイルのイメージが決まった後に考えておくべき点として、外部委託する場合に現状の業務フローから変更となることに許容があるかどうかという点です。
どうしても今までのやり方を踏襲してもらわなければならないのか、あるいはこの際業務フローを変更してもよいのかどうかです。
発注する側として、できるだけ現状の仕事のやり方を変えないで外部に委託したほうが、負担がないと考えるケースが一般的には多いです。
BPOベンダーには、現状の業務フローを尊重してくれて、大きな変更がないまま仕事を受けてくれる会社もあれば、逆に、基本的にBPOベンダーが決めたやり方でしか受けないという会社もあります。
そのあたりの柔軟性についても、BPOベンダーとの面談時の確認事項としてリストアップしておくことをお勧めします。
ただ、業務フローに関しては、現在のやり方が効率的であれば変えないまま進めることが望ましいと思いますが、非効率な面もあるかもしれません。
BPOするのであれば、ある程度標準化した流れにしていかないと発注ができないことも考えられますので、BPOするのを機会に業務フローを見直してみるという視点も必要です。
ボリュームや工数を事前に把握しておくと話がスムーズ
このほか、事前準備として行っておくとよいこととして、BPOをしようと考えている業務のボリューム感を定量化しておくことがあげられます。
通常BPOベンダーがヒアリングをする際は、委託する予定の業務ボリューム等を確認します。これは、料金の設定がボリューム等に応じて変動するようになっているケースが多いので、それを把握するために確認が行われるのです。
正しい見積や業務の受託の可否等を判断してもらうためにも、事前に委託する業務の取引件数や作業時間等を計測しておくことをお勧めします。
今回は、経理のBPOを検討し始めて、BPOベンダーを選定する際に留意すべき点、準備しておくべきポイントについてお話をしました。今後、経理業務のBPOを進めようと考えている方の役に立てれば幸いです。
※掲載している情報は記事更新時点のものです。
※本サイトは、法律的またはその他のアドバイスの提供を目的としたものではありません。当社は本サイトの記載内容(テンプレートを含む)の正確性、妥当性の確保に努めておりますが、ご利用にあたっては、個別の事情を適宜専門家にご相談いただくなど、ご自身の判断でご利用ください。