給与計算ソフトの導入スケジュールと知っておきたい3つのポイント
作成日:2024年6月4日
新たな給与計算ソフトの導入は、業務効率化と正確性の向上に影響を与える重要なプロジェクトと位置付けられていることかと思います。そのため、導入にあたっては慎重な計画立案と正確な実行が求められます。しかし、頻繁には発生しない業務のため、運用開始までのイメージがつきづらい方も多いのではないでしょうか。
そこで、本記事では導入に至るまでの全体の流れと、特に知っておきたい3つのポイントに焦点を当てて紹介します。
一般的な導入スケジュール
給与計算ソフトの導入プロセスは、製品選定から始まります。ここではさまざまなソフトウェアを比較検討し、自社に最適なものを選びます。次にシステム化計画を立て、要件定義、設計を行い、ソフトウェアを自社の規則や運用に合わせて設定します。そのあと従業員データの移行が続き、並行稼働を経て、最終的に給与計算データを新システムに移行し、運用を開始します。この一連のプロセスは並行稼働期間なども合わせると約6〜8ヶ月程度(※導入するソフトの種類や従業員規模、データ量によって異なる)かかるのが一般的です。

特に知っておきたい3つのポイント
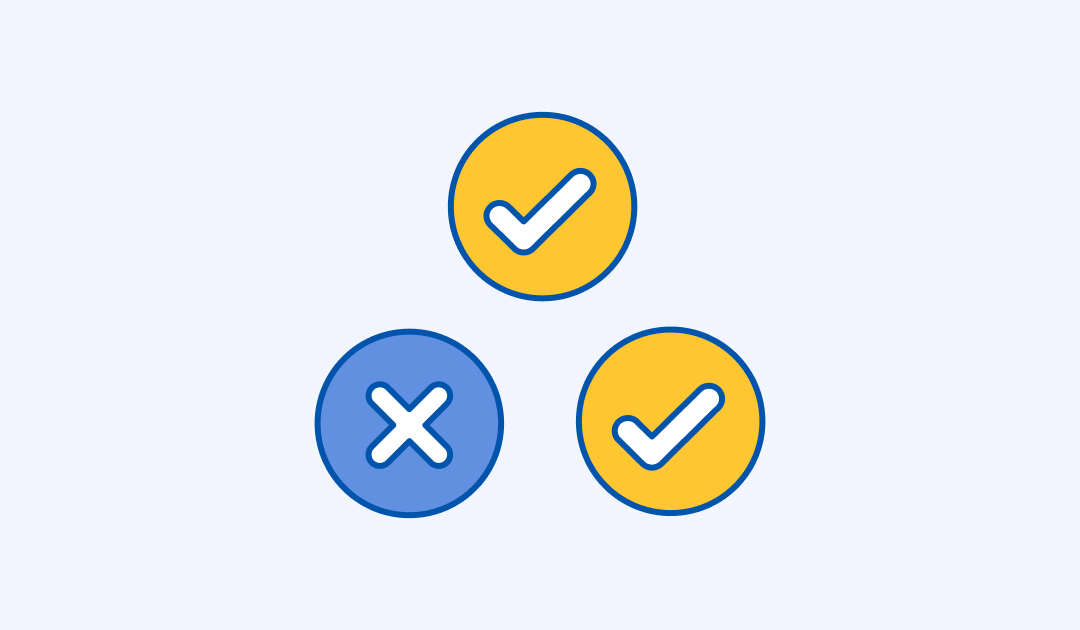
製品選定の際のチェック項目は適切か?
【費用・料金体系】
初期費用や月額料金などの導入コストだけでなく、将来的な従業員の増加や利用機能の拡張なども見すえたうえで、5年程度の期間のトータルコストをシミュレーションしておきましょう。コストだけでなく機能面やサポート体制を含む品質面とのバランスを見て判断することが重要です。
【既存のシステムとの連携】
すでに利用している勤怠管理ソフトや経費精算ソフトがある場合、乗り換え予定の給与計算ソフトがそれらと連携できる製品かどうかは重要です。連携方式(API連携・CSVファイルの取り込みなど)を確認し、運用方法や作業工数を把握しておきましょう。場合によっては新しい給与計算ソフトに合わせて周辺ソフトも乗り換えたほうが、メリットが大きいケースもあります。
【業務に必要な機能】
自社要件をすべて満たす給与計算ソフトを見つけるのは難しいものです。比較検討の際は「必要な機能」と「製品の標準機能」を一覧化し、不足している機能があればソフトに合わせて業務の運用方法を変更したり、要件の重要度を再検討したりする必要もあるでしょう。 このフィット&ギャップ分析により、自社の要件に各社サービスがどの程度対応しているのかの把握がしやすくなります。
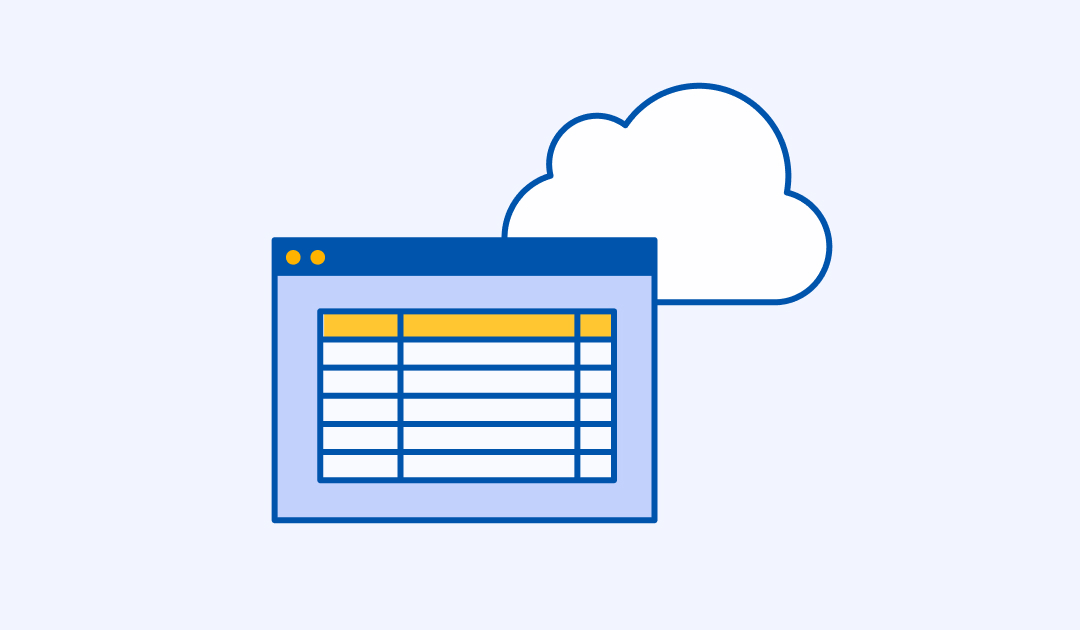
従業員・給与計算データの移行
ソフトの移行の際、従業員情報の登録後に過去給与データの移行をするケースが一般的です。具体的には、現行利用サービスから出力したExcelまたはCSVデータを新たなソフトに登録する、といった対応になります。サポートが必要な場合は、その内容に応じて料金が変動するケースが多いのであらかじめ確認をしておくことをおすすめします。
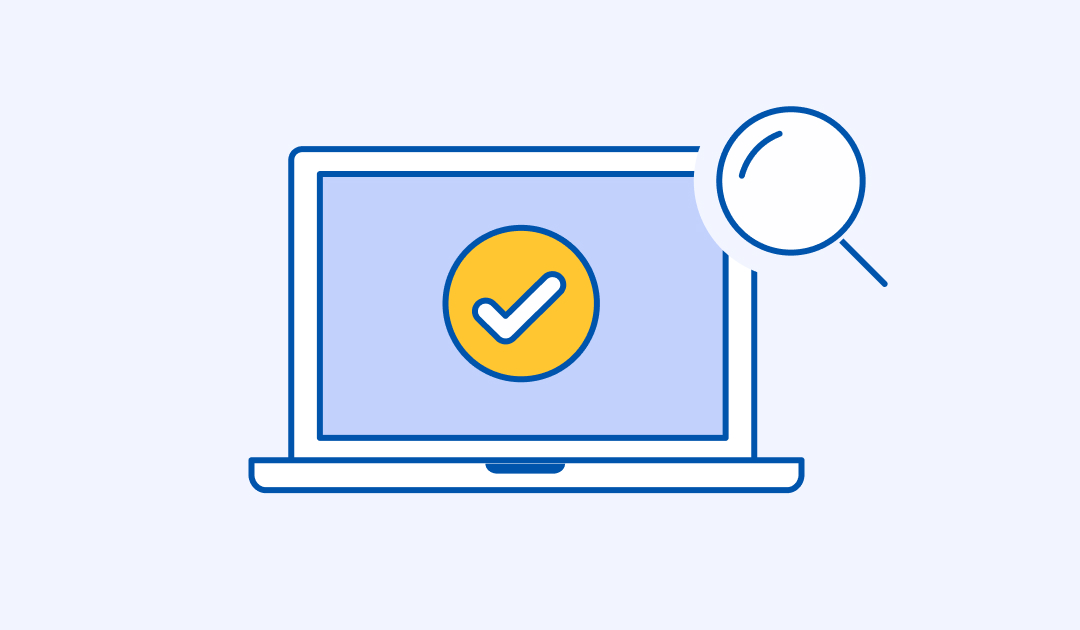
検証・並行稼働
新旧システムの並行稼働は、本格運用後に想定外のミス発生などのリスクを軽減するのに非常に有効です。この期間中、両システムで給与計算を実施し、新たなシステムでの給与計算結果と現システムの結果を突合して金額を一致させます。また、本格稼働後の業務の流れをつかむことも重要な目的です。例えば残業代や雇用保険料の端数計算が合わない場合、新たなシステムの計算ロジックに合わせるのか等を決定することになります。計算式を活用した際の計算ロジックの検証、計算結果が一致しているか確認、計算が間違っていた場合の修正などを行います。