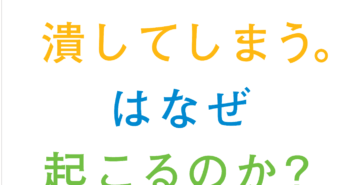テーマはすばり、「デキる上司がデキる部下を潰してしまう。はなぜ起こるのか?~経理編~」です。
人材育成は、言うまでもなく重要なテーマです。特に近年は採用の難易度が上がっていることもあり、その注目度が増しているのではないでしょうか。
なかでもハイ・パフォーマーとも呼ばれる、いわゆる「デキる」人をどう活かすか、さらにはその人たちの「心を折らない」で、自社で活躍し続けてもらうことも、企業の業績に直結するテーマです。
前田さんの最新刊『デキる上司がデキる部下を潰してしまう。はなぜ起こるのか?』(クロスメディア・パブリッシング社刊)の特別版として、経理やバックオフィスをご担当のみなさまにお届けします。
目次
デキる人は、自分自身の人生の後悔はないけれど…
読者の皆さんは、今の職場を選択し、そして経理という仕事を選択して今にいたるわけですが、これまでの人生の選択、そしてキャリアを振り返って、後悔していることはあるでしょうか。
ひょっとしたら「本当はアイドルになるはずだった」「もともとはプロアスリートを目指していた」という人もいるかもしれませんし、今の職場や職種が第一志望ではなかった人もいるかもしれません。
ただ、それが「後悔」かというと、多少意味合いは違ってくると思います。後悔というのは「どうして経理の仕事なんて選んでしまったのだろう」「どうしてこんな会社に入ってしまったのだろう」「どうしてこんな人生になってしまったのだろう、悔やんでも悔やみきれない」ということだと思います。
少なくとも、今このコラムを読んでいる方たちは、そこまで後悔している人は、私はいないのではないかと思います。
なぜなら、このようなコラムをメールマガジンで取得したり、ウェブサイトで閲覧したりする習慣を持っているような前向きな人たちは、自分の人生を、たとえどんな過去があっても最終的には良い方向に持っていくように努力している人たちだからです。
他者から見たら「あの出来事は挫折や失敗だったのでは?」ということも、「あの失敗も人生の勉強になりました」「あの挫折があったから今の自分があります」と言えるように強い信念で生きてきています。だから、失敗や挫折ではあってもそれは後悔ではないということです。
しかし、そのような強い信念を持った人たちであっても、「後悔している」こともあります。それは「かつて、部下を潰してしまったことがある」という後悔です。
私がこの点に着目したのは、「黒字だけれど、飛躍的には伸びきれていない」という、伸びそうで伸びないことを課題に抱えている複数の会社をコンサルティングした時です。
どの会社も一時期は既存の社員に加え、若手社員や中途入社の社員が台頭し、会社全体の売上や利益が伸び「良かったですね」と安心していたところ、その飛躍の原動力となっていた若手社員や中途社員が心身の不調で休職・離職をし、数字も元に戻ってしまっている、ということが起きていました。
経理の皆さんなら、この構造がお分かりになることでしょう。会社の数字は「人」に紐づいていますから、数字を持っている人が辞めてしまったら、そのまま会社の数字は減ってしまうのです。
その現象を防ぐことはできないかと、休職や離職をした人たちの職場環境の詳細を調査したところ、いわゆる「仕事がデキる上司の下」というポジションに位置し、実力を発揮し始めた社員が心身の不調をきたして休職・離職していることが多かったことがわかりました。ただ、上司によるパワーハラスメントやモラルハラスメントなどの行為は確認できませんでした。
では、何が原因で彼らは休職・離職してしまったのでしょうか。これを解明できれば、デキる部下が離脱することなく順調に成長してデキる上司となり、今度は彼らがデキる上司となってデキる部下を育成していく、というサイクルが可能となり、会社の数字も飛躍的に伸びるはずです。
AIが経理業務に参画する時代になり、「処理」の面では負担が軽減されていくなか、新たな役割を経理部門も求められていく時代になると思います。
このような、経理の視点から自社の組織や人材を分析し、より売上・利益を伸ばすためには、あるいは下げさせないためにはどのような施策をすればよいか、という提案もこれからの経理部門、経理社員ができる仕事の一つではないかと思います。
今回の連載では、「デキる上司とデキる部下」の関係性にフォーカスします。デキる上司の下で、デキる部下が伸び伸びと活躍できるにはどのような環境が必要か、また経理部門や経理社員として、どのようなことが現実に貢献できるかを紐解いていきたいと思います。
「一通りデキている部下」と「まだ一通りデキていない部下」
ここで「デキる部下」の定義ですが、「与えられている業務を一人で自発的に行動し完結できている部下」と定義します。そしてそうでない人を「デキていない部下」とします。まだ一通り自分一人では業務が遂行できていない、あるいは上司のサポートやフォローがないと、まだミスなども発生する、といった部下です。
経理業務においては、この「デキる部下」と「デキていない部下」は、真逆の行動をとっていきます。
経理業務は一人でどんどん仕事を進めていける領域も多いので、デキる部下の場合、自分が与えられた仕事が早々に終わってしまうと、上司にも「ほかにやることありませんか」「これも私がやってしまっていいですか」「(上司の仕事を)私がやりましょうか」と、どんどん自分の学びやスキルアップのために積極的に習得しようとします。
その反対に「デキていない部下」の場合は、「そもそも現場社員が間違えた申請をしてくるから私も間違えてしまうんです」「私の仕事が終わらなかったら上司が手伝ってくれるのは当たり前です」など、他責に走る人もおり、なかなか独り立ちできません。
デキる部下がいると、デキる上司はつい期待し過ぎて「放任」してしまう

そのため、上司の立場からすると「デキる部下」の存在は非常に助かるので、つい期待して「全部判断も任せるから」と、頼ってしまいます。ここにデキる部下の心身が壊れてしまう危険がはらんでいます。
私が心身を壊してしまった経理社員の方たちの業務内容を確認させてもらうと、膨大な作業範囲をやっていることがほとんどでした。それも上司にやらされていたのではなく、自ら「やりますよ」「私がやらなければ」「ほかにやれる人もいなそうだから」と、業務範囲を広げていっているパターンがほとんどでした。
つまり、心身が健康なときはそれでもこなせるのですが、ひとたび心身が不調になったときに、一般的な社員であれば心身を整える時間がとれるところを、自ら過剰に仕事を引き受けてしまったおかげで休む時間がとれなくなってしまい、それも自ら志願した結果なので「自分の責任でこれだけ仕事を請け負ったのだから」と自責してしまい、何とか一人でやりきろうとしてしまいます。しかし作業量が膨大なので、結果的に心身を壊してしまうことになります。
一方、そのような状態の部下がいても、上司が常に部下を見守っていれば部下の異変に気付き、ケアすることができます。しかし、デキる上司は、デキる部下を過度に信頼し過ぎて「自分と同じ価値観だし責任感も強いから大丈夫だろう」と、放任のマネジメントをする傾向が高まります。
しかし、デキる上司とデキる部下には決定的な差があります。それは「耐性」です。耐性の多くは、経験値で培われます。上司と部下では経験値が違いますから、いくらデキる部下であっても、その耐性は上司ほどではないため、本人の耐性の限界を超えてしまった時点で、部下はダウンしてしまい、上司が気付いた時には後の祭り、ということが起こるのです。
このように「上司から部下への過度な期待」「部下の過度な業務量」「部下の過度な自責」などが「デキる上司とデキる部下」の組み合わせでは起きやすくなります。そのため、これらの要件が過度、過剰にならないようにする施策が大切です。
デキる部下にはルーチン業務よりもスポット業務を中心に依頼する
対策の一案としては、デキる部下から上司に対して「自分の仕事が終わってしまったので、何か仕事をやりますよ」と言われた際には、業務改善の依頼をするとよいと思います。
例えばアナログ作業をデジタル化できないか、煩雑な社内ルール・経理ルールを整理できないか、など、業務時間を短縮したり、効率化したりするための業務を遂行してもらうようにします。
そうすることで、デキる部下が動けば動くほど、経理全体、社内全体の業務負担は軽減され、それによってデキる部下自身の業務量も軽減されます。その際に、経理のクラウドのソフトウェアなども、経理処理のほかにどのように活用できるかも検討してもらうとよいでしょう。
デキる部下にはルーチン作業を多く任せてしまうと、優秀な分、膨大な業務量・業務範囲をこなせるようになってしまう一方で、部下が心身を壊したときに本人も会社もリスクが高まります。
デキる部下に余力があり、本人も何か新たに仕事をしたがっているときは、業務改善や新規案件など、スポット(単発)案件を中心に仕事を依頼すると、「潰れる、壊れる」リスクを避けることができ、デキる部下も意欲を持って取り組んでくれることでしょう。
※掲載している情報は記事更新時点のものです。
※本サイトは、法律的またはその他のアドバイスの提供を目的としたものではありません。当社は本サイトの記載内容(テンプレートを含む)の正確性、妥当性の確保に努めておりますが、ご利用にあたっては、個別の事情を適宜専門家にご相談いただくなど、ご自身の判断でご利用ください。