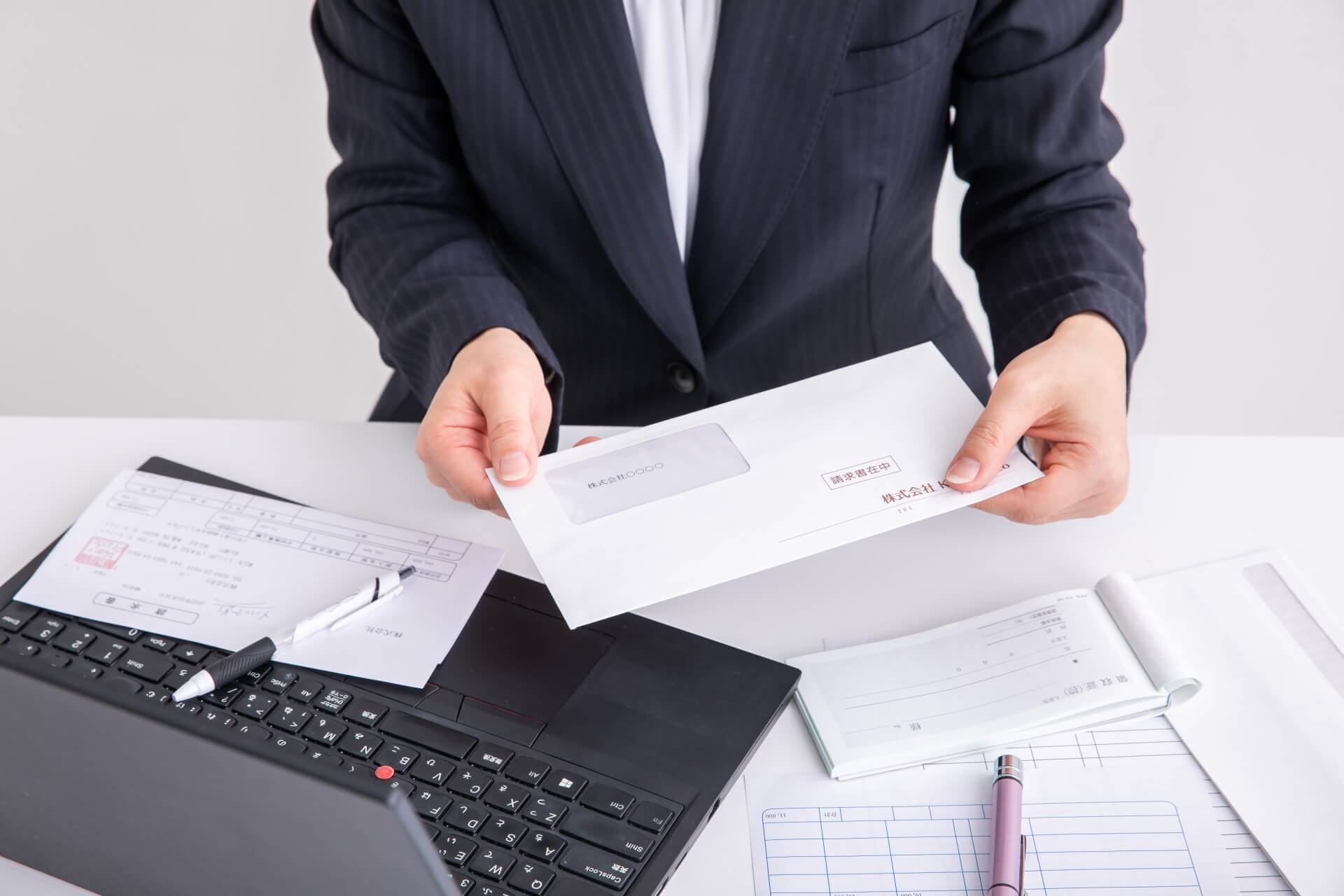
紙面で受領した請求書はどのように処理、保存されていますでしょうか?
紙面のまま支払プロセスに回され、そのまま保存されているケースもあるかと思います。税法上はもともと紙面で入手したものは紙面保存が原則なので、間違った方法ではありません。また、電子保存義務が課されるまでは、電子で入手した請求書なども印刷して紙面で保存することが許容されていました。
そのため、紙面で入手したものも電子で入手したものも両方とも紙面で保存することは、ある意味で「一元化された方法」として一般的に行われてきたと考えられます。
しかしながら、改正電帳法が施行され電子保存義務化が課される2024年(令和6年)1月1日からは、電子で入手した請求書等は印刷して紙面で保存することはできなくなります。
この規制に伴って、いままで電子で入手した請求書等を紙面で保存していた会社は、電子で保存するように変更せざるを得なくなっています。つまり、いままで「一元化された方法」で運用してきた会社は、少なくともその一部を変更しなければならない状況になっています。
従来の一般的な支払プロセス
さて、一般的な請求書の支払プロセスは、次のようになると考えられます。
・請求書は支払依頼書に添付されて経理部門に到着し、経理部門ではそれを保存する。
改正電帳法の施行前では、営業部門がPDFファイルで入手した請求書は印刷して支払依頼書に添付し、それを経理部門が保存することで問題ありませんでした。しかし、施行後は、このプロセスを変更する必要が生じます。
たとえば、請求書をPDFファイルなど電子で入手した場合は、支払依頼書をWordなどで電子的に作成し、請求書のPDFファイルとともに営業部門から経理部門にメールで送信し、経理部門は支払処理のうえでそれを保存する、という方法が考えられます。
対応方法①:スキャナ保存
電子保存義務への対応は、そのような電子的なプロセスを採用することで問題はなくなるかもしれません。
一方で、請求書を紙面で入手した場合のプロセスが変更されずそのままだとすると、電子で入手した場合は「電子的な支払プロセス」、紙面で入手した場合は従来の「紙面回付による支払プロセス」、と複数のプロセスが併存することになってしまいます。
このような場合にお勧めしたいのが、「スキャナ保存」です。スキャナ保存は、取引の相手方から受領した紙面の証憑を、スキャナ機器を使用して電子データに変換し、それを保存することをいいます(紙面は破棄します)。
スキャナ機器には、スキャン専用機や複合機のスキャナ機能を利用します。デジタルカメラやスマートフォンのカメラ機能も利用可能です。
紙面で入手した請求書などをスキャナで電子化することにより、紙面で入手した場合でも「電子的な支払プロセス」に統一することが可能になります。これにより、支払プロセスは大きく効率化されるはずです。
対応方法②:請求書受領BPOサービス
また、最近は「請求書受領BPOサービス」が登場しています。請求書の受領に関する様々な業務(受取、スキャン、会計ソフトへの入力、電帳法に対応した保存、など)を代行するサービスです。電帳法の改正に伴って導入を検討する会社も多くなっているようです。
また、請求書の電子管理や承認ワークフロー、振込指示などを一元管理できるシステムも存在します。
請求書の受領や管理に関わるシステム・サービスには様々なタイプやオプションがありますので、会社の業務内容や取引先の状況に応じて適切なシステム・サービスを選択することがポイントです。
まとめ
電子保存義務への対応について、支払プロセスの効率化の観点から考えてみました。電子で入手した証憑への対応ばかりでなく、紙面で入手した証憑への対応も併せて検討することが効率化につながります。
ここでは、電帳法の規定の一つである「スキャナ保存」の利用や「請求書受領BPOサービス」を紹介しました。スキャナ保存については電帳法で定める要件がありますので、別稿で取り上げたいと思います。
※掲載している情報は記事更新時点のものです。
※本サイトは、法律的またはその他のアドバイスの提供を目的としたものではありません。当社は本サイトの記載内容(テンプレートを含む)の正確性、妥当性の確保に努めておりますが、ご利用にあたっては、個別の事情を適宜専門家にご相談いただくなど、ご自身の判断でご利用ください。
