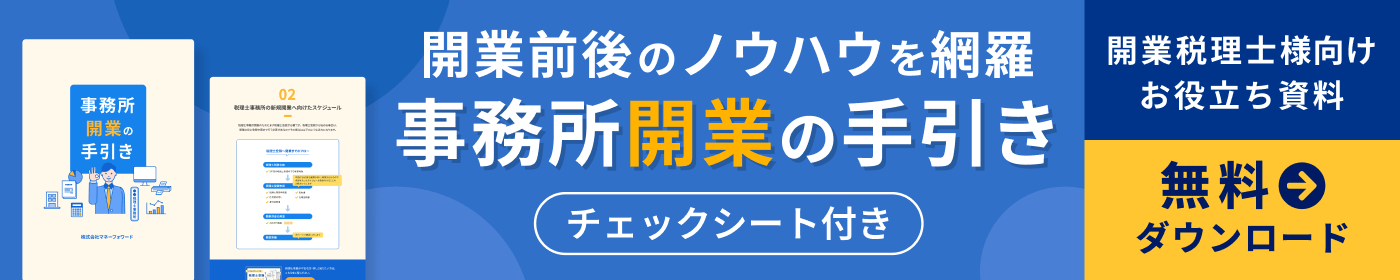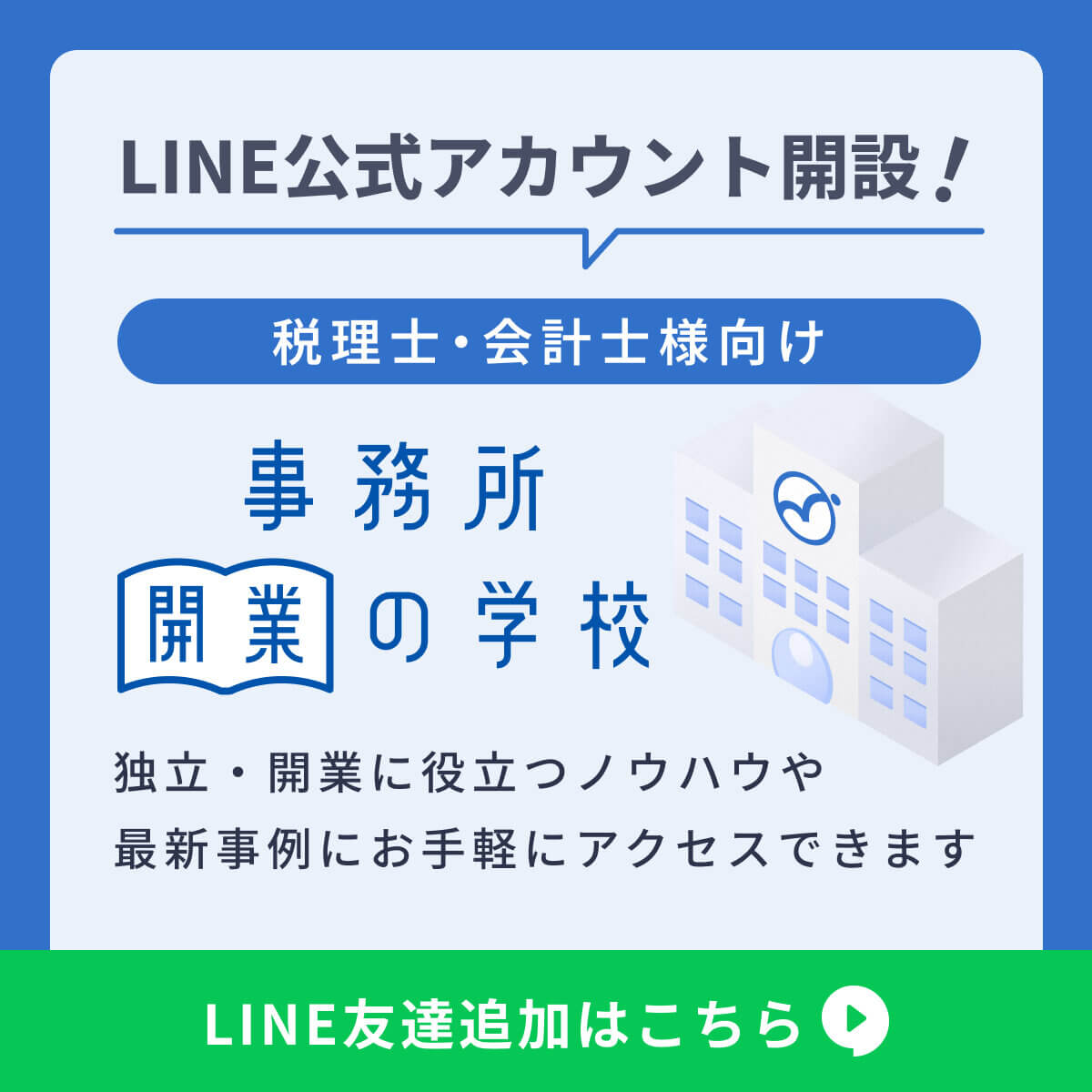公認会計士は専門性や需要が高い仕事であり、独立・開業は難しくありません。独立後は、税務業務やコンサルタントなど、さまざまな道があります。しかし、自身で仕事を獲得しなければならず、競合も多いため、成功のためには自身の強みを持つことが大切です。今回は、公認会計士の独立・開業後の仕事内容や、成功のポイントなどを解説します。
目次
公認会計士の独立・開業は楽?
公認会計士の独立・開業は決して楽ではありません。しかし、事前準備や失敗しないためのポイントを押さえれば難しくはなく、自身で事務所を構えて活躍している方は多数存在します。
公認会計士は、会計のプロフェッショナルです。税理士事務所を開業する、コンサルタントになる、社外CFOを務める、セミナー講師になるなど、独立後の道が複数用意されています。
公認会計士は難関資格であり、専門性の高い仕事であるため、市場価値は高いです。
そのため、その専門性を活かせる仕事であれば、独立・開業は難しくはないでしょう。
税理士登録をして税務業務を主にする場合が多い
公認会計士として独立する場合、税理士登録をして税務業務を担当するケースが多いです。
公認会計士の資格を持っていれば、税理士試験を受けることなく税理士になれます。
また、税務業務をメインにすることで、個人から中小企業まで多くのクライアントから仕事を獲得できる可能性が高いです。毎月顧問料を獲得でき、経営が安定しやすいというメリットがあります。
公認会計士として独立・開業するメリット
公認会計士として独立・開業することには、以下のようなメリットがあります。
- 初期費用や経費をかけずに起業できる
- 業務の自由度が広がる
- 専門性を活かせる
- 女性が活躍しやすい
それぞれ見ていきましょう。
初期費用や経費をかけずに起業できる
公認会計士として独立・開業する際は、初期費用や経費があまりかかりません。税務業務やコンサルタント、セミナー講師などで独立する場合、会計士本人がいればビジネスが成り立つためです。
もちろん、人件費や備品代、事務所を開所する場合は事務所代などの費用がかかります。しかし、倉庫で在庫を抱えたり、機械設備を使ったりするビジネスに比べると、初期費用や経費の負担を抑えられるのがメリットです。
そのため、独立・開業のハードルが低く、初期投資も比較的すぐに回収できるでしょう。
業務の自由度が広がる
公認会計士として独立・開業すると、自身で仕事を選べるようになるため、業務の自由度が広がります。
自身の得意分野に近い案件や、興味がある案件、相性がよいクライアントからの案件などを中心に引き受けられるため、ストレスなく、やりがいをもって働ける可能性が高いです。
また、働く場所や時間、仕事の進め方なども自分で決められるため、ライフスタイルに合わせて、働き方を調整できます。
専門性を活かせる
公認会計士は会計のスペシャリストであり、その専門性を活かせる仕事は多く存在します。
税務関連の業務やコンサルティング、M&Aのサポートなど、さまざまな仕事で、公認会計士としての専門性を活かして活躍できるでしょう。
幅広い分野の仕事を担当し、さらにスキルや実績を獲得できれば、より多くの仕事に挑戦できるようになり、キャリアアップにもつながります。
女性が活躍しやすい
公認会計士としての独立・開業は、特に女性にとってメリットが大きいです。
そもそも、公認会計士業界は実力主義の傾向が強いため、性別に左右されることなく評価されやすく、女性も活躍しやすいという特徴があります。
独立・開業すれば、さらに自身の裁量で働けます。業務内容や作業量、業務時間などを、体調やライフイベントなどに応じて自身でコントロールできるため、ワークライフバランスを実現しやすいです。
公認会計士として独立・開業するデメリット
一方、公認会計士として独立・開業することには、以下のようなデメリットもあります。
- 収入が不安定になるリスクがある
- 日本公認会計士協会の費用を負担する必要がある
- 集客や顧客開拓が必要である
- 競争が激しい
デメリットについても理解したうえで、独立・開業するかを慎重に検討しましょう。
ここでは、独立・開業する4つのデメリットを解説します。
収入が不安定になるリスクがある
独立・開業の大きなデメリットは、収入が不安定になるリスクがあることです。
公認会計士として独立することで、年収が大きくアップする可能性もあります。一方、仕事を獲得できなければ収入を得られません。体調を崩して稼働できなくなった場合でも、事務所がサポートしてくれるわけではないため、収入がゼロになってしまうリスクもあります。
収入を安定させるためには、公認会計士の独占業務である法定監査と任意監査以外の業務も行い、安定的に仕事を受注できる体制を整えなければなりません。
日本公認会計士協会の費用を負担する必要がある
独立すると、これまで会社や監査法人が負担してくれていた日本公認会計士協会の費用を、自身で全て負担しなければならない点にも注意しましょう。
15万〜16万円程度の費用を、毎年支払う必要があります。
また、独立をきっかけに正会員として登録する際は、さらに入会金40,000円や施設負担金50,000円などの支払いが必要です。
集客や顧客開拓が必要である
独立した後は、自身で仕事を獲得しなければなりません。人脈を広げて仕事を紹介してもらったり、セミナーを開催して集客したりなど、集客や顧客開拓を行う必要があります。
そのためには、公認会計士としてのスキルや実績はもちろん、自身を売り込む営業力や交渉力、コミュニケーション能力などが求められます。また、交流会やセミナーなどに参加して人脈を広げようとする、フットワークの軽さも重要です。
競争が激しい
公認会計士として独立した後は、競合との激しい競争に勝つ必要があります。
公認会計士の資格を持っている人は、2023年8月時点で、全国に約35,000人です。難関資格ではあるものの、「公認会計士」という肩書きのみで仕事を獲得できる可能性は低いです。
さらに、独立して税務業務を行う場合は税理士、コンサルタントとして開業する場合は、ほかのコンサルタントが競合になり、さらに競合が増えます。
生き残るためには、自身の強みを明確化し、アピールすることが大切です。
公認会計士として独立・開業後の仕事内容
独立・開業するにあたって、どのような仕事で公認会計士が活躍できるのかを理解しておきましょう。
ここでは、公認会計士として独立・開業した後の、具体的な仕事内容について解説します。
- 会計事務所での税務業務
- 財務・会計のコンサルティング
- M&A、IPO中心のコンサルティング
- 経営のコンサルティング
- 金融に関するセミナーの講師
会計事務所での税務業務
税理士資格を取得し、会計事務所を開業するパターンです。
公認会計士から税理士になる際は、税理士試験の全科目が免除され、2年間の実務経験も必要ありません。登録手続きは必要ですが、税理士になるハードルが低いため、税務業務を行なって売上を確保するケースが多く見られます。
税務に関する知識や実務経験は必要ですが、公認会計士としての専門性も活かして活躍できる仕事です。
なお、税理士登録のためには、登録費用や年間維持費用がかかります。合計で30万円ほどかかるため、コストを理由に税理士登録をしない方も少なくありません。
財務・会計のコンサルティング
公認会計士としての専門性を活かし、税務や会計のコンサルタントとして独立するパターンもあります。
コンサルタントは、特別な資格がなくても始められる仕事です。競合は多いですが、公認会計士は企業の経営課題の分析や解決策の立案に活かせる専門知識を持っているため、コンサルタントとしても活躍しやすいでしょう。
中でも、公認会計士の仕事と強く関連しているのが、財務・会計のコンサルティングです。
M&A、IPO中心のコンサルティング
コンサルタントの中でも、M&AやIPOなど、企業のエグジットを支援するコンサルタントになるという選択肢もあります。
公認会計士は、IPOを支援したり、M&Aにおいて企業価値評価と財務デューデリジェンスを行ったりする役割を担います。その知識や経験を活かすことにより、企業のM&AやIPOについて適切なアドバイスができるでしょう。
経営のコンサルティング
コンサルタントの中でも、経営コンサルタントとして独立するパターンもあります。
経営コンサルタントは、クライアントが抱える経営課題に対して、専門的な視点から解決策を提案する仕事です。コンサルティングを行うためには、さまざまな資料や調査から経営状態を正しく診断し、業績アップのためにアドバイスをする必要があります。公認会計士としての知識や経験を大いに活かせる仕事です。
金融に関するセミナーの講師
金融機関が実施するセミナーの講師や、企業が従業員向けに実施する社内研修の講師、専門学校の講師になる、という道もあります。
セミナー講師を引き受けることで人脈が広がり、セミナーの依頼者や参加者から、税務やコンサルティングなどの大きな案件を受注できる場合もあります。
また、セミナー講師として知名度が高まれば、書籍を執筆する機会を獲得できる可能性もあり、自身の活躍の幅をさらに広げられるでしょう。
公認会計士として独立・開業する年齢は?
公認会計士として独立・開業する年齢に、絶対的な正解はありません。
「独立しよう」と思い立ち、不安や悩みよりも意欲や期待が高まっているときがおすすめです。早く独立・開業することで、自身で案件を獲得して1人で進める、という環境に、より早く順応できます。
一方、独立後の未来に対する期待やモチベーションよりも、不安や悩みの方が大きいのであれば、やめておいたほうが賢明です。
公認会計士の独立・開業で年収はどうなる?
公認会計士として独立・開業した後の年収は、1,000万円以上が目安とされています。
独立した場合、自身で引き受ける案件や稼働時間などを調整できるため、年収を青天井で上げていくことが可能です。スキルや実績次第では、3,000万円以上を獲得することも夢ではありません。
ただし、上記はあくまでも目安であり、一概にいくら稼げる、とは言えません。個人の能力や引き受ける案件数、案件単価などによって年収は大きく異なるため、年収に差がある点には注意が必要です。
公認会計士として独立・開業に向いている人
公認会計士として独立・開業に向いている人の特徴は、以下のとおりです。
- コミュニケーション能力が高い人
- 人脈を作るのが上手い人
- 新しい知識を得るのが好きな人
- マネジメントや管理職の経験がある人
それぞれ解説します。
コミュニケーション能力が高い人
クライアントとスムーズなコミュニケーションをとったり、案件を獲得したりするためには、高いコミュニケーション能力が求められます。
特に、コンサルティング業務を行う場合は、コミュニケーション能力が欠かせません。クライアントと密なコミュニケーションをとり、会話の中から相手が抱える悩みや要望、意見などを正しく汲み取る必要があるためです。
人脈を作るのが上手い人
案件を獲得するためには、人脈作りが重要です。
独立後は、自身で案件を獲得しなければなりません。特に、開業初期はアピールできる実績が少ないため、なかなか信用してもらえず、集客に苦労するでしょう。
監査法人内での人脈や、さまざまな経営者との人脈を築ける方なら、仕事を紹介してもらえる可能性が高く、安定的に案件を獲得できるでしょう。
新しい知識を得るのが好きな人
知的好奇心が強く、新しい知識を積極的に身につけようとする方は、独立・開業に向いています。
知識の幅が広がれば、クライアントからの幅広い要望や期待に応えやすくなります。また、新しい技術やツールの情報を素早くキャッチアップして業務に活かすことで、競合と差別化できる可能性も高いです。
知識を積極的に吸収しようとする貪欲な方は、独立しても成功しやすいでしょう。
マネジメントや管理職の経験がある人
マネジメントや管理職の経験があれば、従業員を雇って組織が大きくなった際も、円滑に組織運営ができます。
組織を拡大してうまく回せるようになれば、より多くの案件に取り組めるようになり、業績アップが期待できます。メール返信や資料作成などのノンコア業務をほかの従業員に任せ、本業に集中できる体制を整えることも可能です。
公認会計士の独立・開業後に何をすればいい?必要な手続き
公認会計士が個人事業主として独立・開業する際は、開業届の提出と、公認会計士協会の登録変更手続きが必要です。
以下で詳しく解説します。
開業の届出
個人事業主として開業する際は、税務署に「個人事業の開業・廃業等届出書」を提出しましょう。
事業の開始等の事実があった日から1ヶ月以内(提出期限が土・日曜日・祝日等にあたる場合は、その翌日まで)に提出する必要があります。
青色申告で確定申告をしたい方は、同時に「所得税の青色申告承認申請手続」を提出するとスムーズです。
参考:国税庁 A1-5 個人事業の開業届出・廃業届出等手続
参考:国税庁 A1-9 所得税の青色申告承認申請手続
公認会計士協会の登録変更
公認会計士が独立する際は、日本公認会計士協会の公認会計士名簿の登録情報を変更しなければなりません。変更が生じた後、直ちに登録申請書を日本公認会計士協会に提出する必要があります。
なお、公認会計士としての登録を抹消する、あるいは準会員を退会したうえで新しいビジネスに取り組む場合は、日本公認会計士協会の会員登録グループにメールを送りましょう。必要な手続きと書類を、別途案内してもらえます。
公認会計士として失敗しないためのポイント
公認会計士として独立・開業し、失敗しないためのポイントは以下のとおりです。
- 監査以外の幅広い業務の経験を積む
- 得意分野、専門分野を持つ
- 人脈の幅を広げ信頼関係を保つ
それぞれ解説します。
監査以外の幅広い業務の経験を積む
ほかの公認会計士と差別化するためには、監査以外の幅広い業務の経験を積みましょう。公認会計士が監査業務についての知識やスキルがあるのは、ある意味当然です。独立して成功するためには、監査以外の幅広い業務の経験を積み、自分ならではのサービスを提供することが求められます。
また、営業活動やマーケティング、採用などについても経験や知識があれば、クライアントとも対等に話せるようになり、信頼を獲得できるでしょう。
得意分野、専門分野を持つ
得意分野や専門分野を持つことで、ほかの公認会計士にはない、自分ならではの強みを発揮できます。
前述のとおり、公認会計士として独立した後は競争が激しく、競合と差別化できなければ、思うように案件を獲得できず失敗してしまう可能性があります。
得意分野と専門分野を見つけてアピールし、それを発揮できる仕事を積極的に請け負えるようにしましょう。
人脈の幅を広げ信頼関係を保つ
独立前、独立後ともに、人脈を広げ、さまざまな人から信頼される公認会計士になることも欠かせません。
人脈を広げ、信頼関係を構築することで、出会った人から案件を紹介してもらい、ビジネスチャンスを獲得できる可能性が高まります。優秀なビジネスパートナーに出会えることもあるでしょう。
ただし、人脈が広ければ広いほどよいというわけではありません。中には、怪しい話を持ちかけてくる人もいるため、付き合う人を自身で見極めることが大切です。
強みを磨いて公認会計士としての独立・開業に成功しよう
会計のプロフェッショナルである公認会計士は、専門性が高い仕事であり、市場価値も高いため、独立・開業は難しくないでしょう。税理士登録して税務業務を行う、専門知識を活かして経営コンサルタントになる、金融に関するセミナーの講師になるなど、さまざまな選択肢があります。
公認会計士として独立して成功するためには、監査業務以外の実務経験を積むことや、競合に負けない専門性を磨くこと、人脈を広げ、信頼してもらうことが重要です。
「事務所開業の手引き」をお手元に
公認会計士の独立形態としては、「税務+コンサルティング」のサービスを提供する税理士事務所・会計事務所が大きな選択肢となります。税務サービスを入口とすることで、毎月の顧問料が安定した収入源になるうえに、コンサルティングサービスへのアップセルも狙えます。
マネーフォーワードでは、独立を目指す公認会計士に向けて、税理士事務所・会計事務所の開業のポイントを整理した「事務所開業の手引」をご用意しました。会計事務所の開業を検討されている方はぜひダウンロードしてみてください。
よくある質問
開業は自宅でも問題ない?
最初は自宅でも問題ないでしょう。コロナ禍以前は直接お会いしてミーティングする場合が多かったですが、コロナ禍以後は、最初のミーティングからWEBミーティングで行う場合が一般的になりつつありますので、軌道に乗りだしてからも自宅でよいかもしれません。しかし、ある程度収益が安定すれば、事務所が別にあったほうが、信用度は高くなるでしょう。
独立開業に向いている人は?
自分で営業獲得して無限に稼ぎたいという野心家や、自身で営業獲得する必要があることからコミュニケーション能力に長けている人、組織に拘束されず自分の自由な時間が欲しいという人が独立開業に向いているでしょう。
税務を行う場合、勉強はどう行う?
TACの税法実務スキルアップ講座等で申告書の書き方を習得する、開業後しばらく知人の公認会計士、税理士等の事務所で手伝いをさせてもらいながら実務を習得するとよいでしょう。5件から10件程度申告書を作成すれば中小企業の税務レベルなら十分対応可能かと思われます。